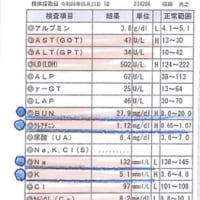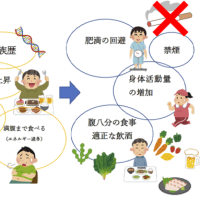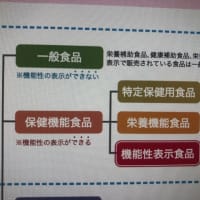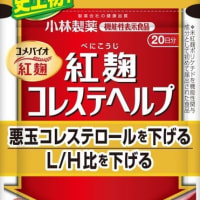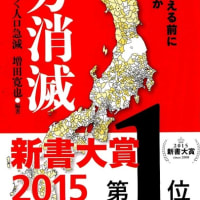過失と医療事故の因果関係、法的責任の考えは、かつては過失があるか否かがまず重要であった。その上で、例え過失があっても死亡等の悪い結果がそれによって引き起こされたのでなければ、医療側は法的責任を負う必要はなかった。これは私共にとって対応の拠り所でもあった。
しかし、因果関係の考え方もこの10年でかなり変わってきた。
2000年代になって、最高裁が判決の中で採用したのが「相当程度の可能性」という考え方である。「相当程度の可能性」というのは、過失と不利益との問に「高度の蓋然性」があるとまでは言えないが、「その可能性は相当にある」と判断されれば、数100万円程度の慰謝料を認める、とする考え方である。
この概念はとても分かりにくい。私は「高度の蓋然性」とは「限りなく黒に近い灰色」を指し、「相当程度の可能性」は、「いろいろな濃さの灰色」を示すと理解している。灰色の色調にクリアな線引きがあるはずもないから評価は難しいのだが、灰色のままで大雑把に決めてしまおう、と言うことである。
要するに、過失と迄ははっきりと言えないが、医療機関側に一定の落ち度はあったのだから、多少なりとも賠償をすべきと言うことである。過失と結果の間に確固とした因果関係がを証明しなくても良いのだから、ある意味で感情論的でもある。しかし、2000年代以前に.「期待権」と言うもっと茫洋とした感情論的考え方があった。これが近年「相当程度可能性」に姿を替えたが、これによって「期待権」からある程度の「因果関係認定」と言うことになるから、感情論は若干ながら後退するだろう。
今後の問題点としては「相当程度の可能性」理論がどのような状況にまで適用されるのかである。広く適応されれば、医療を受けた患者に何かの不利益・実害があれぱ安易に適用される可能性がある。対象範囲があまりにも広がれば、例えば後遺障害が無くとも医療側がやるべき医療行為をしなかった、と提訴され、賠償責任が認められてしまう事にもなる。
これでは医療は到底成り立たない。だから、今後の動きを見守らなければならない。
また、最近知ったのであるが、和解交渉、示談交渉の中でも「相当程度の可能性」理論を応用して事をまとめる動きも出てきているようだ。
しかし、因果関係の考え方もこの10年でかなり変わってきた。
2000年代になって、最高裁が判決の中で採用したのが「相当程度の可能性」という考え方である。「相当程度の可能性」というのは、過失と不利益との問に「高度の蓋然性」があるとまでは言えないが、「その可能性は相当にある」と判断されれば、数100万円程度の慰謝料を認める、とする考え方である。
この概念はとても分かりにくい。私は「高度の蓋然性」とは「限りなく黒に近い灰色」を指し、「相当程度の可能性」は、「いろいろな濃さの灰色」を示すと理解している。灰色の色調にクリアな線引きがあるはずもないから評価は難しいのだが、灰色のままで大雑把に決めてしまおう、と言うことである。
要するに、過失と迄ははっきりと言えないが、医療機関側に一定の落ち度はあったのだから、多少なりとも賠償をすべきと言うことである。過失と結果の間に確固とした因果関係がを証明しなくても良いのだから、ある意味で感情論的でもある。しかし、2000年代以前に.「期待権」と言うもっと茫洋とした感情論的考え方があった。これが近年「相当程度可能性」に姿を替えたが、これによって「期待権」からある程度の「因果関係認定」と言うことになるから、感情論は若干ながら後退するだろう。
今後の問題点としては「相当程度の可能性」理論がどのような状況にまで適用されるのかである。広く適応されれば、医療を受けた患者に何かの不利益・実害があれぱ安易に適用される可能性がある。対象範囲があまりにも広がれば、例えば後遺障害が無くとも医療側がやるべき医療行為をしなかった、と提訴され、賠償責任が認められてしまう事にもなる。
これでは医療は到底成り立たない。だから、今後の動きを見守らなければならない。
また、最近知ったのであるが、和解交渉、示談交渉の中でも「相当程度の可能性」理論を応用して事をまとめる動きも出てきているようだ。