私はここ20年来文献上で歴史を学んでいる。
私の中で勉強不足で大きく欠損していた分野という自覚があったからである。しかしながら、有名人を中心に語られる一般的歴史よりは古い民話やお伽話の中の庶民の生活を中心とした歴史(?)が好きである。
よく読む資料としては、稲田浩二「日本昔ばなし通観」、柳田國男「改訂版日本昔ばなし」、大島ひかり氏等の著書、そのほかを中心に読んでいる。
昔話の主役はお爺さん・お婆さんで、総じて老人である。若いピチピチの人の話はあまり語られていない。その登場人物の老人達はいつも笑顔で幸せそうに見えるが、これは明治初期に一気につくられた教育用の編纂による改変の結果で、私もすっかり最近まで騙されていた。
実際の昔話の原典にある老人の姿は「貧困・孤独・嫉妬」にあるようだ。
昔話から知ることができる老人は「地位はとても低く」、「生きるのに難渋」していたようだ。
「舌切り雀」や「笠地蔵」、「かちかち山」は高齢者単独夫婦世帯。
「かぐや姫」や「桃太郎」は子のない老夫婦が、偶然、子供を見つける話。
「聞き耳頭巾」の如くの独居老人の話、も少なくない。
昔話の老人はとても貧乏で、生きている間はあくせく働かねばならなかった。
「お爺さんは山へ柴刈りに、 お婆さんは川で洗濯に」は昔話の定番であり、お爺さんは刈った柴を背負って町に出て売って細々と生活している。体力的に大変な状況が読み取れる。
「笠地蔵」のお爺さんなどは、大晦日のぎりぎりまで笠を売りに町へ出かけている。それでも食べるものにもこと欠いている。どちらかが倒れたら先がない。
昔の老人は、子や孫がいても、役に立たなくなれば厄介者として「捨てられる」ことが多かったようだ。
更に、昔話の老人は「善良な老人」と「悪い老人」が近所に住み、最後は「悪い老人」が妬みのために破滅する。
要するに、過酷な「生き残り」の世界がそこにあった。
昔話の頃の老人は「社会の厄介者のミノリティ」であったと思われるが、昔話の中ではなぜか主役を演じている。対して、今の日本は超高齢化社会・老人社会といわれ、 新聞・雑誌・ネットなど、あらゆるメディアに老人に関する話題が上がらぬ日はない。現在の老人は「社会のマジョリティ」で「社会の隠れた主役」でもある。「老人が金を貯め込むから経済が回らない」、「年金・医療・介護費が国を滅ぼし兼ねない」、などど揶揄されるなどの問題も抱えている。
陰の主役などではなく真の主役かもしれない。

















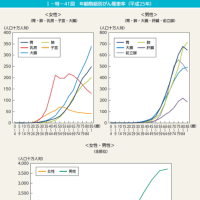


昔話を含めて先人たちの残した記録は私の貴重な指針です。