
公開中の映画の原作本。
漫画が省略の芸術であることを再認識できる。
たとえばコマとコマの間。映画なら連続したフィルムのどれとどれを選択するかということだ。他はすべて省略してしまう。その「コマ」にしても実写は画面の隅まで作りこまないとリアリティが欠如してしまう。漫画は何を描いて何を描かないかを作者がコントロールできる。
このことが大きな効果となって現れるのが被爆後10余年のヒロシマを描く、第1部の「夕凪の街」だ。映画に比べるとさらに過酷な状況をコミックはこの省略の技法で描き出す。省略と言うより「何も描かれない」ラスト近くの描写が最も衝撃的といえるだろう。
映画はその部分が柔らかい夢のような描写になっている。
もし映像で忠実に表現するなら真っ暗な画面に声だけが聞こえてくるのだろうか。コミックはそこを白い画面で表現している。人間の意識がだんだん薄らいでいくとき何色が見えるのだろう。
コミックは3部構成で、映画の「桜の国」はさらに2つのパートに別れている。第2部「桜の国(一)」はヒロイン七波の幼少時のエピソードで、この時期に被爆者である七波の母と祖母が他界する。
第3部「桜の国(ニ)」はヒロイン26歳のエピソードで、二つのパートの間で一家は引越しをしている。
七波は以前住んでいた桜の美しい街をあまり好きではないことが分かる。それは二人の死の記憶が残る街だからだ。
しかしその街は首都圏郊外の、「広島の記憶」とは無縁の美しい街だ。その街の象徴のようにヒロインの幼馴染、東子が登場する。作者自身の「ヒロシマ」との距離感を体現しているのがこの東子のようだ。
家族の死と転居でヒロインの中の「ヒロシマ」は封印されたはずだったが、第3部で再びその封印が解かれる。封じ込めるのではなく、それをどう受け止め、これからの人生を歩んでいくかを、ヒロインは自分で決めなくてはならないのだ。
という話が、ここに書いたほど深刻ではなくむしろ淡々と描写される。それは登場するキャラクターの造形のおかげでもあり、コミックという「省略の表現」を特徴とするメディアの力でもあるのだろう。










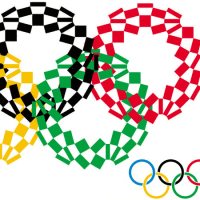

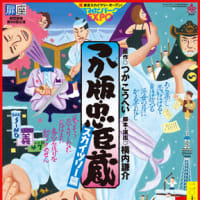







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます