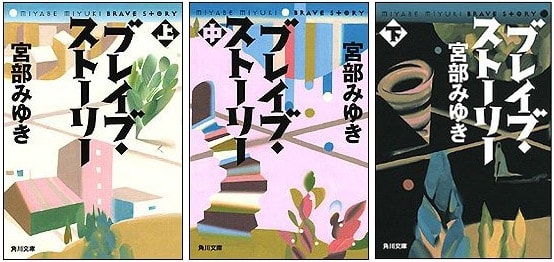リオ・オリンピック開催中なので、しばらくは話題から遠ざかる東京オリンピックです。
エンブレムはシックなブルーで小さなパーツが知的に組み上げられており、見るたびに少しずつ好感度がアップしていきます。
このエンブレムに五彩を施し、オリンピックの五輪マークを描いてみました。
要素となる円が太いので、オリジナルのマークでは2色しか重ならない部分で「3色重ね」が出現します。
この部分の上下関係をどう描くかがポイントですが、エンブレム・パーツを一つずつ分けて処理しすれば解決します。
エンブレムはシックなブルーで小さなパーツが知的に組み上げられており、見るたびに少しずつ好感度がアップしていきます。
このエンブレムに五彩を施し、オリンピックの五輪マークを描いてみました。
要素となる円が太いので、オリジナルのマークでは2色しか重ならない部分で「3色重ね」が出現します。
この部分の上下関係をどう描くかがポイントですが、エンブレム・パーツを一つずつ分けて処理しすれば解決します。