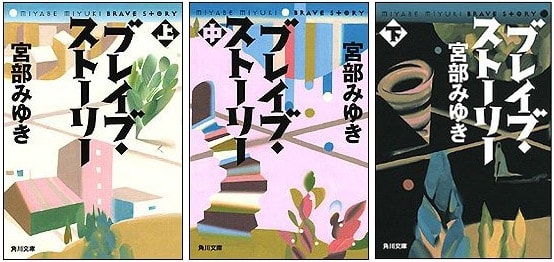今週で終わるというのでもう一度見た。ドラマとしてのふくらみをじっくり味わえ初見時よりさらに面白く感じた。
スーパーマンが父親として、息子の中に自分自身を見る視点が良く描かれている。物語の主軸は、マーロン・ブランド演じる父親からスーパーマンへ、そしてその息子へと受け継がれていく、男系社会の秩序の中に描かれるロマンなのだ。
これからも続くこの一族の長い歴史の中で、いつか男の子が生まれなかった場合は「スーパーマン典範」の改正を議論することになるのだろう。
子役のラストネームがリーブ。もしやと思ったが先代スーパーマンはReeve、子役はLeabuだった。カタカナ表記すると同じだが英語の響きはまったく別。日本人が苦手なrとl、vとbの組み合わせだ。
夕暮れ時の空を、事件性を帯びないでスーパーマンがスーッと飛んでいく情景は夢のように美しい。
スーパーマンが父親として、息子の中に自分自身を見る視点が良く描かれている。物語の主軸は、マーロン・ブランド演じる父親からスーパーマンへ、そしてその息子へと受け継がれていく、男系社会の秩序の中に描かれるロマンなのだ。
これからも続くこの一族の長い歴史の中で、いつか男の子が生まれなかった場合は「スーパーマン典範」の改正を議論することになるのだろう。
子役のラストネームがリーブ。もしやと思ったが先代スーパーマンはReeve、子役はLeabuだった。カタカナ表記すると同じだが英語の響きはまったく別。日本人が苦手なrとl、vとbの組み合わせだ。
夕暮れ時の空を、事件性を帯びないでスーパーマンがスーッと飛んでいく情景は夢のように美しい。