銀座でたった1日だけ開催された展示会「Life on Wheels」を観てきました。
昨年、一昨年がコロナ禍で中止になっていたので、今年が3回目の開催です。
ポスターにあります通り、「人、車、バイクが織りなす情景模型」というコンセプトで、ジオラマという手法を通して、ひとつの物語やシーン、時代感などが表現された作品の展示会です。
従いまして、ピッカピカのカーモデルがズラッと並んでいる展示会ではありません。
12人の有名モデラーさんが作品を出品されていて、当然会場にも居られるので色々お話を聞いたりすることもできます。
当日は35℃を超える猛暑日でしたが、東京都下多摩地区の田舎から電車を乗り継いで1時間半くらい掛かって行った訳ですが、その価値は十二分にありました。
私が一番お目当てにしていたのは斎藤マサヤ氏と松本洲平氏の作品でしたが、両氏共に期待を上回る素晴らしい作品でした。
勿論、他の10人の皆様の作品も眼福の極みです。
斎藤マサヤ氏の作品です。
氏は50~60年代の音楽やファッションと車やバイクをアレンジした、凄くハイセンスなジオラマ作品を作られていますが、今回は60年頃の”Mods”をテーマにした作品です。
この作品のバイクもライダーのファッションも当時のMods族そのものです。
ライダーが着ているモズコートの背中には「The Who」(Modsを代表するロンドンのバンドでパンクロックの元祖とも言われています)と書かれていますし、バイクにも「Mod」の文字があちこちに書かれています。
そして何よりも泣かせるのが、台座になっているEP盤のアナログレコードです。
なんと本物の輸入盤のスモーキー・ロビンソン(Mods族の音楽のルーツであるモータウンのR&Bの代表的なアーティストの一人です)の物です。
バイクは海外の架空ホバーバイクのガレージキットをベースにスクラッチされた物で、全長僅か10cm程の大きさです。
バイクやフィギュアの出来映えも驚異的ですが、ジオラマとしてのセンスとストーリー性が素晴らしいです。
齋藤氏とは4月の「5人の仕事展」でもお話をさせて頂いたのですが、今回もModsやモータウンの事などを中心に10分くらいお話をさせて頂く事ができました。
氏はこのバイク&フィギュアを更に6台製作中で、来年の展示会ではMods族の集団ジオラマが観られるかも知れません。



松本洲平氏の作品です。
1/32のキットを使ったガレージのジオラマですが、氏が昔実現できなかった「マイ・ガレージ」をジオラマで再現された作品です。
細かい工具や車のディテールまで、隅々まで全くスキの無い素晴らしい情景です。
一番驚いたのは、壁際の作業台の上に無造作に置かれたギター(僅か2cmくらいの大きさ)にちゃんと弦が6本張られていることです。
作品カードは全ての作品に統一のデザインで、きちんと額縁に入れて飾られているのも良いです。


伊藤康治氏の作品です。
1967年のイタリアGPで優勝したホンダRA300のスタート前のシーン前です。
ジョン・サーティーズと中村監督が写真とソックリです。


カワサキのSS500も出品されていました。
ヤマモン氏の作品です。

故、塚本康仁氏の作品です。
急に降り出した夕立の光景がショーウィンドウの灯りに照らされて雨水で光る歩道と車のボディの雨粒で表現されています。
雨音が聞えてきそうですね。

藤田祐樹氏の作品です。
典型的なアメリカの警官のおやつタイムのスナップです。
定年が近そうなメタボな警官とちょっと草臥れたパトカーが良い味を出しています。


他にも素晴らしい作品が沢山ありましたが、長くなりすぎますのでこのくらいにしておきます。
今回の展示会で凄く新鮮だったのは、身近な「車」や「バイク」を映画や音楽、それぞれの時代背景や作者の思い出、印象的なシーンと合わせて、ジオラマという手法で作品に仕上げるという世界です。
単なるプラモデル作品という枠を超えて、ひとつの芸術作品に領域に達しているような気がしました。
絵や彫刻に近いです。
<オマケ>
銀座通りなんて何十年ぶりでしょうか?
完全にお上りさん状態です。
日曜日のホコ天にも関わらず人出は少なかったです。
あまりの猛暑のせいだと思います。
ティファニー、ブルガリ、ダグホイヤー、カルティエ、ラルフローレン・・・名だたるブランドが勢揃い。
その中に吉野屋があるのも面白いですね。














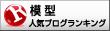





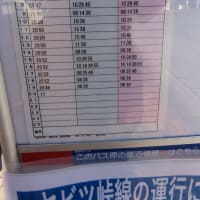











表現することが車だけでなくその物語を、
想像させる いちシーンに見えます。
うちのクラブの代表が思い描いてる作家さんの
集まる作品展なのです。
ヤマモン氏の黄色のアルファも素敵です。
プラモデルを作って楽しむという領域を超えて、プラモデルを使って様々な「表現」をする・・・つまり芸術の領域に入っていると感じました。
高い工作技術が必要なことは言うまでもありませんが、それ以上に発想力や表現力、模型の対象物に対する造詣が必要になってくると思います。
飛行機や船など、他の分野でも同じような表現ができると思います。
しかし・・・私にはどうあがいても無理そうです。
齋藤氏の作品は50~60年代の社会、音楽やファッションと模型とが結びついた表現が魅力です。
これまで拝見した他の作品にも共通しています。
氏のご年齢からすればお生まれになっているかどうかという時代なんですが、この時代への思い入れがかなりお有りのようです。
私の年代の人間にはドンピシャ嵌まります。
ヤマモン氏の作品はスタジオジブリの短編事件作品「On Your Mark」のワンシーンをモチーフにした作品で、黄色いアルファはそのまんまです。
「Life on Wheels」のご紹介、ありがとうございます。
興味は感じつつ、日曜日に銀座まで出るのがちょっとヘヴィーに感じて日和ってしまいました(汗!)。
平日なら仕事サボって見に行ってたと思います・・・(オイッ!)。
どれもアイデアが素晴らしいですね、作家の方々それぞれがどんな人生観を持って生きて来たのかという事まで想像できそうな気がします。
個人的には塚本康仁氏の「夕立」に1票です。
幌を被せないまま夕立に見舞われたシーンが日常の中にありながら裏切られた非日常感というか絶妙な世界観が秀逸だと感じました。
どの作品もですが、こんな風に作れたら最高ですね。
この展示会のタイトル「Life on Wheels」・・車輪人生が象徴していますね。
作者それぞれの車やバイクを介した人生観が垣間見えます。
塚本氏の「夕立」も良いですね。
「日常の中にありながら裏切られた非日常感」素晴らしい表現だと思います。
恐らくお店から出てきたミニスカのご婦人がドライバーで、買物を終えて出てきたら夕立で愛車が中までびしょ濡れ・・・「オーマイガー~~」
通りがかりの親子連れが心配そうに見ています。
なんだか会話まで聞えてきそうです。
塚本氏は一昨年にお亡くなりになられましたが、ご遺族からお預かりした氏の作品をLife on Wheelsのメンバーが出品されている物です。
氏の作品は19年に別の展示会でも拝見しましたが、やはり素晴らしい作品だったことを憶えています。
ホント、こんな風に作れたら最高ですよね。
いいものを見せていただきました。ありがとうございます。
アイデア、センス、対象物や時代に対する見識、作品と仕上げるスキル・・・これらが高次元で合体した作品を堪能してきました。
くうさんにも楽しんで頂けて光栄です。
私には全て不足していますが、少しづつでも近付きたいという願望だけはあります。