プラモデルとプラモデル屋さんの移り変わりについて、振り返ってみたいと思います。
ちょっと長くなりますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
最初は1950~60年代の黎明期です。
私は1950年代半ばの生まれなので、私が物心ついた頃には既にプラモデルという言葉があり、国産のキットもありました。
でも、この頃はまだ「プラモデル屋さん」という専門のお店は僅かしか無く、プラモデルはおもちゃ屋さん、百貨店の玩具売場、文房具屋さんや駄菓子屋さんの片隅で売られているのが殆どでした。
つまり、この頃の店主はブームになり始めたプラモデルを商売のネタとして置いていたという、ただそれだけのことでした。
次がプラモデルの黄金期です。
1960年代の後半、私が小学校の高学年の頃になると、
スケールモデル・戦争物だけではなく、サンダーバードなどのキャラクター物なども出てきて、国産メーカーも増え、輸入キットも広く出回るようになり、一大ブームが来たように思います。
月刊モデルアートが創刊されたのもこの頃で、プラモデルが子供の玩具だけではなく、大人のホビーとして定着してきた時代でもあったと思います。
私がプラモデルを作り始めたのは1965年か66年頃で正にこの時期です。
イマイのサンダーバードなども作りましたが、スケール物がメインでレベルのファイターシリーズ(当時はなんと1個100円で買えました!)を作り倒していました。
この時代になると、プラモデルを専門に扱う「プラモデル屋さん」がかなり増えてきて、一つの街に1軒はあるという感じになってきました。
店先には必ずガラスのショーケースがあって、大人が作った素晴らしい(少なくとも当時はそう見えました)作品が並んでいました。
子供の手が届かない棚の上の方には何千円(今の感覚では何万円)もするモノグラムのキットがありました。 文字通り「手の届かない」存在でしたね。
こういうお店は店主も「おもちゃ屋さんのオヤジ」や「文房具屋さんのおばちゃん」ではなく、模型好きのおじさんや、モデラーになってきました。
つまり、この時代、プラモデルキットは「プラモ屋さん」で、店主や常連客の大人にいろいろ教わりながら買うものであり、子供から見れば、店主は専門家、先生でもあった訳です。
正月になると、貰ったばかりのお年玉を握りしめた子供たちがプラモデル屋さんの店先に群がったのも、この頃の光景です。
こんな状況が1970年代一杯まで続いたと思います。
私は1971年頃までプラモデル作りに熱中していましたが、中学卒業と同時にプラモデルも一旦卒業してしましました。
ちょっと余談ですが、時代背景として重要なことなので・・・。
私も含めて当時の小中学生はナイフ、彫刻刀、ハサミ、金槌、ノコギリなどを使って工作や造形ができるのが、当たり前でした。
次に訪れたのが、1980年代のガンプラブームです。
この頃の私はプラモデルには全く興味が無かったので、詳しいことは判りませんが、ガンプラブームの陰でスケールモデルは衰退の一途を辿ったと思います。
私がプラモデル作りに出戻ったのは、1996年(阪神淡路大震災がきっかけ)で、約25年のプランクがあります。
その間に、この業界の勢力図も大きく変わり、キットの製造方法やパーツの精度も飛躍的に向上しました。
でも一番大きく変わっていたのは、プラモデルは「子供の楽しみではなくなっていた」ということです。
メーカーの技術もモデラーの技量も、完成品のレベルも昔とは比較にならないほど向上しましたが、プラモデルは完全に「中高年のホビー」となっていました。
今の若い人達の大多数にとってプラモデル=ガンプラであり、スケールモデルキットに興味を持つ子供や若者は貴重な存在(ちょっと変わった人、オタク、JKからは「キモイ!」なんて言われかねない・・・)です。
ゲームやネット、テレビが今の子供や若者の楽しみであって、自分の手先を使って物を作り上げるということを殆どしなくなってしまいました。
前半の余談で書いたことが、今の子供や若者の殆どが出来ないんです。
(鉛筆の持ち方を見ればよく判ります。)
つまり、プラモデルキットを作るための基本的な素養が身に着いていないんです。私の子供もそうです。
そして、街を見渡すと、個人経営の「プラモデル屋さん」は殆ど見掛けなくなり、僅かに残ったお店も次々と閉店していきました。
出戻った1996年当時は私の生活圏内に個人経営のプラモデル屋さんが数軒ありましたが、今ではゼロです。
じゃぁ、現代はどこでプラモデルを買うのか?
日本全国どこでも・・という意味では、なんと言ってもインターネット上の通販でしょう。
アマゾンや楽天など大手から、個人経営のプラモデル屋さんまでインターネット通販が主流になっています。
絶版キットを手に入れるにはヤフオクなんて方法もあります。
日本全国、パソコンやスマホでインターネット環境が整い、宅配便網やコンビニの普及と相まって、便利になったものです。
また、プラモデルというのは、所謂「ロングテール商品」であり、ネット販売に非常に向いていることも事実です。
もうひとつは、都市部に限られると思いますが、タムタムやボークスに代表されるような会社組織の大きな専門店、一部の家電量販店、秋葉原の専門店などです。
これらのお店に共通しているのは、お店が広い、綺麗、見やすい、選びやすいということです。
つまり、現代の成熟した(贅沢で我儘な)消費者が当たり前に求める「小売店舗」としての常識を満たしているお店です。
スーパーや色々な専門店と同じように「快適に買い物ができるお店」です。
昔ながらの「プラモデル屋さん」が、実は一番弱いのが、この辺りではないでしょうか?
1970年代の黄金期に商売を始めたプラモデル屋さんが、そのまま現代まで続いていたとしても、その商売のあり方が既に時代に合わなくなってしまっているのではないかという気がします。
あの当時の様な子供や大人は、もう居なくて、中高年の中のごく一部に生き残っているだけなんです。
あと20~30年もすると、居なくなってしまいます。
1960~70年代の黄金期に沢山出来た「プラモデル屋さん」は既に40年以上経ち、私たちが子供の頃の先生でもあった店主も既に老人となり、今更プラモデル屋さんを継ごうという後継者も無く、閉店してしまう例も多いようです。
いずれにしても、今の調子でマーケットが縮小してくると、限られた地域という小商圏では商売として成り立たず、ネットを介して全国を相手にして初めて成り立ってくるのでしょう。
個人でお店を構えていたとしても、実はネットの売上が殆どなんていうお店が生き残るのでしょうね。(ホビーショップガネットさん等はその好例ではないかと推測します。)
長々と書いてしまいましたが、プラモデルという素晴らしいホビー(楽しみ)が、少しでも長く続いていくことを祈ります。










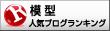





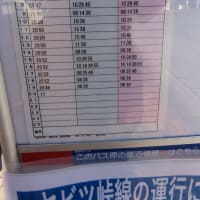














たぶん私自身もkurakinさんと同年代だと思いますが、そのせいか、おっしゃることがいちいち腑に落ちる気がします。私自身は仙台市在住なのですが、やはり模型店の衰退が著しく、大きな街のはずなのに塗料ひとつ買いに行くのでもおおごとになっています。プラモデルは風前のともしび(の一歩手前)というのは、模型店を訪れるさいにいつも実感していることです。そう言う自分自身も安く便利なネットでキットを購入していますので、町の模型屋さんの衰退に一役買っているのがなんとも皮肉ですが。ただプラモデルは製作に高度な技術を要しますので、おっしゃるとおり、ほんらい大人の趣味では?という気持ちも片方にあります。ただ(私もそうなのですが)子どもの頃に親しんだ模型への懐古の思いが多分にあり、実質そうした中高年だけの楽しみになり果てているのはやはり健全な姿とは言えないという気もします。正当な趣味として新たに若い?大人たちが参入してくるようだといいのですが。(貴ブログでご披露されているような素晴らしい完成品の実物を間近に見られる場所があると模型製作へのつよい誘いになるとは思うのですが、模型屋さんがつぎつぎに消えてゆくご時世では難しいでしょうね…。)
まとまりのないコメントになっちゃいましたが、ブログのほうは今年も楽しみに覗かせていただきます。
今年もよろしくお願いいたします。
仰る通り、以前にも似たような記事を書いた記憶があります。
世の中の無数の趣味がある中で、プラモデルは将来性が心配される趣味のひとつであることは間違いないでしょうね。
凄く悲観的になってみたり、時には「そんな心配することないよ」と思ってみたり、揺れ動いています。
でもひとつ確かなことは、全人類が過去数千年以上に渡って営んできた「手先、指先、単純な道具を駆使して物を作る(造形する)」ということが急速に衰退していることです。
ごく一部の芸術家や職人さんを除いて、明らかにこの分野の人間の能力は退化しているでしょう。
小中学校の図工の授業に3Dプリンターを導入しようなどという案も出ているそうです。
「そんな能力は50年後の人間には無用だから」と言い切れるのかどうか判りませんが、私は非常に危機感を感じます。
粘土をこねたり、木を彫ったりして動物や人形を作ったりすることのできる人がこの世から居なくなることを想像してしまいます。
「模型」という趣味は残ったとしても、それをプラモデルのような形で作り上げるという趣味は、将来的に少なくとも産業としては成立しなくなる可能性が高いように思えますが、このブログやサークルの作品展などを通してプラモデルの楽しさを伝えていければ幸いです。
時間もかかり時にはうまくできないこともある模型よりもてっとり早く楽しめるのでどうしてもそちらに流れてしまったのでしょう。
もし息子の小学生~中学生の時に自分が模型を作って与えたり、一緒に作ったりしたら多少変わっていたかもしれませんが残念ながら30代の頃は仕事の追われてその余裕がありませんでした。なんせ出戻ったのが7~8年前の50歳手前の頃ですから。
孫が出来てその頃にまだ作れる力が残っていればなんとか模型の楽しさを教えたいとは思っています(笑)
テレビゲームというか、コンピュータゲームの台頭は遊びの世界を大きく変えてしまいました。
一言で言えば、「能動」から「受動」に変えてしまったと思います。
予め用意されたプログラムに従って、全て受け身で遊ぶのがコンピュータゲームの世界です。
自分で能動的に何かを造り出すということはありません。
私も一時期嵌まりましたが、それが判ってしまうとつまらなくなりました。
そういう私も、自分の子供たちに物造りの愉しさを教えられず、普通の今風の大人になっちゃいましたね。
私の場合自営で卒業後も店の後を継ぎ、お勤めを経験しなかったからでしょうか、割と時間あるのでそれと根がのんびり屋でも有り、結婚、子育て中でも時間見つけては作り続けてました、当然近所の模型屋さんの常連でした。一応ガンプラ以外の全てのジャンルこなし、数、経験では誰にも負けない自負があります。
また小坊、中坊時も大人でも買うのをためらうキットを沢山作れました、なぜかというと行きつけの模型屋の親父に見本つくりを頼まれていたからです。いわゆる白箱でメーカが数買った店に送られてくる、見本品(箱絵がなく、発売前のサンプルもありました)もので、さすが海外キットはなく全て国産でした。塗装工具は自由に使わせてもらいましたが、さすがエアブラシは無理で全て筆で塗装してました。これでかなりのスキルが出来たみたいです。調子に乗って一部改造して逆に商品と違ったらだめと怒られたりしました。
当時自分の周りもプラモデルにはいい印象はなくモデラーなんて言ったらフルスクラッチのソリッドモデラーの事でプラモは子供のおもちゃ程度の認識で出来上がり保証されてるもの作って何が面白いといわれましたが今は全くソリッドモデラーの圏域に滑り込んだようです、近年展示会に作品持込、お話聞くとチョイ寒気がします。
昨今、メードイン、ジャパンの勢いが無いのも関係有りです。
仲間内でも海外の古い作りにくいキットを作るのに燃えるのに、鞭で打たれるのを喜ぶかの様な表現で言われることもあり、キットも作りやすくなった事も何かモチが下がるような気もします。難度の高いゲームをクリヤした気分味わう自分が異常なのでしょうか。???ですから私がガンプラ作らないのもそのためです。
いやぁ、凄い歴史ですねぇ。
それだけの経験があるからこそ、あの素晴らしい腕前があるんですね。
私は多分SOMAPさんの1/10くらいの経験しかありませんよ。
子供の頃から今まで通算したって、恐らく完成品の数は120~30、最大限多目に見ても150個ですよ。
昔はソリッドモデルが正統派でしたね。
確かにプラモデルは子供向けのイメージがありました。
私たちの年代は、敢えて難物に挑戦しようという面がありますが、今の若い人には通用しないでしょうね。
そういう私も、最近は「出来の良い」キットに走る傾向が明白です。(笑) 歳のせいでしょうか。