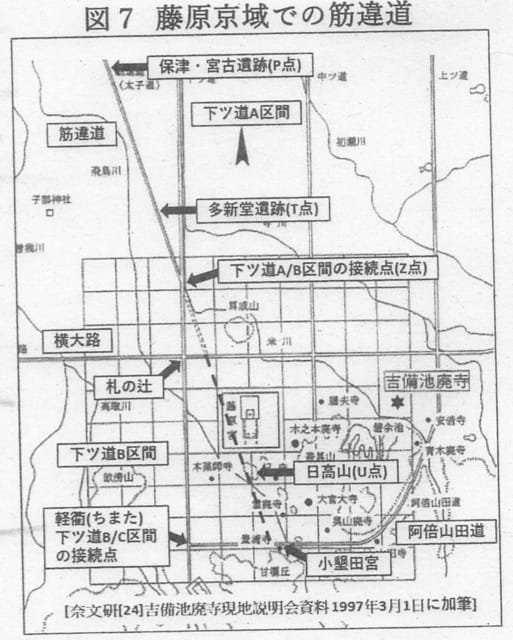天皇号の成立は論争中で決着してませんのでどう呼ぶかで困りますが、その人を呼ぶ鴇は漢字諡号を用い、斉明までは「大王」、天智以後を「天皇」と呼ぶという方針を示したのが、
藤森健太郎「古代の皇位継承と天皇の即位」
(吉村武彦・吉川真司・川尻秋生編『シリーZ古代史をひらく2 古代王権―王はどうして生まれたか』、岩波書店、2024年)
です。「大王」は美称であって、実質は「王」だという吉村武彦説も考慮したうえでのやり方です。何しろ、この本の編者筆頭は吉村氏なので。
大王について、ある程度信頼できる記述を含む記し方が目立ってくるのは継体からですが、その継体は五世王であって畿内の皇統から遠いため、仁賢大王の娘である手白香と結婚したことは良く知られています。その継体と尾張目子媛の間に生まれ、いろいろ議論の多い安閑大王と宣化大王も、仁賢大王のそれぞれ娘を婚姻しています。
そして、継体と手白香の間に生まれた欽明大王も、宣化大王の娘である石姫と婚姻しており、ここまでは、継体とその系統の大王は、それ以前の大王の系統の女性を通じてつながりを確保していたことがわかります。それ以前は、大王の系統の女性と結婚しても、有力氏族の女性と結婚しても大きな違いは無かったのに、この時期から王女を重視し、近親結婚を含めて王族の凝集性を高めたことが指摘されています。
欽明と王女の石姫の間に生まれた敏達の場合、王族である広姫との間に押坂彦人が生まれていますが、欽明は蘇我稻目の娘たちを妃として用明、崇峻、推古をもうけており、敏達は王族の広姫を皇后とすると同時に、蘇我氏の血を引く推古を妃としていました。
つまり、蘇我氏は外戚として力をつけていったのですが、そのためには、王統が特殊な系統として確立している必要があります。藤森氏は、外戚としての蘇我氏の発展を、王統の確立と平行するものと見、氏族のまとまりもこの時期に確立していったと見ます。
これは妥当ですね。戦前の見方では、確立していた皇統の外戚となった蘇我氏が横暴にふるまったとされていたのですが、王統の確立と蘇我氏による外戚の地位の確立は平行する出来事だったのです。
私は前から、中国の北朝や新羅の例を見ても、王権の強化とそれを支える特定の臣下の権勢は同時のものと考えていました。「憲法十七条」は蘇我氏の専横を押さえるための法ではなく、「憲法十七条」が「承詔必謹」を説くことと、その「詔」を出す天皇を、群臣の上に立つようになった大臣が国政指導の強い権勢を持つことは、まったく矛盾しないと思われるのです。冠位十二階でも、大臣は授ける側でしたし。しかも、「憲法十七条」を作成した聖徳太子はその大臣の親戚であって娘婿でした。
藤森氏は、王族系の王統と、蘇我氏系の王統の違いに注目しつつ、両方の路線が交差する場合も少なくないとします。これはけっこう後まで続きますね。
藤森氏は、当時は妻問い婚が風習であった以上、妃たちが一つの後宮にともに住むのではなく、大王との間に子をもうけた有力な女性がそれぞれの根拠地に割拠したのであって、それぞれの母系の子のトップが大兄だったと見ます。6世紀から7世紀にかけて、兄弟相続が普通だったように見えるのは、分散するそれぞれの母系の筆頭が候補者として並立していたためと見るのです。
このため、特定の王族と支援する氏族の結びつきが強まり、系列化が進んだ結果、対立の危機が強まったとする佐藤長門氏の主張を評価します。
そして、そうした系列の中で、大王候補や崇峻大王が殺され、ふさわしい年齢に達していた大王候補がいなくなっていた結果、猶予期間をつくるため、能力も評価されていた推古が即位したと見ます。そして、厩戸は過渡的な制度としての「太子」であったとする同書の「序」での吉村説を紹介したうえで、そうした制度は有効でなかったと説きます。
以下、推古朝以後について論じており、天智天皇はライバルになる別系統をすべて排除したものの、自分の子には条件の揃った後継者がいない状況で晩年を迎えたとし、また後継者争いが発生してしまったこと、さらに以後の展開も説かれています。