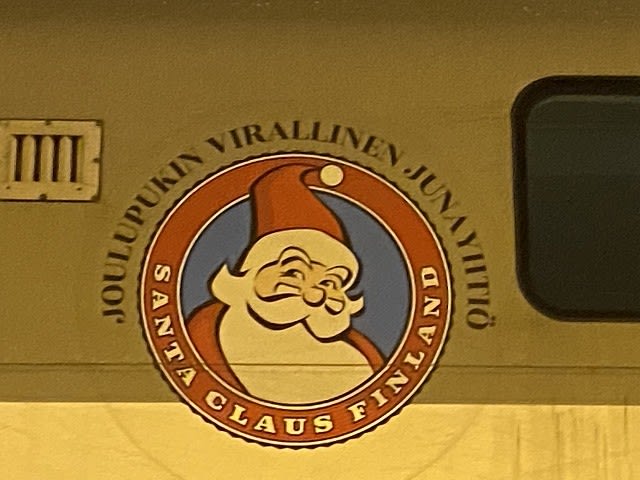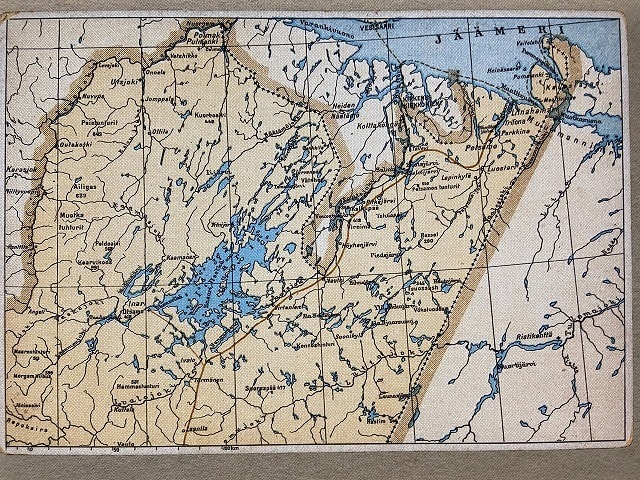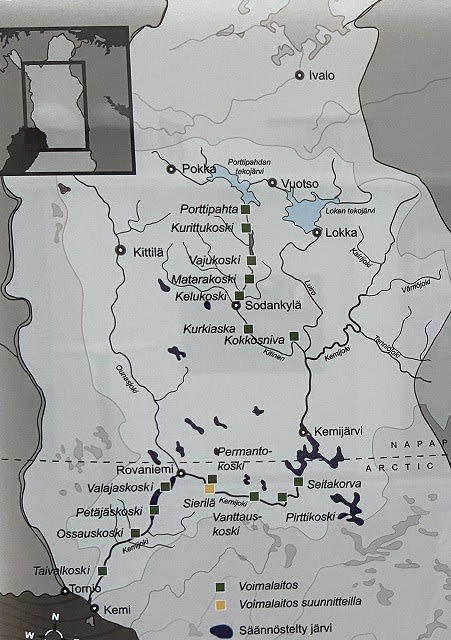朝九時半、港に面したヘルシンキ市庁舎が朝日をあびている。

この建物はロシア支配時代にはホテルだったそうだ。
右隣はスウェーデン大使館。
フィンランドはロシアの前にはスウェーデン領だった。
そのまた隣にフィンランド大統領官邸(この位置からだと見えない)
さらに奥にはロシア正教教会の尖塔が見えている↑
↓冬の時期、港のマーケットに出ている店はすくない。
ロシア皇帝時代の記念碑がぽつんとたっている↓

ここから道をわたって五分もせずに元老院広場に至る。
↓階段の上には白亜のルター派大聖堂。

ロシア時代になって首都がトゥルクからよりロシアに近いヘルシンキに移転された時に整備された広場
↓実際ヘルシンキ駅からロシアのサンクト・ペテルブルグまで、この「アレグロ」号で三時間ほどで行けてしまう現在。

今日は時間があるから階段をのぼって教会の中へ
足元はフィンランドらしい美しい花崗岩

内部はプロテスタントらしくシンプル。
かつて皇帝が下賜した祭壇の絵


↓聖書をフィンランド語に訳した16世紀のミカエル・アグリコラの像

***
定番のテンペリアウキオ教会へももちろん行こう。
↓導線をぐるぐる巻いてできた天井がUFOのよう↓

空いた堂内に静かなピアノが響いている。
↓ほんとうのテンペリアウキオ教会の見どころはここではないと、小松はおもっている。
↓見るべきは屋上と、そこから見る周囲の都市計画

冬の時期は雪が多いので、小松が「行きましょうよ」と言っても、ガイドさんが「すべりやすいのでやめましょう」と却下されることが多いのだが・・・
今年は雪がないので登れました(^.^)

建築というのは環境そのものだから、周囲の建物が調和していなければ成り立たない。
この円盤のような建物をかこむように丸く集合住宅が配置されているのだ。
最初予定していたデザインの教会が出来ていたら、世界中から見学者がくるような教会にはなりえなかっただろう。
↓雪のないときに、足元に注意してのぼってみましょ(^.^)



この建物はロシア支配時代にはホテルだったそうだ。
右隣はスウェーデン大使館。
フィンランドはロシアの前にはスウェーデン領だった。
そのまた隣にフィンランド大統領官邸(この位置からだと見えない)
さらに奥にはロシア正教教会の尖塔が見えている↑
↓冬の時期、港のマーケットに出ている店はすくない。
ロシア皇帝時代の記念碑がぽつんとたっている↓

ここから道をわたって五分もせずに元老院広場に至る。
↓階段の上には白亜のルター派大聖堂。

ロシア時代になって首都がトゥルクからよりロシアに近いヘルシンキに移転された時に整備された広場
↓実際ヘルシンキ駅からロシアのサンクト・ペテルブルグまで、この「アレグロ」号で三時間ほどで行けてしまう現在。

今日は時間があるから階段をのぼって教会の中へ
足元はフィンランドらしい美しい花崗岩

内部はプロテスタントらしくシンプル。
かつて皇帝が下賜した祭壇の絵


↓聖書をフィンランド語に訳した16世紀のミカエル・アグリコラの像

***
定番のテンペリアウキオ教会へももちろん行こう。
↓導線をぐるぐる巻いてできた天井がUFOのよう↓

空いた堂内に静かなピアノが響いている。
↓ほんとうのテンペリアウキオ教会の見どころはここではないと、小松はおもっている。
↓見るべきは屋上と、そこから見る周囲の都市計画

冬の時期は雪が多いので、小松が「行きましょうよ」と言っても、ガイドさんが「すべりやすいのでやめましょう」と却下されることが多いのだが・・・
今年は雪がないので登れました(^.^)

建築というのは環境そのものだから、周囲の建物が調和していなければ成り立たない。
この円盤のような建物をかこむように丸く集合住宅が配置されているのだ。
最初予定していたデザインの教会が出来ていたら、世界中から見学者がくるような教会にはなりえなかっただろう。
↓雪のないときに、足元に注意してのぼってみましょ(^.^)