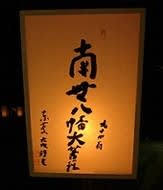○戸栗美術館 『館蔵 鍋島焼名品展』
http://www.toguri-museum.or.jp/
というわけで(前日を参照)、根津美術館を予定より早く切り上げることになってしまったので、この展覧会に寄ることにした。
「鍋島焼」は、肥前(佐賀県)鍋島藩の焼き物である。鍋島藩は、有田皿山を拠点に、海外貿易や日本国内の需要に即した磁器(有田焼=伊万里焼)を製造する一方、将軍家への献上品や諸大名・公家への贈答品を特別に製造する藩窯を別に開いた。この、採算を度外視し、美の極致をきわめた(と言われる)特別あつらえの磁器を「鍋島焼」と呼ぶ。
とにかく「鍋島」は美しい。それも、侘びだの寂びだの、気難しい爺さんがこねまわすような理屈はなくて、誰の目にも、まっすぐ飛び込んでくる美しさである。見ているだけで幸せな気持ちになる。
しかも、長い年月の間に、さまざまな改良や工夫が加えられていて、なかなかに奥が深い。今回の展示でも、藩主から「最近は焼きの質も悪いし、文様もマンネリである。何とか工夫せよ」という改善命令が下された記録が残っていて、興味深かった。
そんな叱咤に応えて生み出されたデザインのひとつが、清新な更紗文様である。鍋島といえば、青海波とか雪輪繋ぎとか、大人の”和”のイメージが強かったが、こんな可愛らしい文様もあると知って意外だった。でも、赤や黄色を惜しみなく使っているにもかかわらず、品のよさを失わないところは、さすが鍋島。
鍋島藩は、磁器産業のほかに、更紗(染織)や緞通(どんつう=敷物に使う厚手の織物)も保護したと言われている。実は、その鍋島更紗の文様を、磁器に転用したものらしい。いやあ、鍋島藩って、おもしろいなあ。こういう手工業の真剣な育成にかけた小藩って、なんか、じわじわといいなあと思った。
http://www.toguri-museum.or.jp/
というわけで(前日を参照)、根津美術館を予定より早く切り上げることになってしまったので、この展覧会に寄ることにした。
「鍋島焼」は、肥前(佐賀県)鍋島藩の焼き物である。鍋島藩は、有田皿山を拠点に、海外貿易や日本国内の需要に即した磁器(有田焼=伊万里焼)を製造する一方、将軍家への献上品や諸大名・公家への贈答品を特別に製造する藩窯を別に開いた。この、採算を度外視し、美の極致をきわめた(と言われる)特別あつらえの磁器を「鍋島焼」と呼ぶ。
とにかく「鍋島」は美しい。それも、侘びだの寂びだの、気難しい爺さんがこねまわすような理屈はなくて、誰の目にも、まっすぐ飛び込んでくる美しさである。見ているだけで幸せな気持ちになる。
しかも、長い年月の間に、さまざまな改良や工夫が加えられていて、なかなかに奥が深い。今回の展示でも、藩主から「最近は焼きの質も悪いし、文様もマンネリである。何とか工夫せよ」という改善命令が下された記録が残っていて、興味深かった。
そんな叱咤に応えて生み出されたデザインのひとつが、清新な更紗文様である。鍋島といえば、青海波とか雪輪繋ぎとか、大人の”和”のイメージが強かったが、こんな可愛らしい文様もあると知って意外だった。でも、赤や黄色を惜しみなく使っているにもかかわらず、品のよさを失わないところは、さすが鍋島。
鍋島藩は、磁器産業のほかに、更紗(染織)や緞通(どんつう=敷物に使う厚手の織物)も保護したと言われている。実は、その鍋島更紗の文様を、磁器に転用したものらしい。いやあ、鍋島藩って、おもしろいなあ。こういう手工業の真剣な育成にかけた小藩って、なんか、じわじわといいなあと思った。