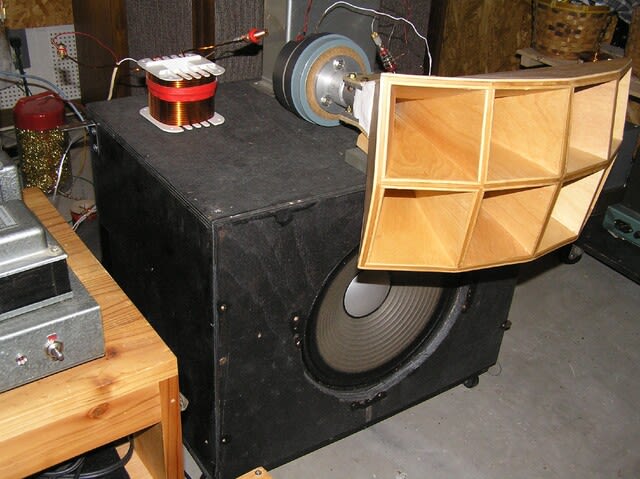3日前の早朝のこと、いつものようにブログを創ろうかと「グーブログ」を開けてみたら、「ブログサービスを終了します」の文字が目に入った。
え~っ、これは・・、と思わず絶句しましたねえ。「青天の霹靂(へきれき)」とはこのことです!
いきなりですから、ビックリしますわいなあ~。「グーブログ」といえば、通信業界の不沈戦艦「NTT」がバックに控えているので、安心しきっていたのにこの有様。
サービス終了の原因といえば、これは推察だけど昨年(2024)の年末だったか、ブラックルートを通じて大量の情報を送り付けられ、処理しきれなくてサーバーがダウンしたことがありました。2日ほどで復旧しましたが、その対策の困難性などが遠因ではないでしょうかね。
ウィルス対策に膨大な費用が掛かることは小耳にはさんでいますが、たしか、現在の1か月あたりの課金は300円程度で、加入者320万人だから、1か月で9億6千万円の商いですけどそれでも足りないのかなあ?
いずれにしても、悔やんばかりでも仕方がないので、今後の選択を迫られてきます。つまるところ、二者択一です。
「他のブログへ移行するか」or「19年間もの長い間ご愛顧をいただき、ありがとうございました」という「店仕舞い」をするか・・、始まりがあれば終わりがあるのが世の倣い、もうこの辺が潮時かもね~。「管理」の問題もあるので、一人娘が帰省した時にじっくり相談してみます(笑)。
拙いブログで質的にはイマイチでしたけど、量的には(現時点で)記事数が「3768」件、使用した画像が「7768」枚ですが、全てお蔵入りになります。まあ、個人的には記録媒体を使って保存しておくつもりですけどね。
それこそ退職後の暇つぶしの積りで始めたブログでしたが、まったく予想外のロングランの展開を見せる中、見ず知らずの様々な方々との交流はまことに得難く貴重なものでした。心から感謝してます。そして余禄として筆者の「ボケ防止」にもきっと役立ったはずです(笑)。
とはいえ、まだしばらく猶予期間が残されていますのでどうかお付き合いくださいね~。
最後に「チャットGPT」さんに訊ねてみました。
「gooブログ」が2025年11月18日にサービスを終了する理由について、公式には明確な説明がされていませんが、複数の報道や関係者の見解から以下のような要因が考えられます。
主な終了理由と背景
-
システムの老朽化と保守の困難化
20年以上にわたる運用により、システムの老朽化が進み、保守が難しくなったことが終了の主な理由とされています。 -
収益性の低下と競争の激化
無料ユーザーが多く、有料プランへの依存度が高かったため、収益化が難しかったと考えられます。また、他社との競争も激化し、運営継続が困難になった可能性があります。 -
インターネット環境の変化
SNSや動画配信プラットフォームの台頭により、従来型ブログサービスの需要が減少しました。スマートフォンの普及に伴い、古いウェブサイトやアプリへの対応が難しくなったことも影響していると見られます。
サービス終了までのスケジュール
-
4月16日:ブログ引越し・データダウンロード機能提供開始
-
4月21日:書籍化機能再開(有料ユーザー向け)
-
6月9日:アプリ版有料会員新規受付停止、アプリ版課金停止
-
7月1日:新規ブログ開設終了
-
8月1日:新規Web版有料会員受付停止
-
9月30日:gooブログアプリ終了
-
10月1日:新規記事・コメント投稿終了、有料課金停止
-
11月18日:サービス終了(全ブログが閲覧不可に) KAI-YOU | POP is Here .+3Impress Watch+3Gooブログ+3アメーバブログ(アメブロ)+2Gooブログ+2Impress Watch+2CNET Japan+1アメーバブログ(アメブロ)+1
ユーザーへの対応策
NTTドコモは、ユーザーが他のブログサービスへ移行できるよう、4月16日から「引っ越しデータ作成」機能を提供しています。データは一般的なMT形式で提供され、多くの他社サービスで対応可能です。ただし、絵文字や画像パスなど一部内容は手動で修正が必要となる場合があります。 Yahoo!ニュース+3アメーバブログ(アメブロ)+3Impress Watch+3
「gooブログ」の終了は、多くのユーザーにとって寂しいニュースですが、時代とともに変わりゆくインターネット環境を象徴する出来事でもあります。利用者は早めにデータ移行や保存作業を進めることで、大切な思い出やコンテンツを失うことなく次へとつなげられます。