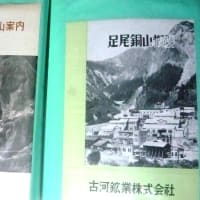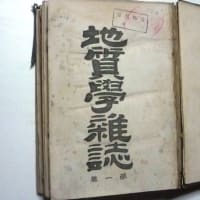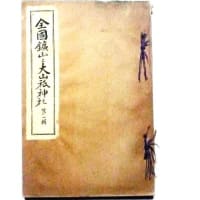皇室の宝物「三種の神器」
我が国の有史において、歴代天皇が皇位の標識として受け継いだ宝物に「三種の神器」がある。三種の神器とは、広辞苑によれば、
- 八咫の鏡(やたのかがみ)
- 天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)
- 八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)
である。
勾玉の原石と「玉造」
この中で、最も興味を惹くのが古代の宝石、「曲玉」(勾玉とも書く。以下これに統一して記述)である。緑色をした勾玉の原石となった主要鉱物は、碧玉(玉造石、ジャスパー)と翡翠(硬玉、ジェイド)と緑玉髄(クリソプレース)である。最初は、朝鮮半島を経由して中国からもたらされたものであろうが、その後は国内の各地でも模倣して勾玉が制作され、「玉造」という地名が日本の各地にあることからみて、製作工房としての「玉造部」が発生し、権力の象徴的装飾品としての「勾玉」を生産し、古代社会に流通させたものと思われる。最も著名な場所は、日本の代表的な碧玉の産地でもある島根県の玉造温泉の花仙山である。そして、玉造の近くには出雲大社がある。
碧玉以外の原石
碧玉以外の原石で、最も色鮮やかなものとなると、「翡翠」である。日本各地の古墳等から出土する勾玉の中には、かなりたくさん翡翠製品が見られる。これらの殆どは新潟県糸魚川市を流れる姫川の上流、小滝のものであり、市内の姫川流域には、翡翠を加工していた集落跡を示す遺跡が発掘されている。緑玉髄は、日本では良質のものが多量に採れる場所がなかったのか、国産品は殆ど見られない。しかし、我が国は比較的水晶にめぐまれ、水晶製の勾玉の出土例は少なくなく、その工房跡も幾つか発見されている。三重県下では、津市一志町にその例があるが、かつて当地で多量に出土した半製品や水晶の原石を見ると、県外より持ち込まれた県外産水晶の可能性が高い。
勾玉の石材、あれこれ
その他、伊勢市内外の遺跡から出土する遺物や古墳の副葬品を見ると、既述の鉱物以外にも色々な石材が使用されており、出土品の中には、滑石や蛇紋石を使った勾玉もある。一通り石材となった鉱物、岩石を掲げると、乳石英、瑪瑙、玉髄、軟玉(ネフライト)、黒曜石、サヌカイト(古銅輝石安山岩)、燧石(フリント)、チャート、松脂岩などである。但し、緑色系のものは蛇紋石と軟玉だけである。いずれもダーク・グリーンであり、碧玉の濃緑色や翡翠の鮮緑色には到底及ばず、石質も又、独特のトロ味のある半透明の美しさ琅�釦(ろうかん)翡翠には程遠い。
勾玉と神話のセット
筆者には、玉造温泉の碧玉と出雲大社の組み合わせが、気になって仕方が無い。勾玉と神話とのワンセットを考えれば、伊勢神宮はどうであろうか。やはり伊勢も神話の国である。天の岩戸とのセットを見れば、同様な組み合わせは宮崎県の高千穂地方と酷似し、宮崎県下には、伊勢神宮周辺の地名と同じ名前のダブリも数多くみられる。ただし、大社級の神宮は宮崎県には無い。
伊勢市近隣の「度会郡火打石」の燧石
そこで、「玉造」に代わる地名が何か無いものかと地図を調べると、伊勢市に隣接する度会郡度会町に「火打石」と言う地名があり、在所の東方の谷奥に三重県指定の天然記念物となっている「燧石」がある。ここの燧石は古生層由来の灰黒色のチャートの岩塊で、谷間の転石なのか、根のある露岩なのかは判かりにくいが、質的にはたいした物ではない。同様の岩石は付近一帯に広く分布しており、古代、石器には使用されたかも知れないが、きれいな勾玉を作れるような代物ではない。それでも、明治期までは発火道具として、この岩塊をかち割って、枡に入れて定期的に伊勢神宮に献納していたいきさつがある。多くの郷土史家らは当地の地名(火打石)の起こりを、この「燧石」の産地に結び付けているようであるが、地学的に見ると、これだけの地名が起こるには「石質」があまりにも貧弱すぎる。もっと立派な本物の「燧石」が出るか、相応の鉱化作用を受けた岩盤や鉱脈があっても不思議ではない。付近一帯は古生層に胚胎するマンガン鉄鉱の鉱床帯である故、鉄石英や熱水による珪化作用を受けた碧玉質の脈石が、近隣の栗原鉱山(跡)をはじめ、当地の河川等で産出しているからである。
彦山川にはジャスパーの転石が・・・
 筆者は、石の色や鉱山に由来する各地の地名が、相応の鉱産物の産地である点から見て、度会町の一之瀬川一帯(特に火打石の在所に流下する彦山川)には、古来、もっと「火打石」にふさわしい見栄えのする碧玉の産地があるのではないかと考えるようになり、2年ほど一之瀬川とその支流を歩き回った。その結果、緑色のきれいな幾つかのジャスパーの転石を得るに至ったが、鉱脈の露頭には行き着いていない。彦山川上流の山中から流出したものである点から見て、天然記念物以外の、当地「火打石」の地名にふさわしい、珪化作用を受けた「碧玉」の鉱脈、もしくは鉱化帯が、人知れずいずこかにあるはずである。
筆者は、石の色や鉱山に由来する各地の地名が、相応の鉱産物の産地である点から見て、度会町の一之瀬川一帯(特に火打石の在所に流下する彦山川)には、古来、もっと「火打石」にふさわしい見栄えのする碧玉の産地があるのではないかと考えるようになり、2年ほど一之瀬川とその支流を歩き回った。その結果、緑色のきれいな幾つかのジャスパーの転石を得るに至ったが、鉱脈の露頭には行き着いていない。彦山川上流の山中から流出したものである点から見て、天然記念物以外の、当地「火打石」の地名にふさわしい、珪化作用を受けた「碧玉」の鉱脈、もしくは鉱化帯が、人知れずいずこかにあるはずである。
画像上から
- 県指定、天然記念物の「燧石」(昭和53年秋 撮影)
- 火打石林道の奥の案内板
- 火打石の在所に流下する彦山川
- 彦山川産の碧玉(大:左右7㎝、小:左右5㎝)