 古山卓巳は俳優部の連中の刺すような視線を背に、撮影所に入った。セットでは伊佐山三郎カメラマンが声高にライティングの指示を出していた。その光のなかに裕次郎が笑いながら立っていた。伊佐山カメラマンが近づく古山卓巳に気づき、振り向いてカメラのファインダーをのぞいてみるようにといった。そして古山卓巳の耳元で「どうだい、阪妻の再来だよ」とささやいた。
古山卓巳は俳優部の連中の刺すような視線を背に、撮影所に入った。セットでは伊佐山三郎カメラマンが声高にライティングの指示を出していた。その光のなかに裕次郎が笑いながら立っていた。伊佐山カメラマンが近づく古山卓巳に気づき、振り向いてカメラのファインダーをのぞいてみるようにといった。そして古山卓巳の耳元で「どうだい、阪妻の再来だよ」とささやいた。
石原裕次郎、といえば1960年生まれのわたしにとっては、「太陽にほえろ!」の七曲署の係長(なんとあの威厳で係長だったのか)。あるいは酒臭そうな息で歌う「ブランデーグラス」などの演歌のイメージだろうか。
だから、彼が死んだときの大騒ぎには今ひとつピンとこないところがあったし、「西部警察」の製作中止がトップニュースになり、渡哲也が「石原裕次郎の名を汚さないように……」なんて発言をしていることには、石原プロの右翼体質以上の何かが感じられた。これは、裕次郎の鮮烈なデビューの現場をリアルタイムで知る世代が、今マスコミで“デスク”と呼ばれる重要な立場にいることが大きい。若い頃のデスク世代にとって、日活青春映画の裕次郎こそが、高度成長期の夢のシンボルだったのだ。
浦山桐郎は、会社が示した吉永小百合と浜田光夫というキャスティングは気に入らなかった。吉永小百合には貧乏のにおいがしなかった。本人が貧乏を知っているといいはっても、それは山の手の貧乏にすぎないと浦山が思っていたことのほかに、彼は日活のスターシステムそのものに強い違和を感じていたのだった。
 同じ夢を吉永小百合も体現していた。「キューポラのある街」のけなげな少女への共感を、時代と共に抱き続けたホワイトカラーたちこそが“サユリスト”であり、以後、どんな映画に出演してもその映画が駄作に帰してしまう皮肉は、時代の夢で在りすぎた吉永の当然の帰結だった……
同じ夢を吉永小百合も体現していた。「キューポラのある街」のけなげな少女への共感を、時代と共に抱き続けたホワイトカラーたちこそが“サユリスト”であり、以後、どんな映画に出演してもその映画が駄作に帰してしまう皮肉は、時代の夢で在りすぎた吉永の当然の帰結だった……
「戦後の『坂の上の雲』」という。そらおそろしいキャッチコピーがついた、石原裕次郎と吉永小百合をめぐるルポにおける関川の断定の連続には、うなずける部分が多い。しかし、昭和三十年代を歴史に押し込めるために、彼はやはり少し無理をしている。史観の押しつけが過ぎる、というか。これは「正論」というゴリゴリの右翼雑誌に連載されたという事情や、北朝鮮ウォッチャーの先駆けである関川へ、近ごろわたしが距離を取り始めていることにもよるのかもしれないが。
でも、五社協定(東宝、東映、松竹、大映、日活による俳優の囲い込み。これを破ると、要するにその俳優は徹底的に干されていく)に反発し、自らのプロダクションを立ち上げて、その存続のために石原がどれだけの辛酸をなめたかや、吉永には、後日「細雪」という傑作がある以上、素材としての魅力を読み誤った映画界の不幸に対する記述はあってしかるべきだった。
 63年5月のはじめ、「伊豆の踊子」をロケ中の下田の宿に、西河克巳監督あての電話がかかってきた。相手は「新潮」の編集長だった。彼は少なからず恐縮した口調で、「川端さんがそちらへうかがいたいといっているのですが」といった。それはいつのことか、と西河が尋ねると、「実はもう下田へきているのです」と答えた。(略)先生が実際に歩かれたのはどの道でしょうと地図を示したが、川端は今度は見ようとさえしなかった。彼の視線は徹頭徹尾吉永小百合のみに向けられていた。
63年5月のはじめ、「伊豆の踊子」をロケ中の下田の宿に、西河克巳監督あての電話がかかってきた。相手は「新潮」の編集長だった。彼は少なからず恐縮した口調で、「川端さんがそちらへうかがいたいといっているのですが」といった。それはいつのことか、と西河が尋ねると、「実はもう下田へきているのです」と答えた。(略)先生が実際に歩かれたのはどの道でしょうと地図を示したが、川端は今度は見ようとさえしなかった。彼の視線は徹頭徹尾吉永小百合のみに向けられていた。
難癖はつけたものの、少なくとも芸能裏面史としての面白さは抜群だ。実は身体が弱かった裕次郎とか、小百合を溺愛する吉永家の異常な実態とか、そして、とにかく徹底的に自動車の運転が下手だった赤木圭一郎とか……
彼らスターと、日活がふりまいた夢は、いまや団塊世代の心の中にのみ存在するのかもしれない。われわれはその夢の残り香を、知らないくせに、ただ懐かしく思う。










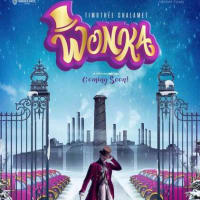















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます