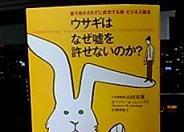ここのところ、三極(日米欧)特許庁の出願様式の統一から特許の相互承認まで、何かと気になる報道が目につくようになってきています。産業としての特許業界は各国別に出願手続が行われるという需要を前提に成り立っているので、これが覆ると相当大変なことになりそうです。財産権の境界線を決めるということは国家主権にかかわるような問題なのでそう簡単にはいかない、という説は理に適っているようにも感じますが、激変期の金融業界に身を置いた経験からすると、変革期には予期せぬことが起こり得るものなので、社会の仕組みの将来像を予測し、ある予測を前提に行動することはリスクが高いように思います。銀行のように公的資金で救われるようなことはあり得ないでしょうから、何かがあってもおかしくないと考えて準備しておくにこしたことはないのだろうと思います。
需要がある制度や規制を前提に創出されるものである以上は、その制度や規制の変化によって総需要も当然に変化するものです。変化にどのように準備しておけばよいかというのはなかなか難しい問題ですが、制度や規制を使いこなすだけでなく、それを使うことによって実現しようとしている企業の目的にまでできるだけ考察を加え、企業活動の一翼を担い得る本質的な資質を養っておく、そういうことを意識して仕事に取り組むことも一つの方法なのではないでしょうか(あまり具体性のない抽象的な結論になってしまいましたが)。
需要がある制度や規制を前提に創出されるものである以上は、その制度や規制の変化によって総需要も当然に変化するものです。変化にどのように準備しておけばよいかというのはなかなか難しい問題ですが、制度や規制を使いこなすだけでなく、それを使うことによって実現しようとしている企業の目的にまでできるだけ考察を加え、企業活動の一翼を担い得る本質的な資質を養っておく、そういうことを意識して仕事に取り組むことも一つの方法なのではないでしょうか(あまり具体性のない抽象的な結論になってしまいましたが)。