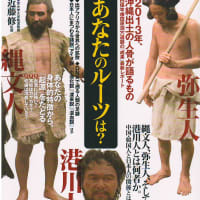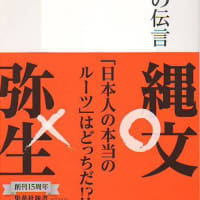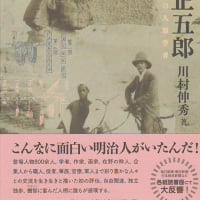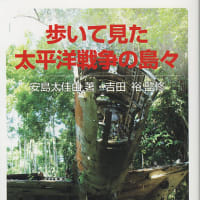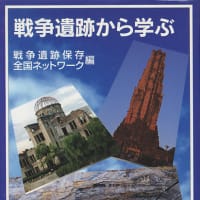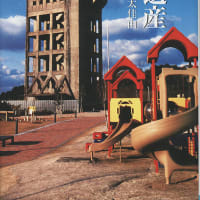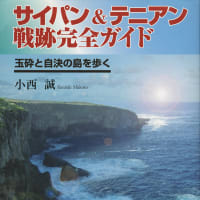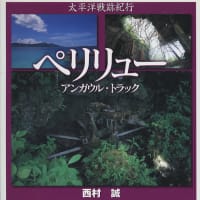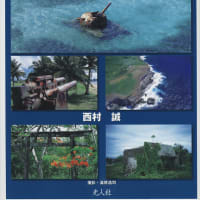山下町第一洞穴は、沖縄県那覇市山下町に所在します。1962年、当時琉球政府文化財保護委員会に勤務していた多和田真淳[1907-1990]の元に比嘉初子が訪ねてきました。比嘉初子達は洞穴を信仰しており、これまでに訪ねてきた1000箇所にも及び洞穴を天然記念物に指定してくれるよう頼んだのです。多和田真淳は、洞穴から人骨や獣骨が出土する場合がある事を説明して、もしそれらを発見した場合は連絡をしてくれるよう頼みます。やがて、比嘉初子達が山下町第一洞穴から発見したシカ(鹿)の化石を持参しました。
写真1.山下町第一洞穴の遠景(矢印が洞穴開口部)
この山下町第一洞穴は、標高約14m~15mに位置し、開口部はほぼ南西に面しており幅約1.2m・高さ約3.2mで、長さは約5.5mという小さい洞穴です。早速、琉球政府文化財保護委員会の多和田真淳と高宮広衛(現・沖縄国際大学名誉教授)は、1962年12月28日から同年12月31にかけて、洞穴の前半部約2.5mの発掘調査を行いました。この第1次調査では、叉状骨器(鹿)と石器(石弾・礫器)が発見されています。
第2次発掘調査は、東京大学(当時)の渡邊直経[1919-1999]を団長とする第1次沖縄洪積世人類発掘調査団により、1968年12月26日から1969年1月6日まで発掘調査が行われました。この調査で、小児のものと推定される大腿骨・脛骨・腓骨が出土しています。洞窟内の堆積物は約3mで、表土のⅠ層からⅥ層にまで分けられ、第Ⅲ層と第Ⅴ層に木炭が多く認められたことから生活層だと推定されました。獣骨は、第Ⅳ層~第Ⅵ層からシカ(鹿)が出土しており、総計794点中、第Ⅳ層で442点・第Ⅴ層で334点が東京大学名誉教授の高井冬二[1911-1999]により報告されています。
写真2.山下町第一洞穴第2次発掘調査の関係者[大山盛保生誕100年記念誌刊行会(2012)『通いつづけた日々』より改変して引用]
この山下町第一洞穴出土人骨の報告は、発掘調査から14年経過した1983年に東京大学名誉教授(当時)の鈴木 尚[1912-2004]により、フランスのパリ人類学会誌に英文で発表され、同年に出版された『骨から見た日本人のルーツ』にも同様の内容が発表されました。
鈴木 尚によると、人骨は石灰華に覆われて良く化石化しており、右大腿骨は約18cm(約17cmという記載もある)・右脛骨は約14cmで、復元すると右大腿骨は全長約26cm・右脛骨は全長約20cmと推定され、同一個体のもので性別不明の約7歳と推定されました。日本人の骨と比較すると、大腿骨後面にある大体骨稜が高く隆起しています。
写真2.山下町第一洞穴出土人骨前面観(右大腿骨と右脛骨)
1996年に、アメリカのニューメキシコ大学のエリック・トリンカウス(Erik TRINKAUS)とジョンズ・ホプキンス大学のクリストファー・ラフ(Christopher B. RUFF)により、再検討が行われました。彼らによると、右大腿骨の最大長は約24.5cm・左脛骨は約21.8cmと推定されるとし、死亡年齢は約6歳と報告しています。また、X線検査により右脛骨には成長遅滞を示すハリス線が3本認められました。さらに、形態からはホモ・サピエンスでは無く、古代型ホモ・サピエンスであると推定しています。
2007年に新潟の日本歯科大学で開催された第61回日本人類学会では、沖縄県立博物館の藤田祐樹等によって、山下町第一洞穴出土人骨の再検討が行われました。藤田祐樹等によると、石灰華をクリーニングし、主に縄文時代人骨と比較するとほとんどの計測項目で縄文時代人骨と変わらない事が判明し、トリンカウスとラフが提唱したような古代型ホモ・サピエンスではなく、ホモ・サピエンスであると結論づけられています。
2011年には、東京大学総合研究博物館の諏訪 元等により、東京大学総合研究博物館に所蔵されている標本を再検討した結果、右大腿骨の遠位部が発見されたと報告されています。
なお、山下町第一洞穴の年代測定は、第Ⅲ層及び第Ⅴ層から出土した木炭からおこなわれており、32,100±1,000B.P.(TK-78)と測定されており、現時点(2014年1月)では日本国内最古の人骨になります。最近話題となっている石垣島から出土した、白保竿根田原遺跡出土人骨は、約26,000年前と測定されています。山下町第一洞穴は人骨から直接年代測定を実施していませんが、白保竿根田原遺跡は人骨から直接年代測定を行っており、直接測定した人骨としては最古となります。
ただ、発見されたと報告された腓骨については、未だに記載が無く、人骨だったのか獣骨だったのかもわかりません。
なお、この山下町第一洞穴は私有地内にあり訪問する際に不便でしたが、現在、公園整備が行われており2014年度中にも完成するそうです。
*山下町第一洞穴出土人骨について、以下の文献を参考にしました。
- 高宮広衛・金武正紀・鈴木正男(1975)「那覇山下町洞穴発掘経過報告」『人類学雑誌』、第83巻第2号、pp.125-130
- 高宮広衛・玉城盛勝・金武正紀(1975)「山下町洞穴出土の人工遺物」『人類学雑誌』、第83巻第2号、pp.137-150
- 高井冬二(1975)「山下町第1洞発見の鹿化石」『人類学雑誌』、第83巻第3号、pp.280-293
- 渡辺直経(1980)「沖縄における洪積世人類遺跡」『第四紀研究』、第18巻第4号、pp.259-262
- H. SUZUKI[鈴木 尚](1983)「The Yamashita-cho Man: A late Pleistocene infantile skeleton from the Yamashita-cho Cave (Okinawa)」『Bull. et Mem. de la Soc. d'Anthrop de Paris』、t10・serieⅩⅢ、pp.81-87
- 鈴木 尚(1983)『骨から見た日本人のルーツ』、岩波書店(岩波新書)
- Erik TRINKAUS & Christopher B. RUFF(1996)「Early modern human remains from eastern Asia: the Yamashita-cho 1 immature postcrania」『Journal of Human Evolution』、30: 299-314
- 楢崎修一郎・馬場悠男・松浦秀治・近藤 恵(2000)「日本の旧石器時代人骨」『群馬県立自然史博物館研究報告』、第4号、pp.23-46
- 藤田祐樹・水嶋崇一郎・近藤修・海部陽介 (2007)「山下町第一洞穴人と縄文人の形態比較」[第61回日本人類学会大会、新潟、10月7日]
- 楢崎修一郎(2010)「日本の更新世人骨の現状と課題」『古代文化』、第62巻第3号、pp.19-38
- 諏訪 元・藤田祐樹・山崎真治・大城逸朗・馬場悠男・新里尚美・金城 達・海部陽介・松浦秀治(2011)「港川フィッシャー遺跡(沖縄県八重瀬町)の更新世人骨出土情報に関する新たな知見」『Anthropological Science (Japanese Series)』、第119巻第2号、pp.125-136
- 大山盛保生誕100年記念誌刊行会(2012)『通いつづけた日々』、大山盛保生誕100年記念誌刊行会













![日本の人類学者51.小金井良精(Ryosei KOGANEI)[1859-1944]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0a/97/46d972234646556faff44f0f58d1bae6.jpg)