対局放棄は非常に残念。
日本女子プロ将棋協会(LPSA)と日本将棋連盟と軋轢があったわけだが。対局放棄はどちらに非があるか以前の愚かな行為である。
昨日、マイナビ女子オープン戦の準決勝の2局を覗いてみようと中継サイトを開くと、なぜか甲斐智美女流四段―鈴木環那女流二段の一局だけ。
ページを見渡してみると、下の項があった。
第6期マイナビ女子オープン
準決勝 里見―石橋戦のお知らせ
里見-石橋戦は行われません
1月29日に日本女子プロ将棋協会から、現行第6期の契約解除と、代表理事である石橋女流四段棄権の発表がありました。30日に予定されていた里見香奈女流四冠-石橋幸緒女流四段の対局は行われませんので、ご了承ください。
さらに、別の項で
第6期マイナビ女子オープン
里見女流四冠不戦勝のお知らせ
1月30日に予定されていた里見香奈女流四冠-石橋幸緒女流四段戦は、里見女流四冠の不戦勝となり、挑戦者決定戦進出が決まりました。
1月29日に日本女子プロ将棋協会は、現行第6期の契約解除を発表し、代表理事である石橋女流四段は対局を棄権しました。
とある。
棋士は将棋を指すのが本分である。
将棋を生業とするのなら、将棋ファンを大切にし、スポンサーに礼を尽くさなければならない。
今回の対局放棄は、里見-石橋戦を楽しみにしていたファン、その舞台を用意したマイナビ社を蔑ろにした行為である。
LPSAは連盟に対していろいろな不満があったと思うが、その不満をファンやスポンサーにぶつけただけの対局放棄と行為に走ってしまった。その他のスポンサーや将棋ファンのLPSAへの信用を失墜させてしまった。
「LPSAへの来季の契約打ち切りが不満なら、
石橋代表よ、挑戦者になって、女王位についてしまえば良かったじゃないのか!」
そもそも、マイナビオープン戦へのLPSA所属の渡部愛ツアー棋士の参加資格問題で折り合いがつかずこじれた。マイナビ社は2団体の話し合いに任せると第3者の立場を取っていた。
参加資格問題から、時期契約問題に発展し、マイナビ社がLPSAとの次期の契約打ち切りを通知した。
それを受けたLPSAが「契約打ち切りの方針変更をしない場合は出場を取りやめる」とマイナビ社に通知した(1月25日)。
【参照】
◆LPSA
「マイナビ女子オープン準決勝対局、断念の背景と経緯説明」
「次期マイナビ女子オープンへの弊協会不出場について(ご通知)」(マイナビ社宛)
◆日本将棋連盟
「日本女子プロ将棋協会(LPSA)による マイナビ女子オープン対局放棄についての記者会見の模様」
また、詳細な経緯や分析が、日本経済新聞の「クローズアップ」の『女流将棋界で対局ボイコット騒動 プロ資格巡り対立』 でまとめられています。
渡部さんの女流棋士としての地位を確保したいという気持ちはわかるが、大人げない行為だった。
女流棋士育成という志も立派であるし、理解できるが、現在のLPSAの認定基準は甘く、その上、連盟が関与しないところで女流棋士を増産されるのは困るというのはもっともな主張である。第一、LPSA所属棋士でまともな戦績を上げているのは中井女流六段と石橋女流四段のみと言ってよい体たらくである。
そもそも、「LPSA公認プロ制度」を立ち上げる際、連盟の確認を取ったのだろうか?もし確認や了承なしで動いたとしたら、非常に無責任だ。若い女流棋士志望者の将来の一翼を担う責任があるはずだ。将棋連盟から独立当時からLPSAは見込み発進が多かったように感じる。
また、今回の経緯を見ると、LPSAは文書でのやり取りしか行っていない。私はこういう契約面での現場は知らないが、文書では綿密なやり取りはできず、誠意や熱意も伝わりにくい。LPSAは本気で交渉するつもりがあったのだろうか?
LPSAは公益社団法人認定取得を誇っているが、LPSAが公益社団法人認定取得できたのは、「将棋」の伝統と素晴らしさ、そして将棋連盟の信用があったからなのではないだろうか?今回の行為は公益社団法人認定取得の認定基準が適正なものか?という疑問さえ感じさせるものだ。
日本女子プロ将棋協会(LPSA)と日本将棋連盟と軋轢があったわけだが。対局放棄はどちらに非があるか以前の愚かな行為である。
昨日、マイナビ女子オープン戦の準決勝の2局を覗いてみようと中継サイトを開くと、なぜか甲斐智美女流四段―鈴木環那女流二段の一局だけ。
ページを見渡してみると、下の項があった。
第6期マイナビ女子オープン
準決勝 里見―石橋戦のお知らせ
里見-石橋戦は行われません
1月29日に日本女子プロ将棋協会から、現行第6期の契約解除と、代表理事である石橋女流四段棄権の発表がありました。30日に予定されていた里見香奈女流四冠-石橋幸緒女流四段の対局は行われませんので、ご了承ください。
さらに、別の項で
第6期マイナビ女子オープン
里見女流四冠不戦勝のお知らせ
1月30日に予定されていた里見香奈女流四冠-石橋幸緒女流四段戦は、里見女流四冠の不戦勝となり、挑戦者決定戦進出が決まりました。
1月29日に日本女子プロ将棋協会は、現行第6期の契約解除を発表し、代表理事である石橋女流四段は対局を棄権しました。
とある。
棋士は将棋を指すのが本分である。
将棋を生業とするのなら、将棋ファンを大切にし、スポンサーに礼を尽くさなければならない。
今回の対局放棄は、里見-石橋戦を楽しみにしていたファン、その舞台を用意したマイナビ社を蔑ろにした行為である。
LPSAは連盟に対していろいろな不満があったと思うが、その不満をファンやスポンサーにぶつけただけの対局放棄と行為に走ってしまった。その他のスポンサーや将棋ファンのLPSAへの信用を失墜させてしまった。
「LPSAへの来季の契約打ち切りが不満なら、
石橋代表よ、挑戦者になって、女王位についてしまえば良かったじゃないのか!」
そもそも、マイナビオープン戦へのLPSA所属の渡部愛ツアー棋士の参加資格問題で折り合いがつかずこじれた。マイナビ社は2団体の話し合いに任せると第3者の立場を取っていた。
参加資格問題から、時期契約問題に発展し、マイナビ社がLPSAとの次期の契約打ち切りを通知した。
それを受けたLPSAが「契約打ち切りの方針変更をしない場合は出場を取りやめる」とマイナビ社に通知した(1月25日)。
【参照】
◆LPSA
「マイナビ女子オープン準決勝対局、断念の背景と経緯説明」
「次期マイナビ女子オープンへの弊協会不出場について(ご通知)」(マイナビ社宛)
◆日本将棋連盟
「日本女子プロ将棋協会(LPSA)による マイナビ女子オープン対局放棄についての記者会見の模様」
また、詳細な経緯や分析が、日本経済新聞の「クローズアップ」の『女流将棋界で対局ボイコット騒動 プロ資格巡り対立』 でまとめられています。
渡部さんの女流棋士としての地位を確保したいという気持ちはわかるが、大人げない行為だった。
女流棋士育成という志も立派であるし、理解できるが、現在のLPSAの認定基準は甘く、その上、連盟が関与しないところで女流棋士を増産されるのは困るというのはもっともな主張である。第一、LPSA所属棋士でまともな戦績を上げているのは中井女流六段と石橋女流四段のみと言ってよい体たらくである。
そもそも、「LPSA公認プロ制度」を立ち上げる際、連盟の確認を取ったのだろうか?もし確認や了承なしで動いたとしたら、非常に無責任だ。若い女流棋士志望者の将来の一翼を担う責任があるはずだ。将棋連盟から独立当時からLPSAは見込み発進が多かったように感じる。
また、今回の経緯を見ると、LPSAは文書でのやり取りしか行っていない。私はこういう契約面での現場は知らないが、文書では綿密なやり取りはできず、誠意や熱意も伝わりにくい。LPSAは本気で交渉するつもりがあったのだろうか?
LPSAは公益社団法人認定取得を誇っているが、LPSAが公益社団法人認定取得できたのは、「将棋」の伝統と素晴らしさ、そして将棋連盟の信用があったからなのではないだろうか?今回の行為は公益社団法人認定取得の認定基準が適正なものか?という疑問さえ感じさせるものだ。











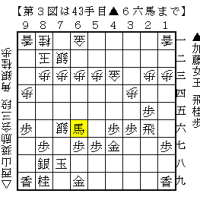

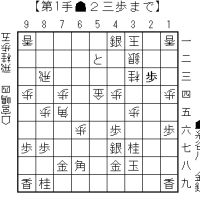




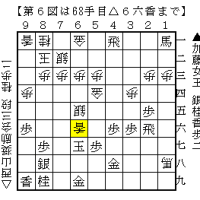






契約継続に駆け引きが必要なのもわかりますが、結局感情的と将棋ファンに受け取られては、協会のさらなる弱体化につながり不利益とは思いませんでしたか。
連盟は大きな組織なので、色々な考え方の方がいるでしょう。しかし、穿った見方をしなくとも、連盟の言い分だってわかりませんか。極端な話、例えばアマチュアが新たな団体を適当に立ち上げて、金銭等何かの手段でメジャー棋戦主催会社と契約されては、プロ棋戦の質を保てるはずはありません。質の悪い製品が売り出されても社会は困りませんが、将棋はお互い同じ場で競い合ってこそ価値が生まれるわけですから、たとえとして不適当と思います。渡辺さん一人についての棋力云々ではなく、やはり連盟としては永続的なルールとして棋力の担保として女流3級を条件としたのでしょう。
そもそも連盟からは妨害されても(良くはありませんが)、全く不思議はない団体。一般の会社であれば、利益の独占を目指すのは当然です。生き残るためにはもっとずる賢く立ち回り、連盟をうまく利用しなければならないと思いました。
筋がどうこうとか対向することより、将棋ファンの期待に応えよう。それを根本の行動指針に据えることだけが、将棋ファンの理解・共感につながり、そうすれば連盟も蔑ろにできなくなると思いますが。
同感です。でも、論調が私の記事への反論のように感じます。(私の勘違いでしたらお許しください)
私は、LPSAが新人を守ろうとする気持ちは理解できるが、今回の対局放棄は暴挙だと考えています。 新人育成もLPSAが独自でプロと認定するのは良くない。ただ、両団体が共同で行うのはありだと考えています。
今回の件でLPSAは未熟な組織だということを露呈してしまいました。
連盟側が正しいのかLPSA側が正しいのかってことの本質は見えるものではないと思います。
日本と中国の尖閣列島をめぐる争いも双方の国家の成り立ち最近の動向から判断して評価するしかありません。
尖閣の問題で言えば、中国共産党が中国本土で政権を握ってから『チベット問題』『ウイグル問題』での不法な介入から選挙し同化していっている過程、『中越戦争』での”懲らしめのため兵を起こした”って驕り高ぶった対応、『南シナ海』問題での高圧的な対応等々から私は中国の主張に無理を感じます。
連盟とLPSAの問題では、連盟側(特に米長前会長の対応)の専横的対応から今回も底には連盟側の不当な動きがあったと感じております。
連盟が将棋の質で勝負して制覇すればLPSA側も立つ瀬がないわけだし、陰湿な対応をするべきではないと感じるのは私の思い過ごしでしょうか?
谷川新体制になり思慮ある対応が望まれます。
コメント、ありがとうございます。
確かに、立ち位置によって見える景色は変わると思います。
私も、名人戦契約問題、女流棋士独立問題、その他いろいろな事柄において、連盟の歪な対応・体質を感じていました。そういった経緯を踏まえつつ、また、LPSAのこれまで活動も認識し、できるだけ客観的な視点で捉えようとしていました。(私は、思い込みが激しいので、将棋に限らず、できるだけ客観的に記事を描こうと思っています。客観的な記事になっているかは疑問ですが)
しかし、今回の対局放棄は、それらの背景と関係なく、LPSAの今までの活動、今後の活動も無にしてしまう行為だったと思います。
例えが適切ではないかもしれませんが、B氏がA氏に不快な態度や言動をとっていて、第三者の目からB氏に非があるように見えていても、A氏が我慢できずにB氏に暴力を振るったら、A氏が悪くなります。
>連盟とLPSAの問題では、連盟側(特に米長前会長の対応)の専横的対応から今回も底には連盟側の不当な動きがあったと感じております。
>連盟が将棋の質で勝負して制覇すればLPSA側も立つ瀬がないわけだし、陰湿な対応をするべきではないと感じるのは私の思い過ごしでしょうか?
岩崎さんのおっしゃるような連盟の態度は私も思い当りますが、だからと言って、今回の対局放棄という行為が認められるものではないと思います。
”併存する組織として認めるか認めないか”って問題からいえば、”貴方の組織からの新人は認めません、しかし私の組織からの新人は私の組織の規約に従って人選し参加させます。もしどうしても認めて欲しければ私の組織の養成基準に従った修行を私の組織でしてクリアーしてからでないと認めません”って対応はLPSAとしては納得できない死活問題ではないのでyそうか?
その問題を提示するためには今回のような対応が必要だったのではないでしょうか?
YouTubuでの会見の意見、LPSAの主張も私は今回の問題があり始めて気づいた部分もあるのです。
”組織として相手組織に対する最低限の礼儀”を踏みにじったのは将棋連盟ではないのでしょうか?
特に米長氏の蛮行に目をつぶり許していた将棋連盟所属棋士の猛省を促したいと思います。
この問題に関してご自分の意見を表明して頂いた英様のご努力には感謝いたします。
お陰様で私も意見表明する機会が得れて嬉しく思っております。
>対局の放棄のようなことをしないと訴えられなかったのではないかと感じたのです
LPSAのそういった心情は想像できます。これまでの連盟との軋轢と、新人育成の思い、新人の渡辺さんのプロとしての地位を確保したいという思いが、こういった行為に至ったと想像はできます。
また、LPSAの心情をくみ取った岩崎さんのお気持ちも伝わりました。
しかし、くどくなりますが、対局放棄はしてはいけないことだと思います。
その理由、それから、新人育成・認定についてや文書のみの交渉のやり方などは、記事に書いたようにLPSAに疑問を感じています。
客観性を主張するわけではありませんが、私は連盟の理事会のやり方にはかなり疑問を感じています。参考までに、『将棋界(順位戦)の歪み その1「「菅井悲劇をもたらした棋界の現状」』の前半の部分を紹介させてください。
将棋界の内部的な問題に関して鋭い視点で捉えられている英さんの力を感じました。
将棋連盟のリストラに関しては長期的な視点で、『奨励会からの四段昇段の制限』『厳しい引退制度』で本当に“身を切る改革”をされてきたと思います。
そして短期的な収益の悪化を防ぎつつ乗り切ってこられたと思います。
名人戦の共催問題では非常に危ない橋を渡りつつ将棋連盟・朝日新聞社・毎日新聞社の叡智で乗り切られたと思います。しかしここでも米長氏の強引さがより危機的状況を招くところではなかったかと私は思ってはおります。
『昇段昇級制度の悲劇』(菅井悲劇)はいわれる通りですね。くじ運だけで納得できない感じがあるのも事実です。しかしそれは公平なルール化の中で生じた歪でありリーグ戦開始時に意図性がないのであれば甘受する範囲ではないのでしょうか?
クラスによっては対局数が10局を超える場合もありますが、大所帯のC2クラスでは10局を超えるのは難しい現状があるように思います。対局をつける際に如何に公平性を期すための努力をしているかをといった記事を読んだことがありますが頭の下がる思いでした。
将棋連盟においては現役棋士160名余りそしてフリークラス30名余りの200人弱の構成に落ち着いた現在、内部的に問題を孕みつつも安定して推移していると感じます。
しかし、LPSA問題は問題の地平が違うのではないでしょうか?
女流棋士の今後の方向性を『自らの意思で選択したい』とする女流棋士側に対し、『現状の男性中心での将棋連盟側の意向に依拠した運営』から脱却することは許さないとする将棋連盟側との対立ととらえることができるのではないでしょうか?
組織の中で不当に押し込まれていた部分(少数派)が不当に支配している部分(多数派)に抗して闘っている構図ではないのでしょうか?
そして別組織になった現状でも不当な圧力( 多数派であり実力を伴った部分による全体的支配を目指した圧力 )をかけ続けている現状があるように思われます。
『女流将棋も我々が発展させてきた』との驕りの思いが将棋連盟の対応には垣間見えるのです。
将棋連盟内部の問題と同列に語れる問題ではないと思いますが如何でしょうか?
拙文を丁寧に読んで下さり、ありがとうございます。
>将棋連盟内部の問題と同列に語れる問題ではないと思いますが如何でしょうか?
あの記事をご紹介したのは、私は「連盟理事会寄り」ではなく、理事会に批判的な目を持っているということを分かっていただきたかったからです。
あの記事自体は、今回の対局放棄の件とは、論点がずれています。しかし、岩崎さんの分析・ご指摘にお答えします。
>公平なルール化の中で生じた歪でありリーグ戦開始時に意図性がないのであれば甘受する範囲ではないのでしょうか?
順位戦のシステム自体にも、46人中3人(C2組)、34人中2人(C1組)の昇級者を10局で決めるということに無理があると思っていrますが、それよりも、約160名の棋士の能力分布に偏りがあることに私は問題点を感じています。
>『奨励会からの四段昇段の制限』『厳しい引退制度』で本当に“身を切る改革”をされてきたと思います。
いえ、新四段の制限は、既得権の確保という趣のものに感じます。
フリークラス制の導入は、棋士の延命化を図ったもののように思います。
>女流棋士の今後の方向性を『自らの意思で選択したい』とする女流棋士側に対し、『現状の男性中心での将棋連盟側の意向に依拠した運営』から脱却することは許さないとする将棋連盟側との対立
女流棋士独立の際の連盟理事の対応は、腹立たしいものを感じました。
あの時の連盟側(主にあの方)の思想は、経費節減の1手段として、女流棋戦の経費節減。女流のトップはまだいいとして、下位の女流棋士に対局料や旅費を支給し、対局室や記録係も用意するのはばかばかしい。そこで、棋譜の価値を見いだせない女流棋士には普及に励んでもらおう(引退していただこう)と、女流棋士に迫ったことに端を発したと記憶しています。
しかし、それを反論しようにも、女流棋士は棋士(会員)とは認められていないから、総会等への参加もままならない。女流側にはそういった権利を認めてほしいという思いがくすぶっていたので、こじれてしまったと。
この騒動の根底には、棋力の低い女流が一人前のことを言うなという男性棋士の考えがあったと思います。(男性棋士全員ではなく、どちらかという少数)
さて、本題です。
私が、この記事を書いたのは、対局放棄が愚かな行為だと思ったからです。
もちろん、その行為に至った経緯は、もちろん考慮することだとは思いますが、たとえ、その経緯がLPSAが激怒するのが当然のものであっても、対局放棄はしてはいけない行為でした。
将棋ファンやスポンサーを蔑ろにし、対局相手、対局設営に関与した人たちの行為を無視し、将棋を冒とくした行為だと思います。
更にLPSAは今年度の契約は残っていたにもかかわらず、一方的に契約破棄をしてしまった。社会的信用は失墜しました。これは、LPSAだけでなく棋士への信用をも落とす行為であり、棋士だけでなく将棋を指す人への目も変化させる可能性さえあります。
岩崎さん、あなたは冷静な目を持ち、私の記事もしっかり読んで下さった客観的な理性を持つ方です。
なので、問います。
経緯は考えないでください。この「対局放棄」が認められる行為だと思いますか?
(私の記事は余分なことが多いので分かりにくいかもしれませんが、主旨は「対局放棄はしてはいけないこと」なのです)
英さんの記事と一連のコメントを読ませていただいて、英さんと岩崎さんはお二方共に非常に正義感が強くていらっしゃるなと思いました。私自身は英さんの結論に90%ぐらい同意ですが、ただ私の率直な感想を申し上げますと、今回の記事はいささか準備不足、あるいは結論に性急に至りすぎている、という印象を受けました。
他方、岩崎さんのコメントに関しましては、そういう立場があることは非常によく理解できますが、「立ち位置によって評価は異なる」とおっしゃる割に、英さんに対して御自身の考えを押し付けすぎているように感じられます。英さんの記事自体がいささか挑発的なトーンなので、失礼ながら英さんにも一半の責任はあると思いますが、他人のブログのコメント欄を借りて自分の意見を言うのに、回答を迫るような書き方では、自分の立ち位置を十分に相対化できているとは言えない気がいたします。
いずれにしましても、この問題については事実関係につき不明の点が多すぎますので、もう少し経緯を見守る必要があるように思います。少し冷却期間を置く意味でも、当面の議論は打ち切られるのがいいのではないか、そう思った次第です。