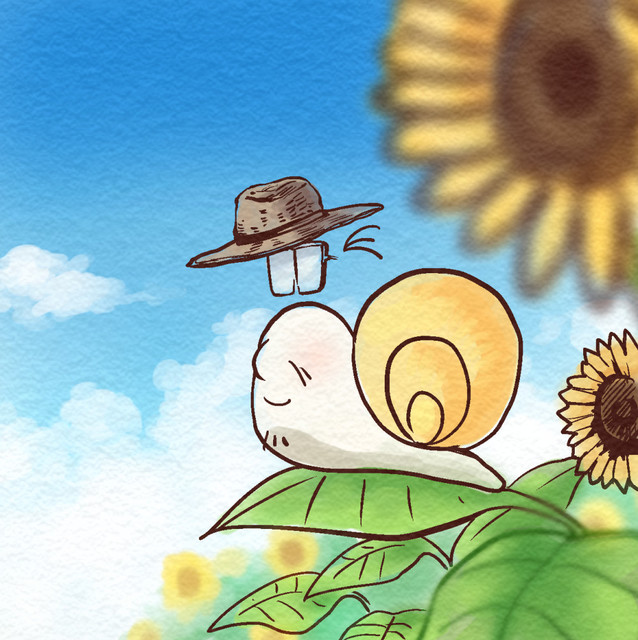2
Fair enough, you might say. However, plenty of new research suggests that forcing Internet-addicted employees to *go cold turkey may make them less productive, not more. (1) A new study, done at the University of Copenhagen, asked participants to perform a simple task – watch videos of people passing balls and count the number of passes. But first they were presented with a distraction. One group of participants had a funny video come up on their screens; the rest saw a message telling them that a funny video was available if they clicked a button, but they were told not to watch it. After ten minutes, during which people in the second group could hear those in the first laughing at the video, everyone set to the task of counting the number of passes. And the curious result was that those who hadn’t watched the comedy video made significantly more mistakes than those who had. You might have thought that those who had spent the previous ten minutes laughing would become distracted and careless. Instead, (2) it was the act of following company policy and not clicking that button that hindered people’s ability to focus and concentrate.
*go cold turkey: stop suddenly and completely
[設問]
問1. 下線部(1) A new study の実験結果を40字以内の日本語で具体的に説明しなさい。ただし、句読点も字数に含む。
問2. 下線部(2)を日本語に訳しなさい。
【解答・解説】
[番號付英文]
2.1 Fair enough, you might say.
2.2 However, plenty of new research suggests that forcing Internet-addicted employees to go cold turkey may make them less productive, not more.
2.3 A new study, done at theUniversityofCopenhagen, asked participants to perform a simple task – watch videos of people passing balls and count the number of passes.
2.4 But first they were presented with a distraction.
2.5 One group of participants had a funny video come up on their screens; the rest saw a message telling them that a funny video was available if they clicked a button, but they were told not to watch it.
2.6 After ten minutes, during which people in the second group could hear those in the first laughing at the video, everyone set to the task of counting the number of passes.
2.7 And the curious result was that those who hadn’t watched the comedy video made significantly more mistakes than those who had.
2.8 You might have thought that those who had spent the previous ten minutes laughing would become distracted and careless.
2.9 Instead, it was the act of following company policy and not clicking that button that hindered people’s ability to focus and concentrate.
[設問]
問1. 下線部(1) A new study の実験結果を40字以内の日本語で具体的に説明しなさい。ただし、句読点も字数に含む。
問2. 下線部(2)を日本語に訳しなさい。
[正答へのアプロウチ]
問1. 2.7のthat 節に結果の説明があります。字數の感覺をつかむには原稿用紙を使つて練習すると良いでせう。
問2. 強調構文です。強調する部分にふたつの -ing formが使はれ長くなつてゐるため、また that がふたつあるためにやや讀みにくくなつてゐます。
[解答]
問1. 滑稽なビデオを觀た集團より、觀てゐなかつた集團の方が明らかに多く間違へた。(37字)
問2. 集中し專念する能力を妨げたのは、會社の方針に從つてボタンをクリックしない行爲であつた。
[語句・構文等]
2.1 婉曲表現: might は假定法由來の婉曲表現で、may よりもいくぶんか弱い意味合ひになります。
2.1 Fair enough (提案に對して、しばしば肩をすくめて)結構です / まあ、いいでせう(※それも仕方ないか、といつた輕い諦めの氣持がこめられてゐるやうに感じられます)
2.2 , not more: and may not make them more productive を簡略に記したものです。
2.2 plenty of ~ 多數の~/多量の
2.2 employee アクセント注意 [implɔ̀ií:]
2.2 cold turkey もともとは「麻藥中毒患者をいきなり禁斷状態にすること(治療で)」といつた意味です
2.2 force ~ to-不定詞(…) 「強ひて~に…させる」
2.3 説明後置(ダッシュ): - の後に a simple task の内容説明を添へてゐます。
2.3 ask ~ to-不定詞(…) 「~に…するやう頼む」
2.4 be presented with ~ ~を提供される / ~を與へられる
2.5 使役: had ~ come up は使役表現で「~を映してもらつた」といふ意味になります。
2.5 準動詞の否定: 不定詞、分詞、動名詞を否定する語句は直前に置かれます。ここで not は不定詞 to watch の前に置かれてゐますから「(ビデオを)觀ないやうにと言はれた」といふ意味を傳へてゐます。
2.5 come up 畫面に映像が現はれることを指してゐます
2.5 tell ~ to-不定詞(…) 「~に…するやうにと言ふ」
2.6 the second group は2.5の the second group(ビデオ映像を觀なかつたグループを指してゐます。
2.6 set to ~ ~(仕事など)に專念する
2.7 省略: 最後の had のあとに watched the comedy video が省略されてゐます。
2.8 婉曲表現: might は假定法由來の婉曲表現で、ここでは<may have 過去分詞>よりも可能性がいささか低いことになります。
might have thought は假定法過去完了の歸結節とかたちは同じですが、ここは「過去の事實とは異なる事態を假定して、その結果を推量する(もし~してゐたなら…であつただらうに)」といふケースではありません。上述の<may have 過去分詞>の一變形でせう。(※この判斷は文脈によつて行なふもの、つまりどちらに解すると適切か、といふ判斷になります)
2.8 spend ~ 現在分詞(…) ~(時間、日など)を…して過ごす
2.9 preparatory it(強調構文): the act of following company policy and not clicking that button が強調されてゐます。
2.9 concentrate アクセント注意 [kάnsəntrèit]
[意味把握チェック]
2.1 まあ、いいでせう、とあなたは言ふかもしれない。
2.2 しかしながら、インターネットに夢中になつてゐる從業員に急に(ネット接續を)やめさせると彼らの生産性を落とす可能性があり、(彼らの生産性を)上げる可能性はない、と多くの新研究が示唆してゐる。
2.3 ある新しい研究では、(それは)コペンハーゲン大學で行なはれたものであるが、研究協力者たちに單純な仕事- 人がボールをパスするビデオ映像を觀て、パスの數を數へる - を行なふやう依頼した。
2.4 だが最初に彼らは娯樂(/氣晴し/氣をまぎらすもの)を提供された。
2.5 ひとつの協力者グループはスクリーンに滑稽なビデオ映像を映してもらつた。それ以外の協力者グループは、ボタンをクリックすれば滑稽なビデオが觀られるといふメッセーヂを見たものの、ビデオは觀ないやうにと言はれた。
2.6 10分後、それまでの間二番目のグループは第一のグループがビデオを觀て笑つてゐるのが聞こえたのであるが、皆がパスの數を數へる仕事に專念した。
2.7 そして興味深い結果は、滑稽なビデオを觀てゐなかつたグループが觀たグループよりも目立つて多くの間違ひをした、といふものであつた。
2.8 仕事の前の10分間笑つて過ごしてゐた人達は氣が散つて仕事がぞんざいになるだらうとあなたは思つたかもしれない。
2.9 ところが、集中し專念する能力を妨げたのは、會社の方針に從つてボタンをクリックしない行爲であつた。