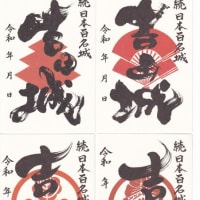お城検索は→こちら
富山城郭カードは→こちら
早月川と角川に挟まれた細長い丘陵には、升方城跡、南升方城跡、水尾城跡、など松倉城の支城である山城が配置されています。
「石の門」は南升方城跡と水尾城跡の間の丘陵鞍部に位置し、直系70~80㎝ほどの川原石を3~4mに積み上げた壮大な石組遺構の事です。周辺には曲輪や土塁場ども設けられ、「砦」の機能も備えていたので、全体を「石の門砦」と呼んでいます。
石尾門は、かつて松倉城の城下町があった鹿熊地区へ向かう西側の入り口にあたり、中世の山街道もこの場所を通っていたといわれています。
魚津市で唯一現存するこの石垣は、当時の城や町の繁栄を今に伝えるものといえます。
魚津市教育委員会、、、現地案内板より
升方城址から林道伝いに「石の門」にやって来ましたが、位置関係の整理をしてみたいと思います。
富山県の7大河川(小学校で習った記憶があります→こちら)の一つ「早月川」の右岸にあって、
西方に面したこの山には「升方城」→こちら
や「水尾城」→こちら
等松倉城支城群の防御施設が点在している。
東側には角川を挟んで本城の「松倉城」→こちら
があり、
この「石の門」はその城戸口にあたると考えられています。

遺構は林道に面して有り、案内板や標柱が整備されています。
石の門(砦)の遺構を分断して林道が建設されており、林道を挟んで反対側の削平地からは発掘調査の結果礎石が発見されたり、16世紀ころの土師器片が出土しているそうです。

林道に面した「石の門」
まさに両脇に石を積み上げた門の形をしていますが、木造建築物を載せた構造ではなかったようです。

どちらも加工されていない漬物石のような「川原石」が用いられていますが、西側の石積みの中央にはひと際大きい四角の石が配され、まるで鏡石のような存在感があります。
林道から石の門に向かって右手西側(升方城方向)の石積み

同左手東側(水尾城方向)の石積み

谷側へ降りて、反対側から見てみました。

法面にまで積み上げられた石垣の壮大さは、林道側からとは全く違う景観です。
写真は東側石垣の、角部から伸びる南法面の石積み

林道下の暗渠を抜けて反対側の削平地に行くことができます。

門の両脇は土塁で固められ、一部に切岸もみられます。

続いて「水尾城跡」へと向かいますよ〜

【石の門】

名称(別名);いしのもん
所在地;魚津市升方
城地種類;門跡
標高/比高;170m/110m
築城年代;戦国期
廃城年代;
築城者;戦国期
主な改修者;
主な城主;椎名氏・上杉氏
文化財区分;市指定文化財
主な遺構;削平地・切岸・土塁・石垣
近年の主な復元等;
※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ
地図;
富山城郭カードは→こちら
早月川と角川に挟まれた細長い丘陵には、升方城跡、南升方城跡、水尾城跡、など松倉城の支城である山城が配置されています。
「石の門」は南升方城跡と水尾城跡の間の丘陵鞍部に位置し、直系70~80㎝ほどの川原石を3~4mに積み上げた壮大な石組遺構の事です。周辺には曲輪や土塁場ども設けられ、「砦」の機能も備えていたので、全体を「石の門砦」と呼んでいます。
石尾門は、かつて松倉城の城下町があった鹿熊地区へ向かう西側の入り口にあたり、中世の山街道もこの場所を通っていたといわれています。
魚津市で唯一現存するこの石垣は、当時の城や町の繁栄を今に伝えるものといえます。
魚津市教育委員会、、、現地案内板より
升方城址から林道伝いに「石の門」にやって来ましたが、位置関係の整理をしてみたいと思います。
富山県の7大河川(小学校で習った記憶があります→こちら)の一つ「早月川」の右岸にあって、
西方に面したこの山には「升方城」→こちら
や「水尾城」→こちら
等松倉城支城群の防御施設が点在している。
東側には角川を挟んで本城の「松倉城」→こちら
があり、
この「石の門」はその城戸口にあたると考えられています。

遺構は林道に面して有り、案内板や標柱が整備されています。
石の門(砦)の遺構を分断して林道が建設されており、林道を挟んで反対側の削平地からは発掘調査の結果礎石が発見されたり、16世紀ころの土師器片が出土しているそうです。

林道に面した「石の門」
まさに両脇に石を積み上げた門の形をしていますが、木造建築物を載せた構造ではなかったようです。

どちらも加工されていない漬物石のような「川原石」が用いられていますが、西側の石積みの中央にはひと際大きい四角の石が配され、まるで鏡石のような存在感があります。
林道から石の門に向かって右手西側(升方城方向)の石積み

同左手東側(水尾城方向)の石積み

谷側へ降りて、反対側から見てみました。

法面にまで積み上げられた石垣の壮大さは、林道側からとは全く違う景観です。
写真は東側石垣の、角部から伸びる南法面の石積み

林道下の暗渠を抜けて反対側の削平地に行くことができます。

門の両脇は土塁で固められ、一部に切岸もみられます。

続いて「水尾城跡」へと向かいますよ〜

【石の門】

名称(別名);いしのもん
所在地;魚津市升方
城地種類;門跡
標高/比高;170m/110m
築城年代;戦国期
廃城年代;
築城者;戦国期
主な改修者;
主な城主;椎名氏・上杉氏
文化財区分;市指定文化財
主な遺構;削平地・切岸・土塁・石垣
近年の主な復元等;
※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ
地図;