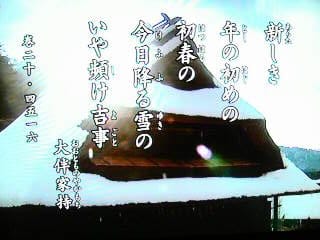日めくり万葉集(240)は最終回。この番組の語りで声の出演を続けてきた女優の壇ふみさんが選んだ、大伴旅人(おおとものたびと)の傍に仕えていた余明軍(よのみょうぐん)の歌。
【訳】
このようにはかなく亡くなられるお命(いのち)でしたのに、萩(はぎ)の花は咲いているかとお尋(たず)ねになった君は。
【選者の言葉】
色々な万葉人と知り合う感じがしたが、一番いい男だなあと思ったのは大伴旅人。萩の花が咲いているかと訊(き)いて死んだという歌があると知って、なんていい男だろうと思った。
父【作家の檀一雄さん】の残した蔵書があるので、その中から父がなくなってからはじめて、しらべものをしていたら、(万葉集の本の中に)汚い紙がいっぱい挟んであった。父の原稿用紙だった。
どういうところに(原稿用紙の切れ端の)、付箋をつけていたのかというと、大伴旅人のところだった。ずっと見ていくと、その先に旅人への挽歌のこの歌があった。そこにも(作家の太宰の名前が書いている)付箋があった。
それで思い出したことがあった。父が亡くなる前の年くらいに東京は自分の身体に合わないのでここに住むと言って九州に移り住んだ。ボロボロの家を買い、自分で手直しして家の周りに萩の花を植えた。
植えてすぐに入院してしまった。入院中の気がかりは「萩の花はもう根付いたか?」。私たちが訪ねると必ず訊いていた。旅人と父が重なるような感じがした。万葉集の番組をやらなければ、私がこの本を開かなかったろうし、父が亡くなって30数年ぶりに父と会話したような感じがした。
万葉人たちはストレートなので、声に出して読んでいくと近い感じがして、読んでいくうちにドンドンどの人の気持ちがうーん、そうだったの。見たいな気持ちになっておもしろい体験だった。
【檀さんの語り】
天平3年、大伴旅人が亡くなったときに傍について仕えていた余明軍の歌。
【感想】
ついに最終回になったかと思うと長かったような、あっという間だったような。その中で檀さんがしっかり《いい男探し》をしていたというのはさすが花の独身女性だなあと。お父様のいい思い出を大切にされていたからこそ、旅人の歌に出会われたのだろう。
父が他界してやはり長い年月が経った。以前に音楽評論家・吉田秀和さんの番組を父の姿を思い出しながら拝見した。吉田さんは父より3歳お若い年齢で、現在でも新聞記事を書いておられるほど元気な方だ。
父はクラシックが好きだったが、時代の影響を受けてマルクス主義の洗礼も受けていた。若かりし頃に父と話しているとき「資本論を読んだことがありますか?」と訊かれてドッキリしたものだ。ソ連邦が解体したときには、それをどう思うかと手紙に書いてきた。
今、格差社会に疑問を抱く若者が小林多喜二の「蟹工船」を読むようになって、再び時代は巡ってきたと、天上から地上を眺めているのかもしれない。娘に対してはいつも丁寧な言葉で話してくれた。乱暴な言葉遣いを好きになれないのは父の影響だろうと思う。
亡くなる少し前の病院のベッドで孫たちを前にして、「憲法の前文を読んでくださいね」といったことが、今でも昨日のことのように目に浮かぶ。丁度、村山内閣が誕生したとき。あれが孫たちとのお別れの挨拶、辞世の言葉でもあった。
【訳】
このようにはかなく亡くなられるお命(いのち)でしたのに、萩(はぎ)の花は咲いているかとお尋(たず)ねになった君は。
【選者の言葉】
色々な万葉人と知り合う感じがしたが、一番いい男だなあと思ったのは大伴旅人。萩の花が咲いているかと訊(き)いて死んだという歌があると知って、なんていい男だろうと思った。
父【作家の檀一雄さん】の残した蔵書があるので、その中から父がなくなってからはじめて、しらべものをしていたら、(万葉集の本の中に)汚い紙がいっぱい挟んであった。父の原稿用紙だった。
どういうところに(原稿用紙の切れ端の)、付箋をつけていたのかというと、大伴旅人のところだった。ずっと見ていくと、その先に旅人への挽歌のこの歌があった。そこにも(作家の太宰の名前が書いている)付箋があった。
それで思い出したことがあった。父が亡くなる前の年くらいに東京は自分の身体に合わないのでここに住むと言って九州に移り住んだ。ボロボロの家を買い、自分で手直しして家の周りに萩の花を植えた。
植えてすぐに入院してしまった。入院中の気がかりは「萩の花はもう根付いたか?」。私たちが訪ねると必ず訊いていた。旅人と父が重なるような感じがした。万葉集の番組をやらなければ、私がこの本を開かなかったろうし、父が亡くなって30数年ぶりに父と会話したような感じがした。
万葉人たちはストレートなので、声に出して読んでいくと近い感じがして、読んでいくうちにドンドンどの人の気持ちがうーん、そうだったの。見たいな気持ちになっておもしろい体験だった。
【檀さんの語り】
天平3年、大伴旅人が亡くなったときに傍について仕えていた余明軍の歌。
【感想】
ついに最終回になったかと思うと長かったような、あっという間だったような。その中で檀さんがしっかり《いい男探し》をしていたというのはさすが花の独身女性だなあと。お父様のいい思い出を大切にされていたからこそ、旅人の歌に出会われたのだろう。
父が他界してやはり長い年月が経った。以前に音楽評論家・吉田秀和さんの番組を父の姿を思い出しながら拝見した。吉田さんは父より3歳お若い年齢で、現在でも新聞記事を書いておられるほど元気な方だ。
父はクラシックが好きだったが、時代の影響を受けてマルクス主義の洗礼も受けていた。若かりし頃に父と話しているとき「資本論を読んだことがありますか?」と訊かれてドッキリしたものだ。ソ連邦が解体したときには、それをどう思うかと手紙に書いてきた。
今、格差社会に疑問を抱く若者が小林多喜二の「蟹工船」を読むようになって、再び時代は巡ってきたと、天上から地上を眺めているのかもしれない。娘に対してはいつも丁寧な言葉で話してくれた。乱暴な言葉遣いを好きになれないのは父の影響だろうと思う。
亡くなる少し前の病院のベッドで孫たちを前にして、「憲法の前文を読んでくださいね」といったことが、今でも昨日のことのように目に浮かぶ。丁度、村山内閣が誕生したとき。あれが孫たちとのお別れの挨拶、辞世の言葉でもあった。