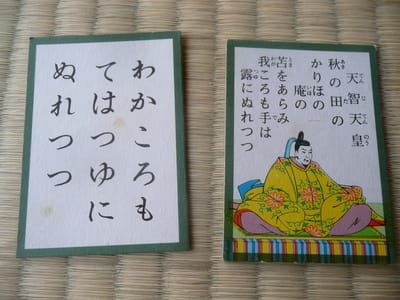朝一番の6時半に朝食を摂って、奥入瀬の道がまだ混まないうちにと、朝霧がまだ残る十和田湖畔を出発しました。

奥入瀬渓流の流れは十和田湖の水で、この水門によって十和田湖からの流出量が調節されているのを、最近ブラタモリで知ったところです。

奥入瀬の流れで一番大きい銚子大滝。
すぐ近くの道に車を停めて、ゆっくり眺めることが出来ました。
まだ8時頃で、人も少なめです。

支流から流れ込んでいる雲井大滝。
奥入瀬渓流っていつからこんなに有名になったのですかね?、カレンダーの写真でよく見るようになったのはいつ頃でしたかね?
オイラセはこんな字を書くのかと、私が知ったのはつい最近の気がしています。
山奥から始まった谷川の水ではなく、大きな十和田湖から流れ出た水なら、琵琶湖から流れ出た水の瀬田川も奥入瀬も、変わらないのかなあと思ってしまいました。


ところどころの道端に車を停める余裕はまだあるので、途中の大きな石ヶ戸(イシケド)休憩所に車を停めて、歩いたりバスに乗って帰ったりする予定をやめて、ちょこちょこ車を道端に停めて、ほんのちょっと歩いて見学する方法に変えました。

シャッタースピードを変えたりして撮ろうと試みるも、やり方解からなくなり、雪でもない紅葉でもない、普通の奥入瀬渓流の風景写真です。

阿修羅の流れと言う名の奥入瀬名物の流れは、極彩色モードで撮ってみました。

そろそろ車の流れも増えてきて、連休の奥入瀬渓流になってきたようですが、まだまだ渋滞したり、停める場所がないほどでもなく、予定より早く奥入瀬渓流は終了。
返事
花水木さん1:やっぱり和井内貞行の記憶は教科書なんですね。
花水木さん2:今の日本人バックダンサーは、
前で歌う歌手より綺麗で脚長いですね。
スクールメッツ時代と大違いです。