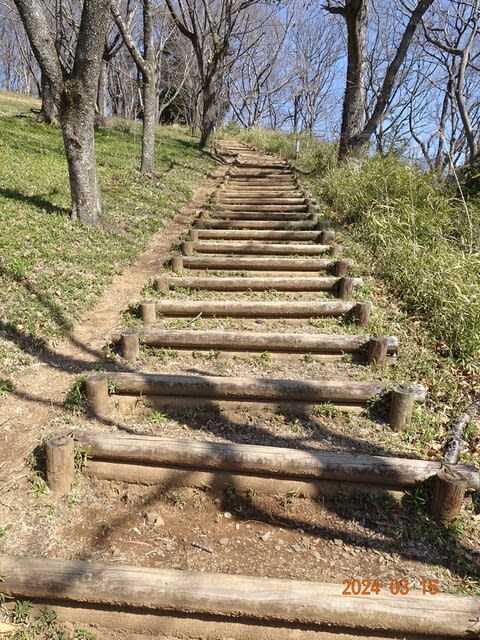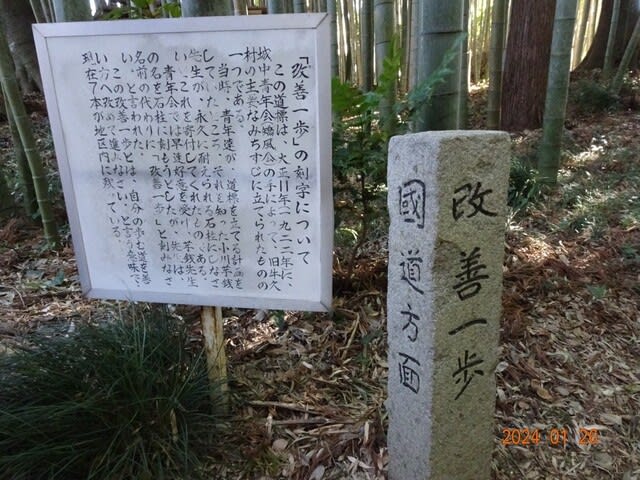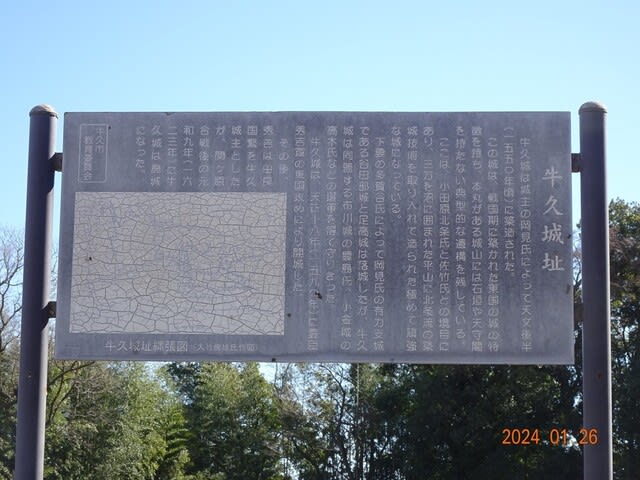令和6年(2024年)4月5日(金)
原則隔週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、
令和6年度(2024年度)第1回、令和6年(2024年)第6回「常福寺~桜川遊歩道コース(土浦市)」
ウォーキングに参加した。
今回は、令和6年度(2024年度)最初の例会となる。
東京都の桜は昨年より約2週間ほど遅れて3月29日にようやく開花、昨日4日に満開になった
と発表されたばかり。
この日は土浦市内の桜川遊歩道を歩くことになっているので、桜の開花状況が気になる。
第一集合場所の乙戸沼公園の桜(ソメイヨシノ)は2-3分咲きほどではないかと思われる。

乙戸沼公園の桜の状況
数年前からの開花状況を参考にしながら、約半年前には次年度の予定を決めていることから、
桜川遊歩道の桜もこのくらいであれば”まあ良し”とするしかないかな・・・

乙戸沼公園の露店の開店時間にはまだ少し早いが、準備万端のようだ。

この日乙戸沼公園には計4名が集まった。
この日の天気は、朝方小雨で後曇り、最高気温11℃という予報だったため、少ないのかも・・・

出発地のイオンモール土浦駐車場へ行ってみると、既にかなりの人数が集まっていた。
中には傘を差している人の姿も見える。

この日は”ミニ総会”を予定しているので、参加者は27名といつもよりはやや多かったものの、
”晴れ”であれば30名以上は集まっていたと思われるが・・・

駐車場周辺に植えられた桜は満開に近い状況。
しかし、これはソメイヨシノではなさそう。
葉っぱが見えることから山桜の一種ではないだろうか?

予定の時刻となったので、駐車場の端っこに移動して”ミニ総会”を開始した。
前年度の決算報告及び会計監査報告、新年度の予算案などの報告・説明などを行い・・・

前年度の各人の参加結果を配布し、注目の皆勤賞等の表彰式を始めた。
年度で22回予定のところ、2回が雨で中止となったので、全20回参加が皆勤賞となる。
先ずは皆勤賞のST子さん。

続いて皆勤賞のSTさん。
STさん夫妻は3年連続で皆勤賞受賞という快挙である。

皆勤賞受賞のHSさん(84)は2年連続だ。
なお今回は、1回だけ不参加OKの精勤賞授与の該当者は残念ながらいなかった。
精勤賞の対象者がいなかったというのは、当会初めてのことである。

3年以上在籍し、傘寿(80歳)を迎えた方への功労賞授与の3名は、いずれも女性である。
先ずはKM子さん

続いてKD子さん

3人目はNK子さん

会則には特に定めていないが、1ヶ月前に卒寿(90歳)を迎えられたKKさんには今回特別に
記念品を贈呈することを役員会で決めた次第である。
TK会長(84)からは、KKさんへの労いの言葉とともに賛辞が表明され、記念品のキャップが
贈呈された。
『当会の誇りとしてこれからも元気で頑張って下さい』
周りからは『とても90歳とは思えないよねっ』 『見習わなくっちゃっ』 の声とともに
大きな拍手が。

真新しいキャップ姿で満面の笑みを浮かべるKKさん。
この先まだまだ元気に歩き続けて欲しいものである。

無事”ミニ総会”が終わり、10時14分、イオンモール土浦駐車場を出発した。
先ず最初に目指すのは、常福寺である。

イオンモール土浦駐車場に沿って土浦市街地方面へ。

左手にイオンモール土浦を見ながら進み、

イオンモール土浦の正面出入口を右に折れて県道123号方面へ。

県道123号を左に曲がって50mほど先の坂道を下高津小学校方面へ。

下高津小学校方面への坂道はかなりきつかった。
『やっぱり坂道はきついわよねっ』

10時28分、下高津小学校前を通過。

かなりきつい坂道もなんのその、皆さんと変わらぬペースで進むKKさん。
新しいキャップが気に入ってくれているようだ。

10時37分、旧国道6号との交差点に到着した。

旧国道6号との交差点を横断し、最初の目的地である常福寺方面へ。

常福寺方面へ進むと、10時42分、常福寺に到着した。
常福寺は、平安時代初期に最澄の弟子の天台僧最仙の開基と伝えられる。
後に真言宗に改宗されて、現在に続く。
常福寺の御本尊である木造薬師如来像は国の重要文化財に指定されている。
平成19年(2007年)1月 土浦市教育委員会

常福寺の境内にある市指定文化財、天然記念物の常福寺の大銀杏
樹勢も旺盛で、春の芽吹き・秋の黄葉ともに見事である。
樹高もあるので、遠く市街地からも遠望できる。
秋には多くのギンナンを落とす。
この木は雌株で、樹齢はおよそ400年前後と推定される。
平成19年(2007年)1月 土浦市教育委員会

土浦市内を一望できる紅葉ヶ丘霊園へ向かうと・・・
子育地蔵像が迎えてくれる。

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(1)
この日は紅葉ヶ丘からの眺望は、樹木が茂っていて土浦市内の一望は望めなかったため、
このパノラマ写真1枚を撮っただけに終わった。

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(2)(1月に下見をした時に撮ったもの)
筑波山方面

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(3)(1月に下見をした時に撮ったもの)
筑波山

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(4)(1月に下見をした時に撮ったもの)
土浦駅前の市役所などが入るウララビル

この日は紅葉ヶ丘の1本の桜が満開だった。
桜の名称は不明だが、見ごたえがあった。

常福寺境内の片隅に愛宕神社がある。
見事な茅葺屋根の本殿を裏から見たところだが、このような重厚な造りの神社は見たことがない。
印象に残る建物である。

愛宕神社の拝殿を正面から見たところ。
愛宕神社に参拝し、

拝殿前の急な石段を下る。
『この階段は怖いよね~っ』

旧水戸街道を銭亀橋方面へ。

桜川に架かる銭亀橋を渡る。

銭亀橋を渡る。

桜川上流の土浦橋方面の眺め

桜川下流の土浦市街地方面の眺め

銭亀橋を渡って左に曲がり、桜川の堤防へ。
堤防に咲いていたボケの花。
『いやぁ 綺麗で見事だよねぇ』 『今がちょうど満開じゃないっ?』

桜川の堤防には菜の花も咲いていた。

11時4分、国道125号の土浦橋に到着した。

国道125号は車の通行量が多く、横断するのに苦労するので、橋の下を通ることにし、
備え付けの石段を下る。

国道125号の下を潜って・・・

道路反対側の桜川の土手へ。

桜川の土手を進むと、額束に道祖神と書かれた鳥居があった。

境内を進むと奥に小さな祠があった。
銭亀道祖神神社である。

例大祭のお知らせが貼ってあった。
4月16日(火)午前10時~午後1時に年に一度の「例大祭」を開催します。
ご参拝のお礼に季節の団子をご用意します、とある。
どんな団子なのだろう、気になる。

桜川の堤防に戻って少し進んだ所の桜の木の下にはいくつかのベンチが設置されていた。
11時10分、ここで一休みすることに。

土手の上で休憩しているが、時々車が通るので注意が必要だ。
『ここは車の通行禁止区間じゃないんだ~』

当会恒例のお茶タイムである。
めいめいが持ち寄った飴やお菓子が配られる。
楽しみのひと時である。

『ちょっとだけお腹が空いて来た頃だから美味しいのよねっ』

お茶タイムも終わり、学園大橋方面を目指す。

土浦港まで4600m、学園大橋まで900mの地点を通過。
この案内表示は100m間隔で描かれているので何かと便利で助かる。

土手の両側が桜並木という状態が始まった。
桜川の桜が一番の見所と言われるポイントだそうだ。
桜は2-3分咲きと言った状態なので、この分だと満開の見頃は4-5日先になると思われる。

木の根元には夜間の桜をライトアップするための準備が既に済んでいた。

両側の桜並木が続く。

『桜はまあまあの状態だよねっ』

桜川の対岸にゴールとなるイオンモール土浦が見える。

桜川側の並木が終わり、前方に学園大橋がはっきりと見えて来た。

学園大橋まで100mの地点を通過

11時34分、学園大橋に到着

学園大橋を渡って桜川の対岸へ。

学園大橋から桜川(下流)を望む。

学園大橋を渡り、

渡り切った所を左方面へ。

右手は市民運動広場になっている。
ゴールはもう直ぐだ。

桜川堤防に沿った道路を進む。

しばらく進むと・・・

桜川と備前川の間に設けられた水門が現れた。

水門を通過してそのまま進むと、前方がイオンモール土浦である。

11時49分、ゴールのイオンモール土浦に到着した。

全員無事イオンモール土浦にゴール出来て一安堵。
最後にTK会長から労いの挨拶があり、

11時52分、次回のコースと集合場所などの説明を行った後、
この日は、ここで解散することにした。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

時刻はちょうどお昼時、イオンモール土浦でご飯でも食べて帰ることにしよう、
ということで、4名でイオンモール土浦のレストラン街へ。
「五穀」という和食の店があった。
『値段も手頃なようだし、ここにしましょうかっ』

全員が海老天付きざる蕎麦(税込1,408円)を注文した。
この後運転があるので、生は注文しなかった。残念!!

食事風景(1)

食事風景(2)

この日は、新年度第1回目として土浦市内の桜の名所でもある”常福寺~桜川遊歩道コース”
を歩いた。
このコースは当会としては初めてである。
茨城県の直近の桜開花予想は3月31日、満開は4月5日の予報となっていたが、桜川堤防を
歩いてみて実際には2-3分咲きだったのではないかと感じた。
満開には未だ少し早いが好天が続けばあと一息と思われた。(あくまでも個人的感想)
”ミニ総会”でも触れたが、当会に卒寿(90歳)を迎えた会員がいることを誇りに思っている。
会員の皆さんも卒寿を迎えられたKKさんを目標にして、出来れば卒寿を迎えるまでは
自分の脚で元気に歩きたいと願っていることだろう。
卒寿が無理ならせめて米寿(88歳)、あるいは傘寿(80歳)まででもと思っているのでは
ないだろうか・・・
この日の万歩計は、11,000歩を計測していた。
”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。
原則隔週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、
令和6年度(2024年度)第1回、令和6年(2024年)第6回「常福寺~桜川遊歩道コース(土浦市)」
ウォーキングに参加した。
今回は、令和6年度(2024年度)最初の例会となる。
東京都の桜は昨年より約2週間ほど遅れて3月29日にようやく開花、昨日4日に満開になった
と発表されたばかり。
この日は土浦市内の桜川遊歩道を歩くことになっているので、桜の開花状況が気になる。
第一集合場所の乙戸沼公園の桜(ソメイヨシノ)は2-3分咲きほどではないかと思われる。

乙戸沼公園の桜の状況
数年前からの開花状況を参考にしながら、約半年前には次年度の予定を決めていることから、
桜川遊歩道の桜もこのくらいであれば”まあ良し”とするしかないかな・・・

乙戸沼公園の露店の開店時間にはまだ少し早いが、準備万端のようだ。

この日乙戸沼公園には計4名が集まった。
この日の天気は、朝方小雨で後曇り、最高気温11℃という予報だったため、少ないのかも・・・

出発地のイオンモール土浦駐車場へ行ってみると、既にかなりの人数が集まっていた。
中には傘を差している人の姿も見える。

この日は”ミニ総会”を予定しているので、参加者は27名といつもよりはやや多かったものの、
”晴れ”であれば30名以上は集まっていたと思われるが・・・

駐車場周辺に植えられた桜は満開に近い状況。
しかし、これはソメイヨシノではなさそう。
葉っぱが見えることから山桜の一種ではないだろうか?

予定の時刻となったので、駐車場の端っこに移動して”ミニ総会”を開始した。
前年度の決算報告及び会計監査報告、新年度の予算案などの報告・説明などを行い・・・

前年度の各人の参加結果を配布し、注目の皆勤賞等の表彰式を始めた。
年度で22回予定のところ、2回が雨で中止となったので、全20回参加が皆勤賞となる。
先ずは皆勤賞のST子さん。

続いて皆勤賞のSTさん。
STさん夫妻は3年連続で皆勤賞受賞という快挙である。

皆勤賞受賞のHSさん(84)は2年連続だ。
なお今回は、1回だけ不参加OKの精勤賞授与の該当者は残念ながらいなかった。
精勤賞の対象者がいなかったというのは、当会初めてのことである。

3年以上在籍し、傘寿(80歳)を迎えた方への功労賞授与の3名は、いずれも女性である。
先ずはKM子さん

続いてKD子さん

3人目はNK子さん

会則には特に定めていないが、1ヶ月前に卒寿(90歳)を迎えられたKKさんには今回特別に
記念品を贈呈することを役員会で決めた次第である。
TK会長(84)からは、KKさんへの労いの言葉とともに賛辞が表明され、記念品のキャップが
贈呈された。
『当会の誇りとしてこれからも元気で頑張って下さい』
周りからは『とても90歳とは思えないよねっ』 『見習わなくっちゃっ』 の声とともに
大きな拍手が。

真新しいキャップ姿で満面の笑みを浮かべるKKさん。
この先まだまだ元気に歩き続けて欲しいものである。

無事”ミニ総会”が終わり、10時14分、イオンモール土浦駐車場を出発した。
先ず最初に目指すのは、常福寺である。

イオンモール土浦駐車場に沿って土浦市街地方面へ。

左手にイオンモール土浦を見ながら進み、

イオンモール土浦の正面出入口を右に折れて県道123号方面へ。

県道123号を左に曲がって50mほど先の坂道を下高津小学校方面へ。

下高津小学校方面への坂道はかなりきつかった。
『やっぱり坂道はきついわよねっ』

10時28分、下高津小学校前を通過。

かなりきつい坂道もなんのその、皆さんと変わらぬペースで進むKKさん。
新しいキャップが気に入ってくれているようだ。

10時37分、旧国道6号との交差点に到着した。

旧国道6号との交差点を横断し、最初の目的地である常福寺方面へ。

常福寺方面へ進むと、10時42分、常福寺に到着した。
常福寺は、平安時代初期に最澄の弟子の天台僧最仙の開基と伝えられる。
後に真言宗に改宗されて、現在に続く。
常福寺の御本尊である木造薬師如来像は国の重要文化財に指定されている。
平成19年(2007年)1月 土浦市教育委員会

常福寺の境内にある市指定文化財、天然記念物の常福寺の大銀杏
樹勢も旺盛で、春の芽吹き・秋の黄葉ともに見事である。
樹高もあるので、遠く市街地からも遠望できる。
秋には多くのギンナンを落とす。
この木は雌株で、樹齢はおよそ400年前後と推定される。
平成19年(2007年)1月 土浦市教育委員会

土浦市内を一望できる紅葉ヶ丘霊園へ向かうと・・・
子育地蔵像が迎えてくれる。

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(1)
この日は紅葉ヶ丘からの眺望は、樹木が茂っていて土浦市内の一望は望めなかったため、
このパノラマ写真1枚を撮っただけに終わった。

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(2)(1月に下見をした時に撮ったもの)
筑波山方面

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(3)(1月に下見をした時に撮ったもの)
筑波山

常福寺紅葉ヶ丘からの展望(4)(1月に下見をした時に撮ったもの)
土浦駅前の市役所などが入るウララビル

この日は紅葉ヶ丘の1本の桜が満開だった。
桜の名称は不明だが、見ごたえがあった。

常福寺境内の片隅に愛宕神社がある。
見事な茅葺屋根の本殿を裏から見たところだが、このような重厚な造りの神社は見たことがない。
印象に残る建物である。

愛宕神社の拝殿を正面から見たところ。
愛宕神社に参拝し、

拝殿前の急な石段を下る。
『この階段は怖いよね~っ』

旧水戸街道を銭亀橋方面へ。

桜川に架かる銭亀橋を渡る。

銭亀橋を渡る。

桜川上流の土浦橋方面の眺め

桜川下流の土浦市街地方面の眺め

銭亀橋を渡って左に曲がり、桜川の堤防へ。
堤防に咲いていたボケの花。
『いやぁ 綺麗で見事だよねぇ』 『今がちょうど満開じゃないっ?』

桜川の堤防には菜の花も咲いていた。

11時4分、国道125号の土浦橋に到着した。

国道125号は車の通行量が多く、横断するのに苦労するので、橋の下を通ることにし、
備え付けの石段を下る。

国道125号の下を潜って・・・

道路反対側の桜川の土手へ。

桜川の土手を進むと、額束に道祖神と書かれた鳥居があった。

境内を進むと奥に小さな祠があった。
銭亀道祖神神社である。

例大祭のお知らせが貼ってあった。
4月16日(火)午前10時~午後1時に年に一度の「例大祭」を開催します。
ご参拝のお礼に季節の団子をご用意します、とある。
どんな団子なのだろう、気になる。

桜川の堤防に戻って少し進んだ所の桜の木の下にはいくつかのベンチが設置されていた。
11時10分、ここで一休みすることに。

土手の上で休憩しているが、時々車が通るので注意が必要だ。
『ここは車の通行禁止区間じゃないんだ~』

当会恒例のお茶タイムである。
めいめいが持ち寄った飴やお菓子が配られる。
楽しみのひと時である。

『ちょっとだけお腹が空いて来た頃だから美味しいのよねっ』

お茶タイムも終わり、学園大橋方面を目指す。

土浦港まで4600m、学園大橋まで900mの地点を通過。
この案内表示は100m間隔で描かれているので何かと便利で助かる。

土手の両側が桜並木という状態が始まった。
桜川の桜が一番の見所と言われるポイントだそうだ。
桜は2-3分咲きと言った状態なので、この分だと満開の見頃は4-5日先になると思われる。

木の根元には夜間の桜をライトアップするための準備が既に済んでいた。

両側の桜並木が続く。

『桜はまあまあの状態だよねっ』

桜川の対岸にゴールとなるイオンモール土浦が見える。

桜川側の並木が終わり、前方に学園大橋がはっきりと見えて来た。

学園大橋まで100mの地点を通過

11時34分、学園大橋に到着

学園大橋を渡って桜川の対岸へ。

学園大橋から桜川(下流)を望む。

学園大橋を渡り、

渡り切った所を左方面へ。

右手は市民運動広場になっている。
ゴールはもう直ぐだ。

桜川堤防に沿った道路を進む。

しばらく進むと・・・

桜川と備前川の間に設けられた水門が現れた。

水門を通過してそのまま進むと、前方がイオンモール土浦である。

11時49分、ゴールのイオンモール土浦に到着した。

全員無事イオンモール土浦にゴール出来て一安堵。
最後にTK会長から労いの挨拶があり、

11時52分、次回のコースと集合場所などの説明を行った後、
この日は、ここで解散することにした。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

時刻はちょうどお昼時、イオンモール土浦でご飯でも食べて帰ることにしよう、
ということで、4名でイオンモール土浦のレストラン街へ。
「五穀」という和食の店があった。
『値段も手頃なようだし、ここにしましょうかっ』

全員が海老天付きざる蕎麦(税込1,408円)を注文した。
この後運転があるので、生は注文しなかった。残念!!

食事風景(1)

食事風景(2)

この日は、新年度第1回目として土浦市内の桜の名所でもある”常福寺~桜川遊歩道コース”
を歩いた。
このコースは当会としては初めてである。
茨城県の直近の桜開花予想は3月31日、満開は4月5日の予報となっていたが、桜川堤防を
歩いてみて実際には2-3分咲きだったのではないかと感じた。
満開には未だ少し早いが好天が続けばあと一息と思われた。(あくまでも個人的感想)
”ミニ総会”でも触れたが、当会に卒寿(90歳)を迎えた会員がいることを誇りに思っている。
会員の皆さんも卒寿を迎えられたKKさんを目標にして、出来れば卒寿を迎えるまでは
自分の脚で元気に歩きたいと願っていることだろう。
卒寿が無理ならせめて米寿(88歳)、あるいは傘寿(80歳)まででもと思っているのでは
ないだろうか・・・
この日の万歩計は、11,000歩を計測していた。
”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。