久しぶりの故郷の家への帰省だった。コロナ禍下のこの2年間、毎月、一人暮らしの母のことが気にかかり福井県南越前町の実家に帰省していたが、この12月や正月には積雪のためになかなか帰省ができなかった。12月中旬頃から、北陸地方や滋賀県北部は断続的に雪が降り続き、ノーマルタイヤでは滋賀県・福井県の県境峠の豪雪地帯を越えることが難しかったからだ。
1月15日(土)・16日(日)・17日(月)の3日間は、この県境あたりは雪が降らないという天気予報だったので、不安をかかえながらも、16日(日)に帰省することにした。京都市から滋賀県の湖西道路を車で走り、琵琶湖大橋近くの道の駅で休憩、比良山系は真っ白な雪に覆われているが、平地は雪がなかった。さらに湖北地方の高島市に入ると、平地にも雪が積もっていて真っ白な雪景色の光景が広がっていた。
滋賀・福井の県境にある高島市マキノ町に入ると積雪はさらに深くなっていたが、幹線道路は除雪がされているのでノーマルタイヤでの車の通行に支障はなかった。メタセコイヤ並木周辺の雪景色が美しい。
メタセコイヤ並木のあるマキノピックランドの広い駐車場は、満杯となっていて駐車がなかなか難しいほど、たくさんの人が来ていた。子供連れの家族も多く、傾斜のある広場が即席ゲレンデとなって、ソリ遊びをしている家族連れの姿が多くみられた。
このメタセコイヤ並木から車で20分ほどのところの県境境(けんきょうさかい)の山間地にある在原(ありはら)集落では、1mほどの積雪となっているようだった。この在原集落経由ではなく、幹線道路の山中峠越え(国道161号線)で福井県敦賀市に向かった。峠付近は積雪がかなりのものだが、道路は完全除雪がされていて、ノーマルタイヤでも不安はなかった。心配は杞憂(きゆう)に終わった。
午後4時頃に故郷の南越前町河野地区に到着した。冬の曇天、若狭湾に分厚い雲間から夕日が放射していた。向こうに京都府の丹後半島が浮かんでいた。
だんだんと日が暮れ行く。北の方角はロシア極東のウラジオストク方面。最近読み返している『アムールヒョウが絶滅する日』や『虎山へ』。アムールトラやヒョウが生息している山脈があるんだなあと思いながら北方の地平線を眺めた。
翌日17日(月)、朝食後に越前岬近くの集落に水仙を買いに行ってみた。越前岬の呼鳥門(こちょうもん)は、かっては海岸道路が門の中を走っていた。この呼鳥門の近くに、「水仙廼社(すいせんだいしゃ)/すいせんのやしろ」という社(やしろ)がある。
ここ越前海岸は日本で最も広い水仙の群生地。越前海岸の断崖のわずかな傾斜地に、雪の降る12月から2月にかけて群生し、水仙の高貴な香りを放つ。この社の祠(ほこら)のそばには、「越前水仙を語る伝説―美しい娘の化身」の伝説について説明している看板が置かれている。平安末期、源平の合戦時代、木曽義仲軍に合流した二人の兄弟たちと村の娘の悲恋の物語だ。また、この祠の背後の洞窟に祀(まつ)られている愛染明王(あいぜんみょうおう)についての説明看板も置かれている。昔からこの越前岬周辺では「愛染さま」と呼ばれ、愛染明王信仰が深かったのだという。
愛染明王とは、どんな仏(ほとけ)なのか?よく山間地の水辺でみられる不動明王とともに、真言密教の明王仏とされている。この愛染明王は、「愛欲の仏」とも言われる。その仏像の特徴は、「①忿怒(ふんぬ)の形相、②赤い体、③逆立つ髪の毛に獅子冠、④3つの目、⑤6本の腕、⑥弓矢を持つ、⑦蓮華座に座る」。かって、上杉景勝の右腕として、徳川家康と対抗し石田三成とともに関ヶ原の戦に至った戦国武将「直江兼続」の兜の上には、大きな「愛」の文字があった。兼続はこの愛染明王を信仰していたことによるとも伝わる。ちなみに上杉謙信は「毘沙門天」への信仰が篤かった。
「愛染」という言葉を聞くと、昭和世代の私などは映画やドラマの「愛染かつら」をすぐに思い出す。この「愛染かつら」という映画は、第一作目が1938年に公開された映画だ。日中戦争さなかの暗い世相を吹きとばした映画とも云われている。主演は田中絹代と上原謙。物語は、「夫に死に別れ、幼子を抱えて懸命に生きる看護婦と病院長の息子である医師との、身分違いの恋愛劇。二人の間に立ちはだかる、いくつもの恋の行く手を阻むことが起きる。花も嵐も踏み越えて……、と二人の愛の行方にハラハラドキドキの映画。
この映画は、1950年代、60年代にも当時の有名男優・女優によって何度も映画化された。また、何度もテレビドラマ化もされた。最後にドラマ化されたのは1976年、主演は片岡孝夫・島田陽子だった。「愛染かつら」の主題歌「旅の夜風」が昭和の名曲の一つとして大ヒットした。歌詞は「花も嵐も 踏み越えて 行くが 男の 生きる道…」。歌手は霧島昇だった。映画やドラマは見ていなくても、この歌は知っているという昭和世代は多いかと思う。
ちなみにこの映画・ドラマの題名「愛染かつら」とは、二人の男女が、愛染明王の祠の横に大きな桂(かつら)の木があり、ここで愛の成就を誓い合う場面に由来する。(原作は川口松太郎の小説。長野県別所温泉に行った際、この愛染明王の祠のそばに立つ樹齢300年~600年以上の桂の木を見て、この物語ができたと云われている。)
越前岬灯台は、丹後半島の経ヶ岬灯台、敦賀半島の立石岬灯台とともにこの若狭湾の船の航行を支え続けた。岬周辺の断崖や越前海岸一帯の切り立った断崖に沿って水仙の花が一面に咲く。そこへ、冬の北陸特有のシベリアからの強い海風が吹く。その風は、霙(みぞれ)や雪をともなって容赦なく水仙に吹き付ける。大きく揺れながらも、風をものともせず凛(りん)と咲く可憐で高貴な香りの花に、人々は時に心を揺さぶられ、自身の心情を重ね合わせる人も少なくないはずだ。これまで幾多の文学者がその心情を作品の中に書きとめている。
作家・水上勉の文学碑が越前岬灯台の近くにある。文学碑には、「旅は 孤独を味わわせる と同時に、かみしめる孤独から勇気を培うものだと 私はかねがね思っているが、越前岬ほど私に人生を考えさせた場所はないようである。黒い断崖に風が吹きすさび、その丘に、なぜ、あのような花が咲くのだろう。黄色い水仙であった。冬の凍てつく土に花が咲くのだ。」と、一文が刻まれている。この一文は、水上勉の「日本の風景を歩く」シリーズの中の一冊『越の道―越前・越中・越後』に書かれている。十数年前に図書館でこの本を借りて読んだことがあった。水上勉の紀行文は、司馬遼太郎の紀行文と双璧をなす。司馬の紀行文は歴史的文学性に優れ、水上の紀行文は叙情的文学性に優れていて、それぞれにとても優れた紀行文学だ。
この日、私は越前水仙売りのおばさんたちから、水仙を4束買った。一束が200円だったが、サービスにあと2束つけてくれた。(※日本三大水仙郷とは、他に「淡路島の黒岩水仙郷・静岡県の伊豆半島水仙郷」がある。どちらも暖かい気候の地域。)
冬の越前海岸と言えば、「水仙とカニ」。私が子どもの頃は、「ばあちゃん、また、今日もカニか…」と冬は毎日のように食べていた。主に、メスガニの「こっぺ」と呼ばれた小さいカニを食べていた。11月6日からカニ漁が解禁となり、3月20日頃までカニ漁が続く。(メスは12月31日まで。資源保護のため。)
福井県越前町の港にはたくさんのカニ漁船が停泊していた。日本海の若狭湾沖にあるカニ漁場には、ここ越前町や京都府丹後半島の漁港、鳥取県香住漁港などから出漁している。漁場に最も近い港がここ越前町の港。
南越前町の道の駅やコンビニに「冬のこどもたち—岩崎ちひろ展」(12/3~3/7)のポスターが置かれていた。岩崎ちひろ(絵本作家)は、越前市(武生市)に生まれ育った。その生家は今も残り、「ちひろの生まれた家記念館」となっている。この越前市(武生)で育った絵本作家として、かこさとしがいる。『からすのパンやさん』『だるまちゃん』シリーズなどの絵本作家だ。短歌歌人で『サラダ記念日』を出版した俵万智も武生育ち。『源氏物語』の作者・紫式部は、父の赴任にともない、越前国府のあったここ武生(府中)で乙女時代を過ごしている。
1月19日付の京都新聞に「雪中四友 冬空に映え—ウメ・ロウバイ・スイセン・サザンカ」の見出し記事が掲載されていた。「雪中四友(せきちゅうしゆう)」とは、中国でうまれた言葉で、中国の文人画などで好まれてきた画題。
冬の四つの花(雪中四友)水仙・蠟梅・梅・山茶花(さざんか)は、中でも、越前海岸の越前水仙は特に「雪中花」としての印象は強い。小林幸子の歌に「雪椿」がある。北陸各地にも咲く赤い藪椿(やぶつばき)に白い雪が積もるさまも、「凛(りん)」とした女性を感じる。












































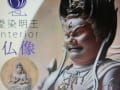




















北陸の「越前・越後」といった表現が好きで、水上勉の作品は少し読んでいました。文章表現に優れ、読んでいると情景が目の前に浮かぶようで、自然に引き込まれてしまいます。多くの文人が北陸出身というのも、その地形気候風土から分かるような気がします。