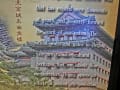「北楼」で最も標高の高い(※880mほど)北八楼から北七楼……北一楼と、長城の各楼を下ってきて、「八達嶺長城」で最も防衛的に重要な「城門」の上に着いた。砲が置かれていた。説明版を見ると、明王朝末期の1638年に設置された砲であり、射程距離は500mとあった。






城門は二重門の構造となっていて、門の名前は「鍵鎖門」(けんさもん)といい、まさに「ここを突破されて北京が攻められることを防ぐために鍵をかけて閉鎖する」という意味を表わしている門だ。




城外に出て「土産物店」に立ち寄り、「八達嶺長城」の絵地図を買って見た。この地図によってこのあたりの長城の全貌がわかった。




北京への帰りは近くの小さな「八達長城駅」(始発・終着駅)から列車に乗ることとなった。なにか新幹線の車体正面とよく似た小さな普通列車だった。列車に乗ってしばらくすると、遥か山並に見事な万里の長城の景色が見えてきた。壮大な景色だった。70分くらいで北京市内の「北京北駅」に着いた。料金は25元(約500円)ほどだった。北京市内から八達嶺長城への往復交通料金は全部で一人145元(約2900円)と、とても安くついた。ありがたい。他に、「長城入場料やロープウェー料金」などが必要だった。
◆北京市周辺の「万里の長城」観光地について
最も多くの観光客が訪れるのが今回行った「八達嶺(はったつれい)の長城」。ここは北京市内から北西に約60kmとほど近く、列車や高速道路などの交通の便が最もよい。「慕田峪(ぼでんよく)の長城」は北京市内から北に75kmにあり、「八達嶺」ほど交通の便は良くないが、連なる山々に延々と続く素朴な長城が見られる場所として有名らしく、より野趣的で感動間違いなしと同僚の鈴木さんが言っていた。また機会があればぜひ行ってみたいと思っている。
北京にはほかに、「黄花城(おうかじょう)長城」「司馬台(しばたい)長城」「居庸関(いようかん)長城」など合計5箇所の地点で長城を公開しているようだ。特に「居庸関長城」(※北京市内から約50km)の門は、まるで城の大天守閣ような壮大な門が設置されているようだ。城好きの私にはたまらない。「八達嶺」の手前(北京により近い)場所らしいが、今回立ち寄れなかったのはとても残念だった。ここがまさに、北京防衛の最重要で最後の関門といえるのだろう。ここを破られたら、北京までは一直線の場所だ。
北方民族・蒙古(モンゴル)の英雄ジンギスカンがこの関門付近まで襲来して戦った歴史があるというが、陥落はさせられなかったようだ。その後、ジンギスカーンの孫の世代にあたる「クビライ」が万里の長城を越えて北京に侵攻し、その後300年間にわたった「宋王朝」を1260年に亡ぼし広大な「元・モンゴル帝国」を中国全土を含めて成立させ、北京に都(※「大都」)を築いた。(日本への2度にわたる「元寇」はこの時代に起きた。)
クビライは、蒙古(モンゴル)草原にあるカラコルムを夏の都とし、大都を冬の都とした。2000年のモンゴル・ゴビ砂漠恐竜発掘調査の際に、このカラコルムに立ち寄ったが、今は僅かに「ラマ教寺院」が残されているだけで一面の平原となっていた。100年間あまり続いた元王朝を1368年に滅亡させて成立したのが「明王朝」である。当初、都を「南京」に置いたが、その後「北京」を都とした。これにより、首都防衛の強化の必要性から「万里の長城」の拡大増強や補強に取り組んだ。現在中国国内に残されている約6300kmあまりの現存する長城のほとんどは、この明王朝時代に築きなおされたものである。(明王朝は約300年間続き1643年に滅亡し、満州族の清王朝に変わった。そして、清王朝は1912年までの約270年間続いた。)






北京北駅に着き、地下鉄に乗って「胡同(フートン)」が多く残る地区に行き、午後3時すぎに遅い昼食をとることとなった。案内された小さな店は、「护国寺小吃」という店名で、この胡同街では安くておいしいと有名な店のようだった。ここで、この日の夕方の新幹線で山東省まで帰る山本さんや米村さんは、食べ物を買ってから早々に新幹線駅に向かった。私も、昨日まで泊ったホテルにキャリーバックの荷物を取りに戻るため、食事後にみんなと別れて店を出た。その後、荷物を受け取り、午後7時半ころに、この日から泊る京都苑というホテルにようやく到着した。
今回、中国人の3人の人には大変親切にお世話になった。上記写真右より、①馬さん(神戸大学への留学経験あり。台湾在住で、中国大陸と台湾を行き来している。とても博識でおもしろい人。)②史さんの知り合いの若い女性。(日本語はできる。とても親切な人で、長城で滑って転倒しそうになった時、危うく支えてくれて助かった) ③史さん。(前号ブログで紹介)
◆ ―2022年北京冬季オリンピック会場は「八達嶺」からほど近い場所のようだ―
史さんの話によれば2022年冬季オリンピックはここから近いという。北京市内は昨年の11月よりずっと雨が降らず、私が今回行った少し前の3月中旬前に久しぶりに雨が降ったようだ。そして、3月17日には雪が激しく降りしきった。北京市内に雪が降るのはかなり珍しい(一冬に1〜2度あるかなしか)ことのようだ。薄っすらと雪化粧にはしばらくするが、積もったりすることはほとんどないようだ。2022年、北京での冬季オリンピックの雪はどうするのだろうか。




八達嶺からほど近いが、少し北に行くと、けっこう積雪があり(※と言っても十数センチ)、スキー場となっている地区があると史さんから教えられた。福州に戻ってからいろいろとインターネットで調べてみた。上記の写真の場所だ。スキー場の積雪が少ないため、人工雪を置いてスキー場としているらしい。このあたりがオリンピック会場の中心地となるようだ。北京冬季オリンピックでは、競技会場での雪は全て人工雪でまかなう計画だと言われている。
オリンピックに向けて、会場や建物、駅などを作る工事が進められているが、この地区の「村全体」が壊されて建築が進められているところも数か所あるようだ。もちろん各家にいくばくかの保障金は出るのだが、強制的で有無を言わさぬのが中国式でもあるようだ。(※上記の右写真の集落は更地にされて今はもうない) まあ このようなことの実態を知ると、北京冬季オリンピックを喜んで迎えにくくもなってしまう。
しかし、もし、北京冬季オリンピックを見に行った人は、万里の長城に足を運ぶことを勧めたい。会場から近いのだ。急な城壁上の転倒にはくれぐれも注意が必要だ。転倒したら軽い擦り傷だけではすまないだろう。滑落することとなる。それから、今回は3月19日という時期の「万里の長城」だったので、まだ草木が萌えず、緑がない状態の長城の景色だった。これが4月中旬以降からの時期だったら緑と長城のコントラストが美しかったかと思う。秋は紅葉が進み、さらに綺麗になるようだ。