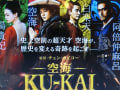白居易(はっきょい)[別称:白楽天] 772年~846年(75歳没)、唐時代の詩人
「八月十五日夜禁中 独直対月憶元九」 白居易 (七言律詩)
銀台金闕夕沈沈 独宿相思在翰林 三五夜中新月色 二千里外故人心
渚宮東面煙波冷 浴殿西頭鐘漏深 猶恐清光不同見 江陵卑湿足秋陰
(漢文読み)
「八月十五日の夜 禁中(きんちゅう)に独(ひと)り 直(とのい)し月に対して元九(げんきゅう)を憶(おも)う」
銀台(ぎんだい)金闕(きんけつ) 夕(ゆうべ)沈沈(ちんちん) 独直(どくしゅう) 相(あい)思いて翰林(かんりん)に在(あ)り
三五(さんご)夜中(やちゅう) 新月(しんげつ)の色 二千里外 故人(こじん)の心
渚宮(しょきゅう)の東面 煙波(えんぱ)冷(ひ)ややかに 浴殿(よくでん)の西頭(せいとう) 鐘漏(しょうろう)深し
猶(な)お恐る 清光(せいこう)同じくは見ざらんことを 江陵(こうりょう)は卑湿(ひしつ)にして秋陰(しゅういん)足(おお)し
■(意味)—宮中のあちこちにそびえる楼(たかどの)が夜のしじまの中に見える。私はひとり翰林院(かんりんいん)に宿直しながら、君のことを思っている。今宵(こよい)十五夜、のぼったばかりの明月に二千里彼方(かなた)にいる君の心がしのばれる。
君のいる渚宮の東は、もやにかすむ水面(みなも)が月に冷たく光っているだろう。私のいる宮中の浴殿の西は、時を告げる鐘(かね)や水時計の音が、しじまに深々ときざまれている。心配なのは、君がこの清らかな月を見られないのではないかということだ。なぜなら、江陵の地は低く湿っぽくて、秋でも曇りがちの日が多いというから。
※中秋の名月(明月)の夜、宮中にひとり宿直した白居易が、親友の元愼(げんじん)を思いやった作。この親友は、政治的才能を早くに認められながらも、直情怪行な性格のため官界とそりが合わず、三十二歳の時、江陵(湖北省江陵県)に左遷された。白居易は中央にいて翰林学士の任にあった。彼の友を思うしみじみとした心が秋の気とともに伝わってくる一作。

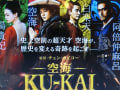



白居易は別称の白楽天で知られている唐代の詩人だが、2017年に公開された映画「空海—美しき王妃の謎」に主要キャストの一人として登場もする。(この映画は、中国での公開名は「妖猫伝」。原作は日本人の作家・夢枕獏。監督は中国人の陳凱歌[チェン・カイコー]。日中合作映画で、日本人俳優としては渋谷将太[空海役]、阿部寛[阿倍仲麻呂役]。他に主要キャストには玄宗皇帝や楊貴妃、安禄山など‥。阿倍仲麻呂は、奈良時代の717年に唐に遣唐使とともに留学。玄宗にも仕え770年に唐で没した。白楽天はその2年後の772年生まれなので、史実的には二人は会ってはいないこととなる。空海[弘法大師]は遣唐使に付随した留学生の一人として803年に唐に渡ってから2年間余りを長安で過ごしているので、白楽天と会っている可能性は高い。)





『唐玄宗紀』(小前亮著)という歴史小説がある。読んでみるととても面白く、一気に読み進めてしまった。このような歴史小説を読むことで、よりこの唐時代の歴史がより具体性をもってイメージされてくる。玄宗皇帝に仕え、名臣として名高い宦官(かんがん)の高力士の目から描いたこの物語。楊貴妃の出現、そして安禄山の大乱[安史の乱](755年~763年)によって国はとめどなく乱れていく。この時代を背景に描いた歴史大河小説だった。
この安禄山の大乱の悲劇の始まり後の50年後に、白楽天によって詠まれた漢詩が「長恨歌(ちょうごんか)」だった。この漢詩は120句もの長さにわたる長大な一編の漢詩。玄宗皇帝と楊貴妃との恋、そして寵愛、安禄山の乱で長安を落ち延びる玄宗。彼に付き添う楊貴妃を殺さざるをえなくなった玄宗との悲劇を詠む「長恨歌」。
「漢皇重色傾国‥」(漢皇[かんこう]女色を重んじて傾国を思う‥/意味:漢の皇帝は絶世美女を求め続けていた‥)の第一句から始まる「長恨歌」は、唐王朝に配慮して、唐の皇帝ではなく、漢の皇帝として詠まれているが、読み進めればまぎれもなく、唐の時代の皇帝・玄宗と楊貴妃の物語であることがわかる。
実は紫式部の『源氏物語』は、この「長恨歌」の影響というか、「長恨歌」をヒントに物語の着想を得て書かれたものとも言えるかと思う。『源氏物語』(54帖)の最初の帖(章)である「桐壺の巻」からして、桐壷帝と桐壺の更衣(光源氏の父と母)の恋愛、そして寵愛、桐壺更衣の死という悲恋の描写、更衣の死後も彼女を想い続ける桐壺帝[天皇]の描写には、「長恨歌」を彷彿(ほうふつ)させる部分がたくさんある。また、『源氏物語』の中には「長恨歌」という漢詩の名前も書かれてもいる帖もある。




『源氏物語』は、主人公の光源氏の一生とその一族たちのさまざまな人生を、約70年間にわたって壮大な王朝文化とともに描いている物語。その一大叙事詩物語の着想となったのが白楽天の「長恨歌」であったことは先に少し述べたが、「長恨歌」が詠まれたのは806年(白楽天が35歳)の時だった。その後、この白楽天の漢詩集「白氏文集(はくしもんじゅう)」などの中国の漢詩は日本にも伝えられる。平安時代の貴族層(男女問わず)は、教養としてこの漢詩文が尊ばれることとなっていく。
清少納言は『枕草子』でこの白楽天の『白氏文集』を愛読書のトップに挙げているし、紫式部は仕えた藤原道長の長女・中宮彰子に『白氏文集』を講義している。『源氏物語』は漢詩の引用が多く、その出典の大半が『白氏文集』でもあることから、式部にとっても座右の書だったかと思われる。
『源氏物語』の須磨の巻に、宰相中将が須磨で謹慎中の光源氏を訪れる場面がある。そこで二人が酒を酌み交わしつつ唱和したのも『白氏文集』だった。物語には「酔ひのかなしび涙そそぐ春の杯のうち」と、詩の一節が書かれている。これは白楽天が任地に赴任する途中、左遷されていた友人に偶然出会って、旧交を温めた際に作られたとされるものだった。恵まれぬ境遇にある友との再会であること、酒を飲みながら語り合うこと、季節が春であることなど、物語の情景は詩句の詠うところとぴったり重なる感がする。
同じ須磨の巻には、さらに古い時代の詩人・屈原(くつげん)も出てくる。屈原は中国の春秋戦国時代、楚(そ)の国の貴族だった。有能な政治家でもあったが、讒言(ざんげん)によって追放され、孤愁の生活の果てに、石を抱いて川に身を投げたと伝わる人物。須磨の巻で、光源氏は船旅の心細さに次の和歌を詠む。「から国に 名を残しける 人よりも ゆくえ知られぬ 家居をやせむ」(中国で名を残した人[屈原]よりも 私はさらに 将来の知れない侘び住いをすることだろう。)
光源氏の和歌は、屈原と比べれば少し大げさではあるが、作者の式部はおそらく絶望感を高めるために源氏に屈原の故事を思い出させたのだろう。




カら1010年代前半までに執筆されたとされる『源氏物語』は、唐時代の詩人白楽天の影響がとても感じられる物語。当時の貴族層の男も女も、誰もが知る長恨歌のエピソードなどを、式部は上手く平安朝風に置き換えて物語にとりいれたようだ。桐壺帝の巻で書かれている桐壺更衣の容貌は詳しく書かれていないが、当時の貴族たちは「長恨歌」の絶世の美女・楊貴妃をイメージもしながら読むので、詳しく書く必要はなかったのだろう。このあたりも式部の上手いところだと思う。
紫式部を主人公にしたNHK大河ドラマ「光る君へ」で、主人公らが詠む場面がたびたび登場する漢詩に注目と関心が高まってもいるようだ。全国各地の「漢詩の会」などへの入会者が男女問わず増加しているとの報道もされていた。漢詩をもっと知りたい学びたい、漢詩を作ってみたいなどの入会動機という。
NHK大河ドラマ「光る君へ」もあと、10月・11月・12月の3カ月間あまりのドラマ放送となったが、『源氏物語』理解のためにも長恨歌を読んでみてみるのもいいかと思う。