(以下、読売新聞から転載)
============================================
通訳・翻訳ボランティア養成 外国人を被災者役に研修
「東日本」契機 座学中心→対応力向上へ
外国語通訳・翻訳ボランティアを養成する県国際交流協会(岡山市)は、言葉や文化の違いで<災害弱者>になりやすい外国人の支援を円滑に行えるよう座学中心の研修を実習訓練形式に変更する。東日本大震災後、より実践的な活動が必要なことが分かったためで、2月に実施する実習訓練では、外国人を被災者役にして、災害時に求められる対応力の向上をはかる。(有留貴博)
県は2005年3月、専門知識を生かして被災者を支援するボランティアの登録制度を設けた。建築物の危険度判定や手話通訳、外国語通訳・翻訳など5分野で、県内の災害発生時、市町村長の要請で活動する。外国語通訳・翻訳には、12言語延べ89人が登録している(11年末現在)。
これまで、年1回の研修では、主な新規登録者がボランティアの体験談を聞いたり、神戸市の「人と防災未来センター」を視察したりしていた。「実践的で、より効果的なものにしてほしい」との声も上がっていた。
研修内容の改善を考えていたところ、昨年3月に東日本大震災が発生。被災地で活動した他の国際交流協会などに聞くと、余震や被害状況をはじめ、避難所の利用法、福島第一原発事故の推移など多岐にわたる情報提供が求められたことが分かった。
実習訓練は2月19日、笠岡市保健センターを避難所に見立てて行う。外国人に参加してもらい、入所手続きや非常食の支給を受ける補助、対策本部が流す情報掲示の通訳・翻訳などを行う。同協会は「臨機応変に対応する力も問われるため、より災害時をイメージしたものにし、質の高い人材を養成したい」と意気込む。
阪神大震災や東日本大震災の際、外国人被災者を支援した神戸市のNPO法人・多言語センターFACIL(ファシル)の吉富志津代理事長は、ボランティアが地域のつなぎ役を担い情報交換を行うことで、「外国人と災害時にともに助け合える関係を構築し、他文化が共生するコミュニティー作りにつながる」と話している。
◇
県国際課や同協会は、ボランティア登録を募っている。同課によると、県内の外国人登録者数は2万2394人(10年末現在)。国籍別では、中国が1万82人と最も多く、韓国・朝鮮6565人、フィリピン1458人、ブラジル1347人と続く。だが、ボランティア89人中、英語の登録が52人を占め、中国語16人、ハングル5人、ポルトガル語2人となっており、実態に即していない。また、「被災時には実際に駆けつけられない人も出てくる可能性がある」(同協会)といい、多数の登録を呼びかけている。問い合わせは同課(086・226・7283)。
(2012年1月24日 読売新聞)
============================================
通訳・翻訳ボランティア養成 外国人を被災者役に研修
「東日本」契機 座学中心→対応力向上へ
外国語通訳・翻訳ボランティアを養成する県国際交流協会(岡山市)は、言葉や文化の違いで<災害弱者>になりやすい外国人の支援を円滑に行えるよう座学中心の研修を実習訓練形式に変更する。東日本大震災後、より実践的な活動が必要なことが分かったためで、2月に実施する実習訓練では、外国人を被災者役にして、災害時に求められる対応力の向上をはかる。(有留貴博)
県は2005年3月、専門知識を生かして被災者を支援するボランティアの登録制度を設けた。建築物の危険度判定や手話通訳、外国語通訳・翻訳など5分野で、県内の災害発生時、市町村長の要請で活動する。外国語通訳・翻訳には、12言語延べ89人が登録している(11年末現在)。
これまで、年1回の研修では、主な新規登録者がボランティアの体験談を聞いたり、神戸市の「人と防災未来センター」を視察したりしていた。「実践的で、より効果的なものにしてほしい」との声も上がっていた。
研修内容の改善を考えていたところ、昨年3月に東日本大震災が発生。被災地で活動した他の国際交流協会などに聞くと、余震や被害状況をはじめ、避難所の利用法、福島第一原発事故の推移など多岐にわたる情報提供が求められたことが分かった。
実習訓練は2月19日、笠岡市保健センターを避難所に見立てて行う。外国人に参加してもらい、入所手続きや非常食の支給を受ける補助、対策本部が流す情報掲示の通訳・翻訳などを行う。同協会は「臨機応変に対応する力も問われるため、より災害時をイメージしたものにし、質の高い人材を養成したい」と意気込む。
阪神大震災や東日本大震災の際、外国人被災者を支援した神戸市のNPO法人・多言語センターFACIL(ファシル)の吉富志津代理事長は、ボランティアが地域のつなぎ役を担い情報交換を行うことで、「外国人と災害時にともに助け合える関係を構築し、他文化が共生するコミュニティー作りにつながる」と話している。
◇
県国際課や同協会は、ボランティア登録を募っている。同課によると、県内の外国人登録者数は2万2394人(10年末現在)。国籍別では、中国が1万82人と最も多く、韓国・朝鮮6565人、フィリピン1458人、ブラジル1347人と続く。だが、ボランティア89人中、英語の登録が52人を占め、中国語16人、ハングル5人、ポルトガル語2人となっており、実態に即していない。また、「被災時には実際に駆けつけられない人も出てくる可能性がある」(同協会)といい、多数の登録を呼びかけている。問い合わせは同課(086・226・7283)。
(2012年1月24日 読売新聞)










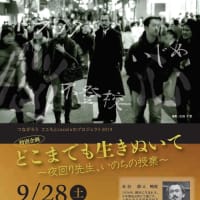
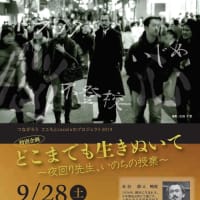

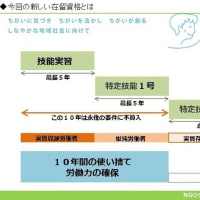

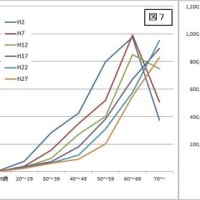
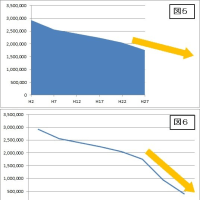
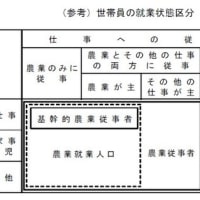
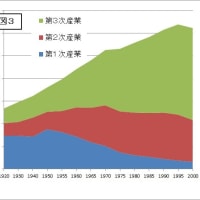
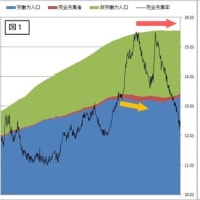
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます