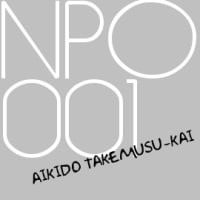豊臣秀吉の聚楽第跡から本丸内堀の石垣が見つかったと京都府埋蔵文化財調査研究センターが発表した。
【現地説明会】
聚楽第は豊臣秀吉が関白に就任した翌年、1586年に京都の公邸として構えた城郭で1587年に完成した。後陽成天皇を迎えるなど権勢と栄華を象徴する豪華な城郭であった。この聚楽第で徳川家康ら有力大名に忠誠を誓わすなどした。また天正少年使節の謁見もここで行われた。1591年に甥の秀次に関白職を譲り、聚楽第も譲ったが、後に秀次を謀反の嫌疑で切腹させた。1595年に聚楽第を破却、その建物の多くは伏見城へ移建された。
京都市上京区智恵光院通上長者町角の京都府警本部宿舎建設工事現場約1100平方メートルを調査。聚楽第本丸を囲む東西約200メートル、南北約320メートルの堀(幅約40メートル)の南側から2、3段に積まれた石垣が東西約7メートルにわたって見つかった。石は計11個あり、長さ約100〜70センチ、幅約50センチ前後。ほとんど加工されることなく割っただけの石だが大きさや形が揃えられていて、本丸の正面を飾るに相応しい石組みである。また本丸の城郭の地形が南と北で2メートルの高低差があったことがわかった。
聚楽第の絵図は複数存在するが、三井記念館所蔵の「聚楽第図屏風」は最も忠実に描写されているものとされ、秀次が造営した北之丸には土地の高低差を利用した天守が荘麗な姿を見せていたと考えられる。
今回の調査では、聚楽第で用いられていた金箔のついた瓦も出土、土師器皿を廃棄した土坑や柱穴などの遺構も見つかった。
1624年頃作成の最古の京地図「京都図屏風」には秀吉による城郭都市形成への御土居が描かれ、すでに破却された聚楽第の城郭を示す堀が記されている。
聚楽第の内堀は、北は一条通、南は下長者町通、東は大宮通、西は智恵光院通の範囲で、外堀は、北は元誓願寺通、南は下立売通、東は堀川通、西は千本通近くに及ぶと推定される。
今回の調査から、はじめて本丸南堀北端の正確な位置が判明した。従来の復元案よりも南に位置し、櫓台や、入り口部分の張り出しによって城壁が屈曲している。聚楽第の構造を知るうえで貴重な成果を得ることができたという。 (現地説明会資料「平安宮跡・聚楽第跡」参照)
京都府警察本部西陣待機宿舎建設工事に伴い、平安宮跡ほかの発掘調査を実施しました。この地は平安宮の大内裏、安土桃山時代の聚楽第のあった位置にあたります。調査の結果、近世段階に聚楽土を採掘した穴や井戸、ごみ捨て穴などを検出しました。聚楽第に関する遺構として、土師器皿を廃棄した土坑や柱穴が、調査地の南端では聚楽第の内堀推定地点で、調査地外に延びる落ち込みと石垣が検出され、聚楽第との関連が注目されます。また、戦国時代の土坑が2基検出され、聚楽第以前の土地利用の一端をうかがうことができます。 (京都府埋蔵文化財調査研究センターHP)
【現地説明会】
聚楽第は豊臣秀吉が関白に就任した翌年、1586年に京都の公邸として構えた城郭で1587年に完成した。後陽成天皇を迎えるなど権勢と栄華を象徴する豪華な城郭であった。この聚楽第で徳川家康ら有力大名に忠誠を誓わすなどした。また天正少年使節の謁見もここで行われた。1591年に甥の秀次に関白職を譲り、聚楽第も譲ったが、後に秀次を謀反の嫌疑で切腹させた。1595年に聚楽第を破却、その建物の多くは伏見城へ移建された。
京都市上京区智恵光院通上長者町角の京都府警本部宿舎建設工事現場約1100平方メートルを調査。聚楽第本丸を囲む東西約200メートル、南北約320メートルの堀(幅約40メートル)の南側から2、3段に積まれた石垣が東西約7メートルにわたって見つかった。石は計11個あり、長さ約100〜70センチ、幅約50センチ前後。ほとんど加工されることなく割っただけの石だが大きさや形が揃えられていて、本丸の正面を飾るに相応しい石組みである。また本丸の城郭の地形が南と北で2メートルの高低差があったことがわかった。
聚楽第の絵図は複数存在するが、三井記念館所蔵の「聚楽第図屏風」は最も忠実に描写されているものとされ、秀次が造営した北之丸には土地の高低差を利用した天守が荘麗な姿を見せていたと考えられる。
今回の調査では、聚楽第で用いられていた金箔のついた瓦も出土、土師器皿を廃棄した土坑や柱穴などの遺構も見つかった。
1624年頃作成の最古の京地図「京都図屏風」には秀吉による城郭都市形成への御土居が描かれ、すでに破却された聚楽第の城郭を示す堀が記されている。
聚楽第の内堀は、北は一条通、南は下長者町通、東は大宮通、西は智恵光院通の範囲で、外堀は、北は元誓願寺通、南は下立売通、東は堀川通、西は千本通近くに及ぶと推定される。
今回の調査から、はじめて本丸南堀北端の正確な位置が判明した。従来の復元案よりも南に位置し、櫓台や、入り口部分の張り出しによって城壁が屈曲している。聚楽第の構造を知るうえで貴重な成果を得ることができたという。 (現地説明会資料「平安宮跡・聚楽第跡」参照)
京都府警察本部西陣待機宿舎建設工事に伴い、平安宮跡ほかの発掘調査を実施しました。この地は平安宮の大内裏、安土桃山時代の聚楽第のあった位置にあたります。調査の結果、近世段階に聚楽土を採掘した穴や井戸、ごみ捨て穴などを検出しました。聚楽第に関する遺構として、土師器皿を廃棄した土坑や柱穴が、調査地の南端では聚楽第の内堀推定地点で、調査地外に延びる落ち込みと石垣が検出され、聚楽第との関連が注目されます。また、戦国時代の土坑が2基検出され、聚楽第以前の土地利用の一端をうかがうことができます。 (京都府埋蔵文化財調査研究センターHP)