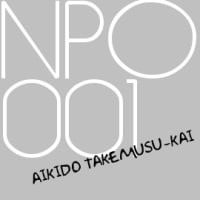当時植芝盛平は、大阪の警察署や憲兵隊などへ武道の指導にいっていた。そればかりでなく、幾ヵ所もの民間団体からも稽古を依頼されて廻っていたから多忙な時期である。
そこの道場で、あるとき稽古の休憩中に、道場主である門人が、
「先生、昔から忍術というものがありますが、あんなことは出来るものですか」
と聞いた。盛平は、
「忍術は昔からあるが、活動写真でやっているような、煙が出てドロンドロンと消えるあんなものではないよ」
という。この道場は六十畳(330平方メートル)の広さで、道場と控えの間のあいだは、二階に上がる階段があるという造りである。
先生は道場の真中に立って、十数人の門弟たちに木刀、棒、銃剣術の木銃などを持たして取囲まれている。先生は、
「みんないっしょに、突くなり打つなり、かかってくるんだ」
というので、門弟たちは気を合わせて、
「ヤッ」
とかけ声もろとも打ってかかった。その時、門弟たちは何か、
「ヒュー」
という音か声を聞いたような気がしたが、見るとそこには、先生の影も姿も見えなかった。ウロウロしていると、
「ここだ、ここだ」
と声があった。声の方をふり向くと、二階へ上る階段の途中に腰かけた先生の顔があった。道場の真中からそこまでは三間から三間半(6、7メートル)の距離がある。道場の階段付近の途中に、門弟たちが十人ばかり休憩していて、
「君たちは、先生がここを通るのを知らなかったのか」
と、他の門弟たちに聞かれたが、誰も知らないという。
「忍術て、こんなもんや」
と、先生が笑っていった。
またその後、この道場に地方の名士などおおぜい見に来ているときに、その人たちにも先の忍術の一件を見てもらおうと思って、道場の主人が、
「先生、忍術をやってくれませんか」
とねだると、温厚な盛平が顔色をかえて、
「お前たちは俺(わし)を殺す気か」
といった。門人たちは驚いてわけを聞くと、
「あんなことをしていると、五年も十年も寿命をちぢめるのじゃ」
といって、ものすごく怒られたという。
この町の道場主の名は田中万川(本名、伊三郎)である。
資料:砂泊兼基「合氣道開祖植芝盛平」講談社
写真:田中万川「合氣道神髄」/真空の気
そこの道場で、あるとき稽古の休憩中に、道場主である門人が、
「先生、昔から忍術というものがありますが、あんなことは出来るものですか」
と聞いた。盛平は、
「忍術は昔からあるが、活動写真でやっているような、煙が出てドロンドロンと消えるあんなものではないよ」
という。この道場は六十畳(330平方メートル)の広さで、道場と控えの間のあいだは、二階に上がる階段があるという造りである。
先生は道場の真中に立って、十数人の門弟たちに木刀、棒、銃剣術の木銃などを持たして取囲まれている。先生は、
「みんないっしょに、突くなり打つなり、かかってくるんだ」
というので、門弟たちは気を合わせて、
「ヤッ」
とかけ声もろとも打ってかかった。その時、門弟たちは何か、
「ヒュー」
という音か声を聞いたような気がしたが、見るとそこには、先生の影も姿も見えなかった。ウロウロしていると、
「ここだ、ここだ」
と声があった。声の方をふり向くと、二階へ上る階段の途中に腰かけた先生の顔があった。道場の真中からそこまでは三間から三間半(6、7メートル)の距離がある。道場の階段付近の途中に、門弟たちが十人ばかり休憩していて、
「君たちは、先生がここを通るのを知らなかったのか」
と、他の門弟たちに聞かれたが、誰も知らないという。
「忍術て、こんなもんや」
と、先生が笑っていった。
またその後、この道場に地方の名士などおおぜい見に来ているときに、その人たちにも先の忍術の一件を見てもらおうと思って、道場の主人が、
「先生、忍術をやってくれませんか」
とねだると、温厚な盛平が顔色をかえて、
「お前たちは俺(わし)を殺す気か」
といった。門人たちは驚いてわけを聞くと、
「あんなことをしていると、五年も十年も寿命をちぢめるのじゃ」
といって、ものすごく怒られたという。
この町の道場主の名は田中万川(本名、伊三郎)である。
資料:砂泊兼基「合氣道開祖植芝盛平」講談社
写真:田中万川「合氣道神髄」/真空の気