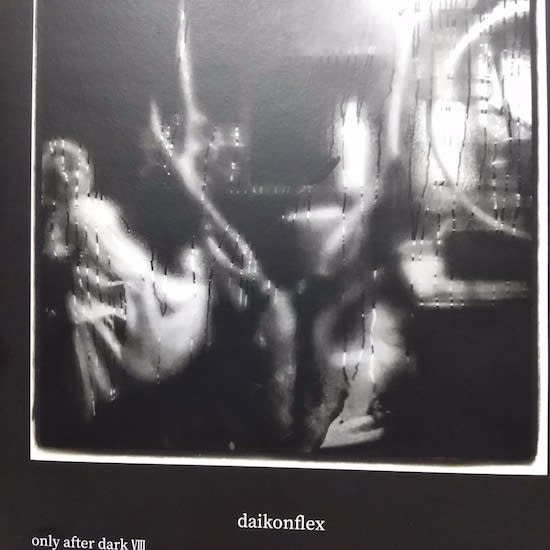
バブル時代を基準にするのは問題が多いのだが、バブル以前はものごとが”進んで”行ったし、日本以外の先進諸国は現在も進んでいる。
進むというのは更新されていくということで、そこでは金が動いてその金額も増えていくと言っていいのだろう。
現在の情勢の反対を想像すればいいわけで、金がかかることもやってみる、チャレンジする、新しい事を面白がる、過去に縛られない、発想の転換をする、マイナス評価しないが”目標”だったりしたわけだ。(微妙な言い方)
そういう中で実生活とは関係ない出費(そんなもの現在はどれだけあるのだ)にお金をかけることに否定的でない考え方を生み出して、それが表現とか美術とかにも影響を与えて”潤い”をもたらしているわけだが、しょせんは無駄金、困った時には一番にカットされる運命にある。だから現在の日本には潤いがないんだろうね。
そういう中でも人は生きていて、例えばヨーロッパなどは日本のバブルの頃からずっと不景気で若者は仕事にあぶれ生活は荒れているんだけど、そういう生活の中からアートの革新が起こったりしたわけだ。
エド・ファン・デア・エルスケンの写真集に「セーヌ左岸の恋」というのがあり、パリにある時期集まった若者たちの姿を物語風に写真集にしたものである。
時代的には第二次世界大戦が終わってようやく一息ついた頃だろうか(1950ー54)。
まだ新たな価値観が定まらない時期に若さをあふれさせた各国の若者が一か所に集まり交流し、去っていったのだ。
その時間の中からその後さまざまな人が華を咲かせていったわけで、その影響力は現在も続いていると言えよう。
そして日本でも同様に若者が集い、何かを生み出していった。
そういう動きはバブル崩壊後沈静化してしまったように感じられたのだが、そうではなく静かに各地で続いていたようだ。
特に関西では地理的な事とかあってか人間関係性が濃く、良くも悪くも波紋を広げて影響しあう。
数年前に一時期関西で仕事をしていた時に色々な場所を彷徨ったけれど、残念ながらその時にはキチンとしたアンテナが働かずそういう動きに対応できずに関東に引き揚げてきたのだが、ここしばらくはすっかり関西に目が離せない状況が続いている。
京都に集まる若者が中心にアート関連で動きまわっている。
関西は狭いところなので、当然大阪や近郊にも影響を与えているが、その活動の中心が写真やパーフォマンスなのだが、ネットでも画像を上げたり活動報告をおこなっている。
この動きを従来のアート”業界”(そんなものがあればだが)の基準で考えればドシロートのお遊びとなるのだが、上記のようにすでに日本において金の動く表現活動などバブル比で比べなくても何分の1にも縮小して、むしろそんな基準で現在の若者たちの動きをはかるのもおこがましい状況なのである。
そこに金でものごとをはからない若者が好き勝手をするのだから愉快でないわけがない。
それを従来の基準に照らして下手くそ、ありきたり、作品と呼べない等々酷評するのは簡単だが、その基準ってどれだけ昔の古びたものなのだろう。
キチンとした形で作品を作り、権威ある人に見出され、作品としての価値が上がり、広告にも使われてお金が入ってきて時代の基準となる。
そんなことはこれからはあり得ないのだ。
そんな”シンデレラストーリー”よりも現在は”アナ雪”の時代なのだ。
自分が楽しいと思ったことをして仲間と時間を共有する。
そのためのツールがカメラであったりするわけで、媒体はネットであったり(それもツイッターとか流れ去る時間が短いもの中心)近場での展示だったり、コンパクトな写真集だったりシロートぽいのだ。
今はその身軽さが力となる時代なのだ。
権威あるギャラリーで展覧会をしてなんぼの世界は去っていったのだ。
そういう”京都派”の中心人物の一人であるdaikonflexさんが恒例の写真展を行ない同時に写真集「only after dark VIII」を作って、贈っていただいた。
この写真集を見るには二つのとらえ方があり、一つは彼によって日々書き込まれるツイッターの世界をなぞりながら見るか、一つの作品集として眺めるかであろう。
しかし結果的にはどちらであっても2019年の京都での若者の日々の出会いと別れの物語を味わう事になる。
まさしく「鴨川右岸の恋」なのだ。
進むというのは更新されていくということで、そこでは金が動いてその金額も増えていくと言っていいのだろう。
現在の情勢の反対を想像すればいいわけで、金がかかることもやってみる、チャレンジする、新しい事を面白がる、過去に縛られない、発想の転換をする、マイナス評価しないが”目標”だったりしたわけだ。(微妙な言い方)
そういう中で実生活とは関係ない出費(そんなもの現在はどれだけあるのだ)にお金をかけることに否定的でない考え方を生み出して、それが表現とか美術とかにも影響を与えて”潤い”をもたらしているわけだが、しょせんは無駄金、困った時には一番にカットされる運命にある。だから現在の日本には潤いがないんだろうね。
そういう中でも人は生きていて、例えばヨーロッパなどは日本のバブルの頃からずっと不景気で若者は仕事にあぶれ生活は荒れているんだけど、そういう生活の中からアートの革新が起こったりしたわけだ。
エド・ファン・デア・エルスケンの写真集に「セーヌ左岸の恋」というのがあり、パリにある時期集まった若者たちの姿を物語風に写真集にしたものである。
時代的には第二次世界大戦が終わってようやく一息ついた頃だろうか(1950ー54)。
まだ新たな価値観が定まらない時期に若さをあふれさせた各国の若者が一か所に集まり交流し、去っていったのだ。
その時間の中からその後さまざまな人が華を咲かせていったわけで、その影響力は現在も続いていると言えよう。
そして日本でも同様に若者が集い、何かを生み出していった。
そういう動きはバブル崩壊後沈静化してしまったように感じられたのだが、そうではなく静かに各地で続いていたようだ。
特に関西では地理的な事とかあってか人間関係性が濃く、良くも悪くも波紋を広げて影響しあう。
数年前に一時期関西で仕事をしていた時に色々な場所を彷徨ったけれど、残念ながらその時にはキチンとしたアンテナが働かずそういう動きに対応できずに関東に引き揚げてきたのだが、ここしばらくはすっかり関西に目が離せない状況が続いている。
京都に集まる若者が中心にアート関連で動きまわっている。
関西は狭いところなので、当然大阪や近郊にも影響を与えているが、その活動の中心が写真やパーフォマンスなのだが、ネットでも画像を上げたり活動報告をおこなっている。
この動きを従来のアート”業界”(そんなものがあればだが)の基準で考えればドシロートのお遊びとなるのだが、上記のようにすでに日本において金の動く表現活動などバブル比で比べなくても何分の1にも縮小して、むしろそんな基準で現在の若者たちの動きをはかるのもおこがましい状況なのである。
そこに金でものごとをはからない若者が好き勝手をするのだから愉快でないわけがない。
それを従来の基準に照らして下手くそ、ありきたり、作品と呼べない等々酷評するのは簡単だが、その基準ってどれだけ昔の古びたものなのだろう。
キチンとした形で作品を作り、権威ある人に見出され、作品としての価値が上がり、広告にも使われてお金が入ってきて時代の基準となる。
そんなことはこれからはあり得ないのだ。
そんな”シンデレラストーリー”よりも現在は”アナ雪”の時代なのだ。
自分が楽しいと思ったことをして仲間と時間を共有する。
そのためのツールがカメラであったりするわけで、媒体はネットであったり(それもツイッターとか流れ去る時間が短いもの中心)近場での展示だったり、コンパクトな写真集だったりシロートぽいのだ。
今はその身軽さが力となる時代なのだ。
権威あるギャラリーで展覧会をしてなんぼの世界は去っていったのだ。
そういう”京都派”の中心人物の一人であるdaikonflexさんが恒例の写真展を行ない同時に写真集「only after dark VIII」を作って、贈っていただいた。
この写真集を見るには二つのとらえ方があり、一つは彼によって日々書き込まれるツイッターの世界をなぞりながら見るか、一つの作品集として眺めるかであろう。
しかし結果的にはどちらであっても2019年の京都での若者の日々の出会いと別れの物語を味わう事になる。
まさしく「鴨川右岸の恋」なのだ。

























