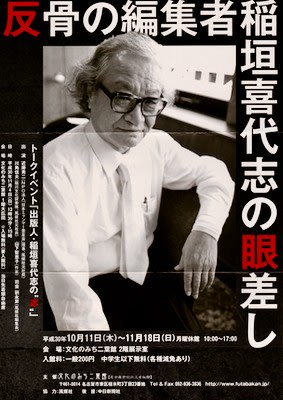メダカが来てから一週間。メダカの天敵がいることは予想していた。小魚を捕食する水生昆虫などは近くにもいないし、火鉢の中へやってくることはないだろう。
とすると、あとは猫か鳥類だ。そこで、夜間には網戸のネットを利用したカバーを掛けることにした。われながらいいアイディアだと思った。
しかし、いつも掛けておくわけではなく、餌をやる時間は全開し、昼間は半分、ないしそれ以上は開けておくことにしている。だって、メダカたちにも、ホテイアオイにも、充分陽の恵みを与えてやりたいではないか。

彼らがやってきて以降、それでうまくやってきた。だから16日も、朝、餌をやってから半分以上を開放状態にしておいた。
昼、覗きに行って、ア、と思った。なんと、ホテイアオイの葉の上に、アマガエルが一匹乗っているではないか。これは想定外だった。
慌てて追いかけ回し、捕らえて火鉢の外へ追放した。
メダカたちは何ごともなかったように元気に泳ぎ回っている。
そこでハッと気づいた大問題は、アマガエルはメダカを食うかどうかだ。さっそくネットで検索した。
ところがどうだ。その回答はほぼまっ二つ。
「アマガエルは陸上で昆虫などを捕食し、水中のものは食べません、うちでは、メダカとアマガエルが共存しています」というものがある一方、「アマガエルは陸上だろうが水中であろうが、小さな動くものに反応し捕食します、うちのメダカが減ったのはそのせいだろうと思います」というのもあって、10近くの回答のうち、その可否はほぼ半々。

ならば自分の目で確かめてみようと火鉢のヘリで目視の観察。ホテイアオイも引き上げて数えてみる。
わが家へ来たときの構成はこうだった。緋メダカ5、スタンダード3、シルバーまたはホワイト3(この中には脊椎が曲がったノートルもいた)、そして真っ黒が1、で計12尾。
懸命に数える。緋色の5尾はすぐ確認できる。スタンダードは地味で数えにくいから後回し。続いて白ないしはシルバー、ん?2尾は確認、残るはノートル・・・・、目を凝らすが見当たらない。
後で確認するとしてほかを探す。黒いのは底の方にいた。そしてスタンダード。よくわからないが、2尾は確認できた。
もう一度最初から数えてみる。ノートルがいないのは確実だ。スタンダードの残り一尾も怪しい。結局、12尾中確認できたのは10尾。
では、アマガエルが食べたのであろうか?それはあまり信じたくはない。うちにはアマガエルはいっぱいいる。しかも彼らは、メダカたちがくる前はこの家のアイドルだったのだ。
近づいてもあまり逃げようともせず、夜、彼らの居そうな繁みに向かって、「ケケケケケケ」とやや高い声で呼びかけると、時として「ケケケケケケ」と鳴き返してくれる愛嬌もの。
そんな彼らが、メダカの天敵だとは思いたくないではないか。

たまたまアマガエルが火鉢の中のホテイアオイの上にいた。そしてメダカの数が減った。これは並行して起こったことだが、この間を因果関係で結びつけるのはやめようと思う。
ただし、網戸用のネットを利用した防御措置は一応強化しよう
それから、もうひとつ、メダカたちを個別に識別し、それに名付けることもやめようと思う。なまじっか名付けたりするから、それの「死」を意識しなければならない。単にメダカたちとのみ心に留めておけば、「数が減った」で済むではないか。

ナチスだって、ユダヤ人を名前で記憶せず番号で呼んでいた。だから、「殺す」という意識を抜きに、「移送」し「最終処分」できたのだ。
さらにいうなら、日本軍の731部隊も、生体解剖の対象を「丸太」とし、一本、二本と数えることで「殺す」のではなく「実験対象」とし得たのではなかったか。
とはいえ、唯一名付けた「ノートル」は、やはり「減った」のでなく「死んだ」のだ。しかも名付けたことによって、その死は悼ましい。
生き物を飼うということはこういうことなのだ。
*写真の白いメダカはすべて在りし日のノートル