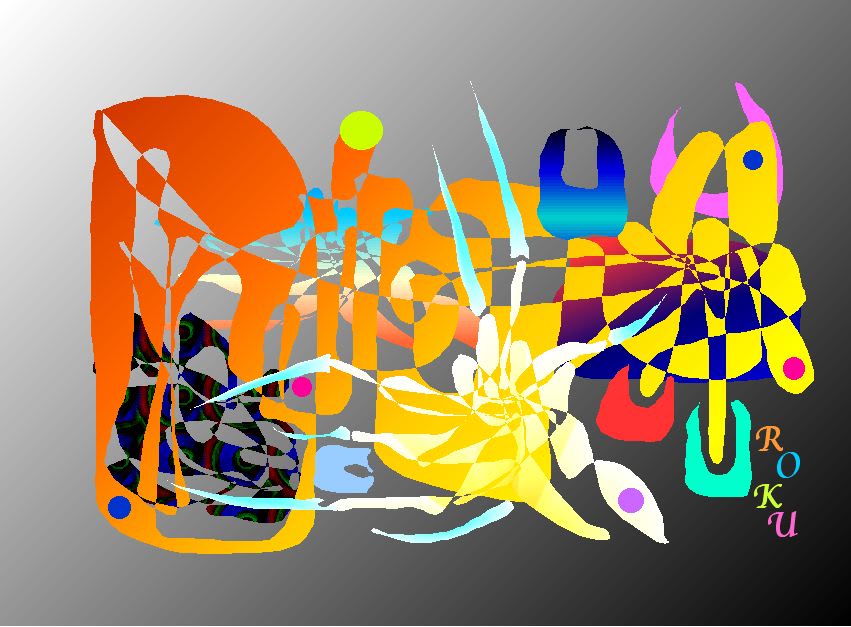かつて、というのは私の若い頃だが、近未来小説のバイブルといったら、
ジョージ・オーウェルの『1984年』であった。
そこでは、当時のソ連など一般に全体主義国家をさらに徹底したようなディス・ユートピアが描かれ、行動の自由はむろん、内面の思想などまでが、ハイテクを駆使した監視下にある状況が描かれている。
もちろん一党独裁管理の社会だが、その社会のスローガンは、
1)戦争は平和
2)自由は屈従
3)無知こそ力
というものである。
ところで、この小説、私の若い頃はほとんど必読書扱いであったが、最近はあまり読まれていないようだ。
その要因は、
「1984年」が実際に過ぎ去ってしまったこと、さらにはその後数年をしてソ連圏などの
一党独裁支配の国の大半が姿を消したことにあると言えよう。

しかしそれは、そうした時間的・歴史的変遷にとどまらず、
オーウェルのこの小説の射程距離の限界をも示すものではないだろうか。
その限界を私は以下のように考える。
1)そこで描かれた管理社会を、例えば
狭義のスターリニズムのようなものに限定し、いわゆる民主制の回復によって問題が解消しうるかのように考えたこと(だから、単純な反共小説として迎えられた側面をも持つ)。
2)それをある特殊な閉塞された社会の病理として描き出したが、実は
科学技術の発展に内在するさらに普遍的な問題でもあるという側面を描ききっていないこと。
3)従って、そこでの状況は、ある種の
狂気による病いとして描かれているが、反面、
理性という名の狂気という病いでもあり、それは
体制の如何に関わらず今日も継続しつつある問題ではないかということ。
以下は、最近読んだ本からの抜粋であるが、それは、あとから種明かしするように、哲学や社会科学のようないわゆる硬派の本ではなく、
エンターティメント性のある小説である。
「20世紀の夢はついえ去った。
共同体は啓蒙された市民が自発的に集まってくる場所だという考えは永久に葬り去られたんだ」
「われわれは・・・・ほとんど、あらゆる形の市民参加を放棄して、
社会の経営を一握りの政治技術者に任せて満足している。・・・共同体的価値を尊重するような口ぶりをしているが、実際はひとりでいたいんだ」
「隅々まで正気が支配する社会では、狂気が唯一の自由なんだ」
「ファシズムとは、根深い無意識の要求を満たす
>仮想的な精神異常正常であることが危険な世界に突入したんだぜ」
「人間の魂にすらバーコードが印刷されているんだ」
既に述べたが、この小説は、何ら思想的な問題を正面に掲げたものではなく、いわゆる
ミステリー小説なのである。そして、以上の台詞は、この小説の主人公、いわゆるヒーローのものではなく、その
犯人と目される人物のものなのだ。
前にも述べたように、私は幾分堅いものを読んだりした後、固まった頭へのご褒美としてミステリーを読む。それもトランダムで、上記のものも、図書館で題名を観て、映画が絡んだものかなと思って借りてきたに過ぎない。

作者は、英国の
J・G・バラードで、小説の題名は『スーパー・カンヌ』(2000年・新潮社刊)。もともとは、SF作家らしいが、この小説についてはミステリーサスペンス風である。
実は、この前に同じ作家の
『コカイン・ナイト』を読んだのだが、これもミステリー風であった。
さて、先に引用した台詞を思い起こしていただきたい。
私はそこに、
オーウェルの『1984年』の続編を、そして、さらに
一層拡大された現代という病いを読みとるのだ。
小説のことだから、あまり詳しくは述べないが、その舞台は、カンヌ近くのシリコンバレーを思わせる先端企業や研究所の集まった理想都市、「エデン=オランピア」である。人々は、そこでありとあらゆるものを与えられ、自由に研究や事業にいそしむことが出来る。ところが・・。
私たちは今、20世紀の経験に懲りたのか、
自分たちを投企すべき近未来に関する思考やイメージを棚上げしたままで生きている。そして、
生産と消費という枠の中でしかその知力を働かせようともしない。
一方ではそれは、
科学技術のめざましい発展に裏打ちされてもいる。私たちの未来は、その発展により無限に開かれているのであり、その運用の効率と享受、つまり、生産と消費のみが課題なのである。
生産と消費とは確かに人間的な行為ではあるが、同時に、限りなく動物的なものとの接点でもある。そこにはプリミティヴな意味での生が張り付いていて、その維持と延命が課題となる。
それは、私たちの個人においてそうであるばかりでなく、
政治全体がその生の管理に関わる「狭義の政治」に限定されてしまっているということである。これは、かつて
ハンナ・アレントが説き、
ミッシェル・フーコーが幾分別の切り口で語り、今日、
ジョルジョ・アガンベンが展開しつつあるところであるが、その詳論はおく。

その意味では、
「歴史は終焉」したのであり、ある種の
「ポストモダン」状況の到来とも言えるのであろう。
ギリシャ時代のポリスにおいての「活動」としての政治(それは奴隷労働や女性の家事労働というエコノミーに支えられていたという問題を孕んでいるのだが)や、生産と消費にとどまらない、
自分たちのありようの近未来への投企としての政治といういわゆる「広義の政治」は、もはやほとんど問題たり得ない。
それを敢えて言い立てるのは「ダサイ」ことなのだ。
こうして私たちは、その
魂にもバーコードを貼り付けて、生きていくのだろうか。