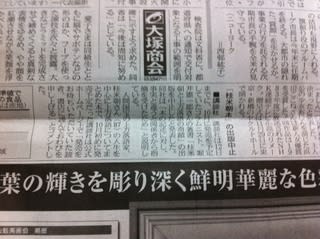日本人はフランス語を誤解している!・・・と思うけどなあ・・・
フランス語系人のBO-YA-KI
すばらしいワールドカップ
今回のワールドカップは、非常に意義深い、すがすがしいものでした。
アルジェリアの健闘、優勝国ドイツに敗れたとはいえ一点差で渡り合った正々堂々たる闘いぶりは世界中の、とくにイスラム圏、アラブ圏の人たちの共感をあつめています。アルジェリア・イレブンは、イスラムは卑劣なテロリストばかりではないことを世界に示してくれました。監督のヴァヒ―ド・ハリルホジッチにも一気に支持が集まり、大会前から退任が決まっていた彼をなんとかひきとめようという声が高まっていて、既にブーテフリカ大統領まで動き出しています。
ハリルホジッチ監督の母国ボスニアも、エディン・ジェコ選手を中心にチームがまとまり、国がまとまるという得難い経験をサッカーを通じて得ることができました。
アメリカ合衆国の健闘も注目に値します。ビジネス最優先のプロスポーツしか興味のなさそうだったアメリカ合衆国人のなかに「サッカー人」が増え始め、「アメリカ合衆国以外全部」の世界であるサッカー界で、他の国々と対等のチームとしてしのぎを削り合い、それを世界が見るというのは、どれだけ意義のあることか。
スアレスの噛みつきというのもありましたが、こういう行為をただ程度の低い人間が程度の低い行為をしている、とだけしか見られないのだったら、その人はもう終わっているといえるでしょう(日経の武智氏のコメントが意義深かったです)。
アルゼンチンに挑んで惜しくも敗れた時のイラン・ケイロス監督のコメントのすがすがしさには感激しました:「アルゼンチンのことは研究し尽くしていた。チームを抑えることはできたが、天才を抑えることができなかった。メッシでなければ決められなかったゴールだ」
そのアルゼンチンも、メッシに頼るところが大きすぎ、最後はドイツに屈しました。でも決勝戦を終了直前まで0-0で持ちこたえたのはすごい健闘でしたね。
唯一、すがすがしくなかったのが日本、だったような・・・(汗)
なんで日本は自分のところが負けたことの「反省」ばかりするんだろう。少しはコートディヴォワール・チームの頑張り、ドロバDrogbaの力量をさすがだと讃えてもいいのではないだろうか。
さて、ネイマールを怪我で失ったブラジルがたいへんもろい崩れ方を見せたのは、なんだかこの国が普通の大国としてグローバル経済にしっかり組み込まれ、みんながまともに仕事し、仕事させられる国になってきたことが遠因にあるような気がしてます。(日本ではブラジル=サッカー、ボサノヴァ、サンバという旧態依然のイメージが強すぎるんでしょうね。音楽面ではいまはMPBというすばらしい現代的ジャンルが発達してきているので、こいつを聞かなきゃ。でもグローバル経済に支配される世界においては、売れると分かっていないとモノも情報も入ってこないから、外で何が発達していてもさっぱり分からない。これがとくに日本国にとって敗因となります)
それで、優勝はグローバル経済、EU支部の――唯一の――優等生ドイツ、ということで・・・
サッカーが真に民衆的なものであった時代は去っていくんでしょうかね。
それを見越しているからこそ、FIFAはワールドカップをロシア、そしてカタールに持っていくわけなんだな・・・
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
つまり
集団的自衛権だ、日米安保条約だと言う前に、日本が関係するあらゆる戦争を未然に防ぐためのあらゆる思索、工夫、算段をすること。
そしてできるなら世界全域において戦争がなくなるように思想的、実際的な努力をすること。
これだと思います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
集団的自衛権
・・・前にも書いたような気がしますが、わたしとしては憲法9条の精神は、湾岸戦争のときに何も言わずに莫大な戦費を他国軍のために出した時点で、ほぼ死んでしまっていたと思うのです。
経済大国とかの地位は捨てても、あるいはさらに経済的に追い詰められて日本国民が飢えに苛まれることになっても、戦争遂行を助ける行為はしない、というのが憲法の精神だったと思うからです。
ただ、これからこの精神から残ったものを生かすこと、生かし直すことは、不可能ではないと思います。というか、不可能だと投げやりになってはいけないと思います。世界の現状を真摯に見、学び、世界全体を平和に導くことに貢献すべきだと思うのです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ブログお休み中ですがシンポジウムのご案内です
(ブログお休み中ですが、わたくしがお話をしますシンポジウムのご案内を転載させていただきます。このシンポは入場無料ですが事前申込が必要ですので一番下をご覧ください)
平成25年度 日アラブ文化対話シンポジウム
「北アフリカと日本の21世紀-国際文化交流が築く平和な共生社会」
日時:2013年11月20日 15:00~19:00
場所:明治大学リバティーホール(明治大学駿河台キャンパス)
主催:国際交流基金、明治大学
近年、北アフリカを初めとするアラブ諸国の政治状況は急速に変化し、様々な形で社会に影響を与えています。それらは報道を通じて日々日本にも伝えられていますが、その情報の多くは政治や経済に関することであり、一般市民が何を感じているのか、また日本に対してどのように考えているのか、といった生の声は聞こえづらいのではないでしょうか。本シンポジウムでは、北アフリカと日本において、多面的な相互理解や共感を生み出すために、これからの文化交流・民間交流が果たし得る役割について語り合います。
15:00 – 15:05 開会の挨拶
15:05 – 15:25 基調講演:イナメナス人質事件から考える―国際文化交流が築く平和な共生社会(仮題)
15:25 – 16:55 セッション1:日本での北アフリカの存在とその映り方を再考する
17:15 – 18:55 セッション2:北アフリカで日本の文化や価値観をより良く知ってもらうために
18:55 – 19:00 閉会の挨拶
登壇者
○基調講演・セッション1パネリスト
勝俣誠(明治学院大学国際学部教授、明治学院大学国際平和研究所所長)
○セッション1モデレーター
福田邦夫(明治大学商学部教授、明治大学軍縮平和研究所所長)
○セッション2モデレーター
鷹木恵子(桜美林大学人文学系教授)
○セッション1パネリスト
モハメド・アイト・ラシュゲール(モロッコ/SNRT公共テレビ放送チーフ編集者)
アブドルバーシト・ムハンマド・ベンギース(リビア/国営リビア通信LANA国際報道部所属記者)
ターレク・シェヒディ(チュニジア/アフリカ開発銀行コーディネーター)
○セッション2パネリスト
布施広(毎日新聞論説室専門編集委員、季刊『アラブ』編集長)
粕谷雄一(金沢大学国際学類ヨーロッパコース教授)
ヌラ・コルト(チュニジア/ラジオ・チュニス国際ラジオ放送局)
スマイル・デベシュ(アルジェリア/アルジェリア第三大学教授)
★メールにて事前にお申し込みください。
メールタイトルに、「北アフリカ国際シンポジウム」と明記し、本文に氏名・ご所属・連絡先を記載の上、下記アドレスにお送りください。
north_africa_symposiumアットマークhotmail.com
(宛先は明治大学内の本シンポジウム事務局のメールアドレスです。個人情報については、本シンポジウムの受付以外には利用しません)
平成25年度 日アラブ文化対話シンポジウム
「北アフリカと日本の21世紀-国際文化交流が築く平和な共生社会」
日時:2013年11月20日 15:00~19:00
場所:明治大学リバティーホール(明治大学駿河台キャンパス)
主催:国際交流基金、明治大学
近年、北アフリカを初めとするアラブ諸国の政治状況は急速に変化し、様々な形で社会に影響を与えています。それらは報道を通じて日々日本にも伝えられていますが、その情報の多くは政治や経済に関することであり、一般市民が何を感じているのか、また日本に対してどのように考えているのか、といった生の声は聞こえづらいのではないでしょうか。本シンポジウムでは、北アフリカと日本において、多面的な相互理解や共感を生み出すために、これからの文化交流・民間交流が果たし得る役割について語り合います。
15:00 – 15:05 開会の挨拶
15:05 – 15:25 基調講演:イナメナス人質事件から考える―国際文化交流が築く平和な共生社会(仮題)
15:25 – 16:55 セッション1:日本での北アフリカの存在とその映り方を再考する
17:15 – 18:55 セッション2:北アフリカで日本の文化や価値観をより良く知ってもらうために
18:55 – 19:00 閉会の挨拶
登壇者
○基調講演・セッション1パネリスト
勝俣誠(明治学院大学国際学部教授、明治学院大学国際平和研究所所長)
○セッション1モデレーター
福田邦夫(明治大学商学部教授、明治大学軍縮平和研究所所長)
○セッション2モデレーター
鷹木恵子(桜美林大学人文学系教授)
○セッション1パネリスト
モハメド・アイト・ラシュゲール(モロッコ/SNRT公共テレビ放送チーフ編集者)
アブドルバーシト・ムハンマド・ベンギース(リビア/国営リビア通信LANA国際報道部所属記者)
ターレク・シェヒディ(チュニジア/アフリカ開発銀行コーディネーター)
○セッション2パネリスト
布施広(毎日新聞論説室専門編集委員、季刊『アラブ』編集長)
粕谷雄一(金沢大学国際学類ヨーロッパコース教授)
ヌラ・コルト(チュニジア/ラジオ・チュニス国際ラジオ放送局)
スマイル・デベシュ(アルジェリア/アルジェリア第三大学教授)
★メールにて事前にお申し込みください。
メールタイトルに、「北アフリカ国際シンポジウム」と明記し、本文に氏名・ご所属・連絡先を記載の上、下記アドレスにお送りください。
north_africa_symposiumアットマークhotmail.com
(宛先は明治大学内の本シンポジウム事務局のメールアドレスです。個人情報については、本シンポジウムの受付以外には利用しません)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
しばらくお休みします
フランスも韓国もお話はあるのですが、時間もほとんどないし、ブログを書く気にもなれません。
いたわるべき人がいます。
しばらくお休みにさせていただきます。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
東駅

今回のフランスでは、なんだかこの国も小奇麗路線を取ったように思えて、あんまり印象よくなかったです。
これはパリ東駅Gare de l'Est。駅の中にブティックの塊りみたいなのができてますね。
ドイツは環境大国で、きれいな国ドイツにいらはいいらはい、という感じですが、フランスもモード、ファッションできれいな国フランスにいらはいいらはい、をやってるんですな。
わたし、こういうの嫌い。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ブログお休み中ですが・・・
ランスReimsの大聖堂が炎上したのは99年前の今日、9月19日であったという記憶を皆様に喚起したいと思います。
今回の渡仏は全く仕事のためなのですが、なぜか国民的象徴の破壊、ということを考えさせる滞在になりました。
それでは25日以降、また。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
Et ecce stella ! SUKIYAKI 2013

すべてが終わり、片付けに入ったスキヤキ2013。
空を見上げると、ちょうど天頂に星が。
(星に詳しい方、日本時間2013年8月25日19時15分、富山県南砺市付近で天頂 --- zenith < semt ---にみえた星はなんという星か、教えてください)
iPhoneでその星を撮りましたが、さすがにこれは写真では見えないだろうな・・・ と思ったら、ぼやーっと、なんとなくそれらしいのが写ってますよ? みなさんは見えますか?
・・・これらのできごとは、なにかひとつながりをなしていて、なにかをわたし(たち)に示唆しているような予感を与えてくれました。
人生とは、また人の歴史とは、そういうものかも(と、自分でも何を言ってるのかわかりませんが。アンドレ・ブルトンを愛読していると言っておられた笹久保伸さんはわかってくださるかな?)。
コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )
メール
メールというのは、ある意味、コミュニケーションを拒否するためのコミュニケーション手段という、矛盾した性格をもっていることを最近痛感します。
でも、われわれはすでにメール社会にどっぷり浸かり、これなしではあらゆる活動が破綻をきたしてしまう時代を生きています。
終末感に酔いしれる --- だけ --- というのはスタンダリアンのやることではないので、なにか打開策を考え、具体化しようと思います。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |