日本人はフランス語を誤解している!・・・と思うけどなあ・・・
フランス語系人のBO-YA-KI
今日は学生さんとお話ししました。
和むことができたのは、わたしの方でした。
学生さんの方も心を和ませられていることを祈ります。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
留学
留学はけっして遊びではないですよ。学生さんの個人的嗜好は当然あっていいですが、それ以上の、社会に対して胸をはれる「大義名分」があります。(大義名分というと、やっぱりなんだか言葉の上だけのような雰囲気が漂いますね。日本語って、困ったな)
世界の多くの人と個人的につながりをもつこと。
現在の日本や世界が依って立っている原理、原則、大事なことがどのようにして生まれ、育ってきたか、その歴史を知り、活かし方を探ること。それが生まれてきた土地で、これから活かされるべき土地で。
留学しようかしまいか真摯に悩む人に申しますが、わたしは、そういう形で自分の心にしわ寄せすることはないと思います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
要するに
大学の制度がどうのというより、現在から未来への展望をもった授業をやっていないといけないということではないんでしょうか。
日本の大学が世界に伍するためには。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
やっぱ
日本の人がアラブの人をよく理解しないようにしておく、というのは、やっぱ、アメリカの意向なのかなと、最近つくづく思います。
やれやれ・・・
当の朝日新聞にこんな記事も前、出てましたね。
朝日新聞 3月16日
アルジェリア事件でイスラム本の出版中止 日経新聞出版
[PR]
【北林晃治】「イスラムの人々はなぜ日本が好きなのか」と題し日本経済新聞出版社から刊行予定だった新書が、アルジェリア人質事件の後で読者の理解が得られないとする同社の判断で出版中止になっていたことが15日、分かった。
著者は現代イスラム研究センターの宮田律(おさむ)理事長(57)。自身のソーシャルメディア・フェイスブックで明らかにした。
新書は、日本人の礼儀正しさや道徳観がイスラム社会で高く評価されている理由をイスラム教の教義や歴史的背景から分析した内容。宮田さんによると、出版社側からの提案で昨年9月に出版契約を結び、12月には脱稿した。今年1月には装丁の見本もでき、2月上旬の「日経プレミアシリーズ」からの刊行に向けた最終段階だった。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
今日の新聞(3) さーて日仏時代かなあ

オランドさんが日本にやってきて「日仏は共通の課題に直面している」「日仏の特別なパートナーシップは欧州やアジアにとってだけではなく、世界にも有益だ」なんてことを言って行ったらしいですね。
そうかもしれません。
はっきり言って、1870年から2000年ころまで、勃興するドイツをなんとか抑えようと四苦八苦したフランスの経験は、中国という超弩級パワーをなんとかなだめすかし、周りの世界に与えるネガティブな影響を最小限にとどめてソフトランディングしてもらう任務を矢面にたって引き受けなければならない日本にとって、他山の石くらいにはなるはずですから。
ただ原子力に関することでのパートナーシップの強化は、どうかなあと思ってます。昨日授業していて気づいたんですが、キュリー夫妻の発見を原点とする原子力産業は、フランスにとっては「自分のもの」、国家的プライドの源泉という感じがするんでしょうね。ちょうどリュミエール兄弟の生んだ「映画」が「自分のもの」だという感覚を明らかにフランス人が持っているように。
「発展」を支配的概念としてもっている(これはニーチェの考え)はずのドイツ人の国が、現在原子力の領域における発展を自ら止めてしまう態勢でいるのは、歴史の皮肉なんでしょうか。
原子力についてのわたくしの考えはここで述べた通り、廃棄物の問題が解決しない限り、絶対知というようなことを口にすべきではないので、「発展」ということは捨てるか、あるいは概念を練り直さないといけないと思う、ということになります。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
今日の新聞(2) 書評欄。
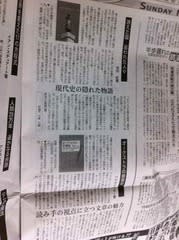
『消えた国 追われた人々』。池内紀氏の新著。
わたし的には、日本のドイツ文学研究者はこのひとだけ、みたいな感じになってしまってます。
ドイツの傷は大きいのです。しかも評者の川本三郎氏が「加害国のドイツにも国を失う悲劇があったのかと現代史の複雑さを教えられる」なんて、いまさら何を言うのかってほどのんきなことを書いているくらいで、その傷は見えにくいところがある。ドイツ人自らその傷を言い立てられないし、しっかり見つめることさえ難しい。思想的にも非常に難しい位置にある。
その難しさをしっかり見ていく池内氏は「ヨーロッパの辺境をこれほど旅した人は少ない」という人であるわけです。
ただその難しい位置にあるドイツ語の教育をモデルにして日本の第二外国語教育全体をデザインするのは、これはやめておいたほうがいい。少なくとも相対化したほうがいい。
そうした方が、結局はドイツ語教育のためにもなると思うのです。
これがわたしの主張です。
パウル・ベッカー著『オーケストラの音楽史』。
「オーケストラという表現媒体の歴史的な終わりを告げるシェーンベルクやストラヴィンスキーの記述で終わっているが・・・」
「オーケストラに代表される西洋古典芸術音楽がいよいよ最後の時期を迎え始め、さまざまな延命策が講じられ始めた今日、・・・」
西洋古典音楽、オーケストラというものについてのわたくしの意見はたとえばこれとかさらにこれとかに書いてましたが・・・
いまでは――これはわたしのオリジナルな考えではないんですが、どこで読んだかな――いま世界に行き渡っている「ポピュラー音楽」が基盤をおいているのは、まぎれもなくこの西洋古典音楽の培った「音楽理論」だということを常に念頭におかなければならない、と考えています。
世界の諸音楽伝統は、そのままでは他の文化地域に伝播するのが困難――つまり珍しい音楽とはみてもらえても、本当に楽しめる音楽とは思ってもらえない――ですが、西洋古典音楽理論という共通コード――ちょうど言語で言う英語みたいな事実上のlingua franca――に乗せれば、たとえばアルジェリアの音楽が日本のリスナーが「ほんとうにたのしむ」ことのできる音楽になりうるのです。
これは昨日の「文化資源学概論」でわたしが、半数以上留学生である受講生に向かって論じたことでもあります。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
アフリカが自力で問題解決できるために Vers une Afrique autonome
Jeune Afriqueが報ずるところではアフリカ連合の議長であるエチオピアの首相ハイレマリアム・デサレン Hailemariam Desalegnが27日、アフリカ大陸の紛争を迅速に解決するための自前の「緊急部隊」force d'intervention rapideの創設を宣言したそうです。"Force africaine en attente "(アフリカ待機軍?)の創設は10年前から懸案となりながら難航しているので、とりあえず、ということでしょう。
アフリカの紛争「解決」のためによその大国がしゃしゃり出てくる時代はそろそろ終わりにするぞ、ということですね。
歴史的ですね。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
かなだはなかなか、かな? 4

モンクトン大学の購買部みたいなところには、よく見るとPensees Positives「肯定的な思考」とラベルの貼られた棚がたくさんありました。これは特定のムーヴメントに結びついているのでしょうね。
たしかにこの大学にはSCIENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 健康諸科学と共同体サービス学部というのがありますが、他の学部関係の本はそんなに置いてないんですから・・・
これらの本は、学生さんたち自身の生活のためのもの、生活用具なのでしょう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
大げさなはなし une grande histoire a big story
たぶん日本の人は有史以来経験したことのない局面にいるのだと思います。
Sans doute les Japonais sont dans une phase qu'ils n'ont jamais connue.
Perhaps Japanese are in the phase unknown in all their history.
19世紀後半から20世紀の終わりまで、日本の人は基本的に、観念的に、精神的に上のものを志向していて、その「上のもの」というのはヨーロッパ起源のものであって、その「上志向」は基本的に「自己否定」だったと思います。
やむをえなかったとはいえ傲慢な話ですが、ヨーロッパ(アメリカ合衆国がどういう位置にあるかちょっと考えますが)と対峙しているのは「日本」であって、世界の他の地域(アジア、アラブ、アフリカ・・・ 中国がどういう位置にあるかちょっと考えますが)は視野に入っていなかったです。
日本の始まりから19世紀まで「文明」は中国から来るものだったのが、19世紀後半から20世紀終わりまではそういうことになりました。
でもヨーロッパ自身が予言したとおり(ヴァレリーとかフーコーとか)「精神」は拡散し、「人間」は死につつあります。ヨーロッパの優位が完全消滅するとまでは言わないまでも(たとえば「世界標準」を押さえる力を保持し続けるなど。CEFRはそのひとつ)、確実にその存在は相対化されてきました。
韓国が来て、中国が来て、インドが来て、BRICSやVISTAが来て、アラブが、アフリカが世界の前面に出て来ようとするとき、彼らはそれぞれのやり方で自己「肯定」を掲げてきます。日本よりはるかに「自己否定させられた」地点からの出発ではありますが。そして「世界標準」に随時、適当に、あわせながらの「進歩、発展」ではありますが。
その世界のなかで日本の人は世界を舞台に、韓国の人や中国の人たちをライバルとして渡り合わなければならないわけですが・・・そんなノウハウ、年をとった世代の日本の人、とくに旧来タイプのインテリが、もっているわけがない。二千年来もってなかったんですから。
でも日本は、海外旅行ブームという大航海時代を経験したし、「ゆとり世代」以降は旧来の、無効になった思想も希薄にしか持っていないわけで、まだまだのぞみはあるはずだし、またなければならないと思います・・・
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
かなだはなかなか、かな? 3
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |





