前回のエントリーで書いたソニーの話で、文字数の関係でテレビ製造部門のことに触れられなかったので今回はそのあたりを書いておきます。ただしこの問題は対アップルのケースと違い、ソニーの限った話ではなく同様にテレビ製造で苦しみ今期大きな赤字を計上する見通しとなったパナソニック、シャープを含め、日本の家電業界共通の問題でもありますので、そんな観点から書いたものであるとの理解の下お読みいただければと思います。
日本のテレビ製造はどこで道を誤ってしまったのか、この問題はよく韓国のサムソンとの比較の問題で語られています。サムスンの転機は97年の韓国通貨危機でした。これにより企業の存続すら危ぶまれるほどの危機に直面した同社は、開発および国際化のあり方を根本から見直したと言います。それまでは技術で最先端を行く日本に追随しいかに追いつき追いぬくかに使命感を持って取り組んでいた同社が、最先端技術の開発競争を降り同時に日本とは異なる国際化を進展させました。
日本は、相変わらず最先端技術開発で世界をリードできるという過去の幻想の下に、安価な労働力を求めて製造のみの国際化に軸を据えていきます。片やサムスンは、最先端技術は日本の後追いに甘んじつつも、新興国に製造部門だけではないマーケティング+R&D部門を置くことでそれぞれの地域をマーケットとしてとらえ、日本の後追い技術をそれぞれの地域の嗜好にカスタマイズする「リバース設計」により安価な商品を投入することで新興国でのシェアを伸ばすというやり方に転じた訳です。
さらにこの背景にあった家電デジタル化の進展は、製造原価に占める人件費率をアナログ時代に比べ大きく下げることにつながり、日本の敗北は決定的になります。世界的にみれば必要とはされないかもしれない最先端技術の開発に多くのコストをかけ、製造原価における人件費削減目的でより人件費の安い新興国を求めて製造拠点を増やす。その繰り返しをしている間に、サムスンは世界中の新興国に工場としてではなく企業として進出することでマーケットニーズを把握し、その国仕様の先端技術とは無縁の安価な製品でマーケットシェアを伸ばす…。気がついた時にはすでに勝負はついていました。
(この辺の話は他の家電商品にも相通じるもので、例えば洗濯機は日本では今や一槽ドラム式以外はお目にかかりませんが、新興国では今も二槽式が主流で利用者も高価な日本製の一槽式は求めていないとの話も耳にします)
大幅な赤字を抱えた我が国のテレビ製造業界にとって、今さら一に立ち返ってサムスンのような新興国戦略への転換をはかるような悠長なやり方はあり得ないでしょう。技術という力を誇示し、経済的弱者の新興国を製造工場として自らの“エサ”にしてきた様は、まるで進化の原則である環境への順応をせずに滅びた恐竜のようでもあります。サムスンは、一度ひん死の危機に直面したことによって、環境への順応の大切さを知りました。力を誇示する先端技術競争から一歩引き、日本の先端技術を各新興諸国のニーズにあわせた「リバース設計」に専心することで環境順応を果たし、見事に“進化”をとげ生き延びたわけです。なるほど、もはや日本のテレビ製造は恐竜と同じく滅びる以外に道はないのではないかと思えます。
今朝の日経新聞におもしろい記事が掲載されています。日産自動車が利益で業界首位に立ったと。掲載記事をよく読むと、その理由は「開発の現地化」があると書かれています。「技術者2万人のうち外国人が3割。市場ごとに消費者のニーズをくみ上げ開発にいかす」ことで、中国、ロシア、ブラジルなどでの販売実績が軒並み大幅に増加したと。まさにサムスンと同じ「進化戦略」がそこに見てとれます。
過去に最先端技術を誇り世界に大きく飛び出した日本のモノづくりですが、ここに来て行き過ぎた最先端技術は必ずしも世界的には必要とされないという状況を生み出しています。家電のみならずあらゆる業界で、環境順応という進化の道を歩めるか過去に隆盛を誇っただけの恐竜として滅びてゆくか、日本のモノづくりは今大きな分岐点に差しかかっているように思います。
日本のテレビ製造はどこで道を誤ってしまったのか、この問題はよく韓国のサムソンとの比較の問題で語られています。サムスンの転機は97年の韓国通貨危機でした。これにより企業の存続すら危ぶまれるほどの危機に直面した同社は、開発および国際化のあり方を根本から見直したと言います。それまでは技術で最先端を行く日本に追随しいかに追いつき追いぬくかに使命感を持って取り組んでいた同社が、最先端技術の開発競争を降り同時に日本とは異なる国際化を進展させました。
日本は、相変わらず最先端技術開発で世界をリードできるという過去の幻想の下に、安価な労働力を求めて製造のみの国際化に軸を据えていきます。片やサムスンは、最先端技術は日本の後追いに甘んじつつも、新興国に製造部門だけではないマーケティング+R&D部門を置くことでそれぞれの地域をマーケットとしてとらえ、日本の後追い技術をそれぞれの地域の嗜好にカスタマイズする「リバース設計」により安価な商品を投入することで新興国でのシェアを伸ばすというやり方に転じた訳です。
さらにこの背景にあった家電デジタル化の進展は、製造原価に占める人件費率をアナログ時代に比べ大きく下げることにつながり、日本の敗北は決定的になります。世界的にみれば必要とはされないかもしれない最先端技術の開発に多くのコストをかけ、製造原価における人件費削減目的でより人件費の安い新興国を求めて製造拠点を増やす。その繰り返しをしている間に、サムスンは世界中の新興国に工場としてではなく企業として進出することでマーケットニーズを把握し、その国仕様の先端技術とは無縁の安価な製品でマーケットシェアを伸ばす…。気がついた時にはすでに勝負はついていました。
(この辺の話は他の家電商品にも相通じるもので、例えば洗濯機は日本では今や一槽ドラム式以外はお目にかかりませんが、新興国では今も二槽式が主流で利用者も高価な日本製の一槽式は求めていないとの話も耳にします)
大幅な赤字を抱えた我が国のテレビ製造業界にとって、今さら一に立ち返ってサムスンのような新興国戦略への転換をはかるような悠長なやり方はあり得ないでしょう。技術という力を誇示し、経済的弱者の新興国を製造工場として自らの“エサ”にしてきた様は、まるで進化の原則である環境への順応をせずに滅びた恐竜のようでもあります。サムスンは、一度ひん死の危機に直面したことによって、環境への順応の大切さを知りました。力を誇示する先端技術競争から一歩引き、日本の先端技術を各新興諸国のニーズにあわせた「リバース設計」に専心することで環境順応を果たし、見事に“進化”をとげ生き延びたわけです。なるほど、もはや日本のテレビ製造は恐竜と同じく滅びる以外に道はないのではないかと思えます。
今朝の日経新聞におもしろい記事が掲載されています。日産自動車が利益で業界首位に立ったと。掲載記事をよく読むと、その理由は「開発の現地化」があると書かれています。「技術者2万人のうち外国人が3割。市場ごとに消費者のニーズをくみ上げ開発にいかす」ことで、中国、ロシア、ブラジルなどでの販売実績が軒並み大幅に増加したと。まさにサムスンと同じ「進化戦略」がそこに見てとれます。
過去に最先端技術を誇り世界に大きく飛び出した日本のモノづくりですが、ここに来て行き過ぎた最先端技術は必ずしも世界的には必要とされないという状況を生み出しています。家電のみならずあらゆる業界で、環境順応という進化の道を歩めるか過去に隆盛を誇っただけの恐竜として滅びてゆくか、日本のモノづくりは今大きな分岐点に差しかかっているように思います。











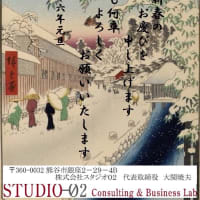
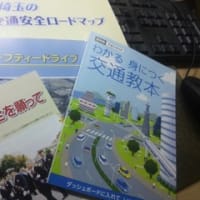
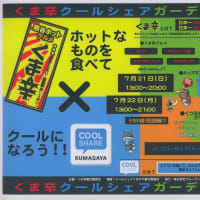
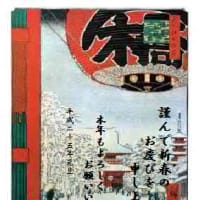


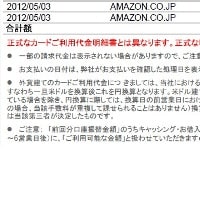

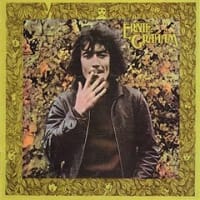
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます