
プロジェクトや会議の運営を成功に導く「戦略シナリオ」についてです。
社内で新たなプロジェクトや会議を発足させる場合、社長が発案して任せきりになるケースがよく見受けられます。社長の「○○を検討しろ!」「××を考えるチームを発足させろ!」といったケースです。こんな場合、決まってチームや会議が途中でとん挫したり、袋小路に入ったり、その頃には社長の熱も冷めてうやむやに…。
まず、新設のチームや会議にはまず「目的」「目標」「課題」の共有が不可欠です。「目的」「目標」「課題」のことを、私は「プロジェクトの3要素」と呼んでいます。共有の仕方ですが、「目的」はとりあえず指示者である社長が提示する必要があるでしょうが(もちろん与えられた「目標」をメンバー間で議論して修正を加えることは可です)、「目標」「課題」はチームや会議のメンバーが話し合って決めるのがベストでしょう。
では、「目的」「目標」「課題」って何でしょう?
「目的」の明確化とは、「何のためのチーム、会議であるか」をハッキリさせることです。例えば「社内の無駄を削減するためのチーム」「顧客満足度を高めるためのチーム」「原価計算を正確にするためのチーム」等々、チームとして与えるミッションが必ずあるはずで、これをしっかりと伝えメンバー全員に認識をさせることが必要です。言いかえれば、「何をしたいか」「どういう状態にしたいか」を「目的」として、具体的に指し示すことです。「目的」のないところにマネジメントは存在しません。
「目的」の共有ができたら次は「目標」です。「目標」の「標」は“しるし”と言う意味です。すなわち、何をもって当面「目的」を達することができたとするかの具体的な“目印”のことです。この“目印”は抽象的ではいけません。「目標」の見える化です。具体的な数字を“目印”にすることが大切なのです。「目標」にも必要な3構成要素があります。「何の指標を」「いつまでに」「どこまで達成するか」です。例えば、「経費率を」「今年度末までに」「5%下げる」といった感じです。この3要素のどれかひとつでも、あやふやであるとプロジェクトや会議はいい加減なものになってしまします。
同時に「目標」の設定の仕方次第で、チームの取り組み姿勢が大きく変わってくるわけで、「目標」の設定は大変重要です。社長の意向で強く理想を追いかけすぎて「目標」が実現の実感がもてなければ、チームの活力が失われるでしょうし、逆にチームに任せすぎて容易に達成できる「目標」になりすぎてもチームを組む意味がなくなります。その意味では「目的」を提示した指導者の責任として、社長が適正な「目標」であるか否かのか判断を下すことは忘れてはいけない重要なポイントであるのです。
「課題」は「目標」を達成するために解決すべき問題に対する“策”のことです。ここで間違えていけないのは、「課題」=「問題点」ではなく「問題」を解決するための「策」であるということです。ですから、組織内にある「問題」を列挙するのではなくあくまで「目標」を達成するための「問題」を抽出して、その「策」を講じることが肝要です。重要なことは、解決すべき「問題」はネガティブでもその対策である「課題」はポジティブなものであるという点を誤らず共有させることです。
明確な「目的」の下、それを実現するための「目標」を数値で表すことで努力の度合いに関する認識を共有させ、さらにそれを実現するための「課題」を明らかにしていく。このようにしてつくられるものが、まさに「戦略シナリオ」に他ならないのです。迷路に入ったプロジェクト、形式に流されている会議等は、たいていこの「戦略シナリオ」を見失っているのです。既存のチームや会議において、「混迷」「停滞」「マンネリ」等を感じたら、まずは「目的」「目標」「課題」の再確認をおすすめします。
社内で新たなプロジェクトや会議を発足させる場合、社長が発案して任せきりになるケースがよく見受けられます。社長の「○○を検討しろ!」「××を考えるチームを発足させろ!」といったケースです。こんな場合、決まってチームや会議が途中でとん挫したり、袋小路に入ったり、その頃には社長の熱も冷めてうやむやに…。
まず、新設のチームや会議にはまず「目的」「目標」「課題」の共有が不可欠です。「目的」「目標」「課題」のことを、私は「プロジェクトの3要素」と呼んでいます。共有の仕方ですが、「目的」はとりあえず指示者である社長が提示する必要があるでしょうが(もちろん与えられた「目標」をメンバー間で議論して修正を加えることは可です)、「目標」「課題」はチームや会議のメンバーが話し合って決めるのがベストでしょう。
では、「目的」「目標」「課題」って何でしょう?
「目的」の明確化とは、「何のためのチーム、会議であるか」をハッキリさせることです。例えば「社内の無駄を削減するためのチーム」「顧客満足度を高めるためのチーム」「原価計算を正確にするためのチーム」等々、チームとして与えるミッションが必ずあるはずで、これをしっかりと伝えメンバー全員に認識をさせることが必要です。言いかえれば、「何をしたいか」「どういう状態にしたいか」を「目的」として、具体的に指し示すことです。「目的」のないところにマネジメントは存在しません。
「目的」の共有ができたら次は「目標」です。「目標」の「標」は“しるし”と言う意味です。すなわち、何をもって当面「目的」を達することができたとするかの具体的な“目印”のことです。この“目印”は抽象的ではいけません。「目標」の見える化です。具体的な数字を“目印”にすることが大切なのです。「目標」にも必要な3構成要素があります。「何の指標を」「いつまでに」「どこまで達成するか」です。例えば、「経費率を」「今年度末までに」「5%下げる」といった感じです。この3要素のどれかひとつでも、あやふやであるとプロジェクトや会議はいい加減なものになってしまします。
同時に「目標」の設定の仕方次第で、チームの取り組み姿勢が大きく変わってくるわけで、「目標」の設定は大変重要です。社長の意向で強く理想を追いかけすぎて「目標」が実現の実感がもてなければ、チームの活力が失われるでしょうし、逆にチームに任せすぎて容易に達成できる「目標」になりすぎてもチームを組む意味がなくなります。その意味では「目的」を提示した指導者の責任として、社長が適正な「目標」であるか否かのか判断を下すことは忘れてはいけない重要なポイントであるのです。
「課題」は「目標」を達成するために解決すべき問題に対する“策”のことです。ここで間違えていけないのは、「課題」=「問題点」ではなく「問題」を解決するための「策」であるということです。ですから、組織内にある「問題」を列挙するのではなくあくまで「目標」を達成するための「問題」を抽出して、その「策」を講じることが肝要です。重要なことは、解決すべき「問題」はネガティブでもその対策である「課題」はポジティブなものであるという点を誤らず共有させることです。
明確な「目的」の下、それを実現するための「目標」を数値で表すことで努力の度合いに関する認識を共有させ、さらにそれを実現するための「課題」を明らかにしていく。このようにしてつくられるものが、まさに「戦略シナリオ」に他ならないのです。迷路に入ったプロジェクト、形式に流されている会議等は、たいていこの「戦略シナリオ」を見失っているのです。既存のチームや会議において、「混迷」「停滞」「マンネリ」等を感じたら、まずは「目的」「目標」「課題」の再確認をおすすめします。











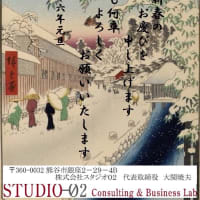
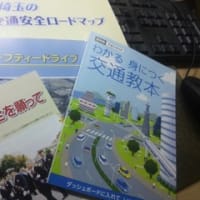
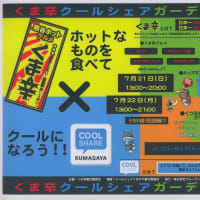
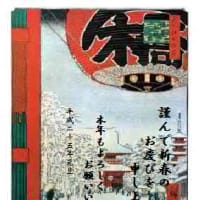


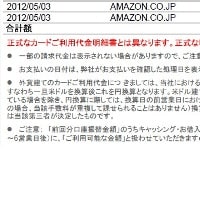

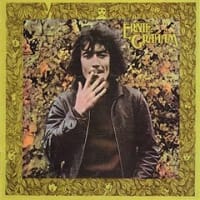
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます