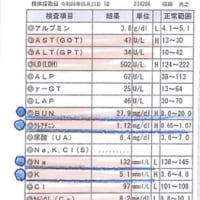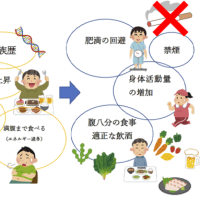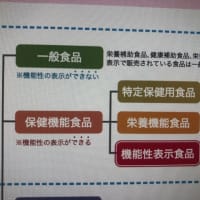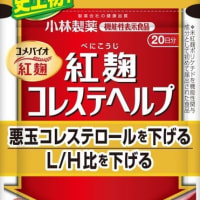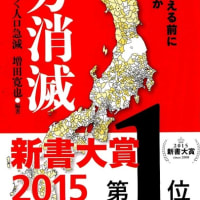昼夜を問わず治療にあたる勤務医は、長時間労働が常態化している。
心身ともに疲弊して勤務医を辞める人もおり、さらなる医師不足を招く悪循環が生じていた。
勤務医の過酷な長時間労働によって医療体制が維持されている現状は、健全とは言えない。各医療機関が働き方改革に取り組むとともに、国は医療の維持のための対策を強化すべきである。
その際に患者の受診行動の是正を伴わなければ実効性は確保できない。
2019年に施行された働き方改革関連法では、医師については影響が大きいとして、実施を5年間先送りしていた。それだけ国は医師の労働について「使命感」に頼って低い評価で長い間労働を搾取し続けてきた。
(1)医師の労働搾取の実態 無給のインターン制
例えば、私が医師になる直前までは大学医学部・医科大学・医学専門学校を卒表した医師の卵には1年間の無給のインターン制度があった。
1945年(昭和20年)にGHQの指導で、卒業生にインターン教育と医師国家試験が義務となった。
インターン教育では医師資格を有しないインターン生が医療行為を行った。医療事故の責任所在も明確ではなかった。1967年(昭和42年)に東大医学部のインターン生らが「医師国家試験ボイコット運動」を起し、それが東大紛争に発展したこともあって社会に注目され、1968年(昭和43年)に「インターン制度」は廃止された。
国は20年以上も無給の制度を続けてきた。
これによって、卒後すぐに国家試験を受け合格者には医師免許が授与されることになった。
(2)低賃金医という身分
インターン制の廃止によって「寄る辺なき無資格医」の立場はなくなったが、大学病院や大規模病院には「無給医・低賃金医」という勤務形態があった。
私は1973年(昭和48年)から秋田大学内科に所属したが、その時の身分は1日ごとに資格が更新される日雇医師であった。休日や勤務時間などあっても無きに等しい状況でほぼ24時間拘束状態で、当時の給与は4-5万円程度。
週末は秋田県内の病院を点々としながら生活費を稼いでいた。
(2)無給医という身分
「無給医」とは、無給で働く医者のこと。種々の理由で給料を一切もらわずに労働している医師が存在した。ほとんどは医師になって3~10年目くらいの若手医師であった。医師は超長時間労働さえ覚悟すればアルバイトで生計を立てられる道があったからそう深刻ではなかった。この時期を耐えれば教授からいい就職先を紹介してもらえることも期待できたからである。
私は純然たる「無給医」の経験はないが「低賃金医」を3年近く経験した。