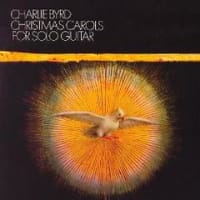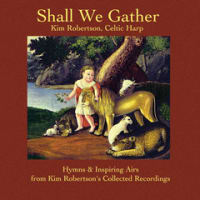”I WILL NOT STAND ALONE”by KAYHAN KALHOR
とりあえずワールド・ミュージックのファンをやっているのだが、各国の民俗音楽とか古典音楽とかには、あまリ興味は持てないのだった。時間の流れから隔離されて博物館に陳列されているような音楽を退屈こらえて聴いているよりも、各国の生きのよい流行り歌、港々の歌謡曲に、同時代を生きるものとして共鳴したい。
この盤はイランの民族楽器、カマンチェの奏者による古典音楽ということで、まあ、いつもの私ならスルーする筈の物件なのだが。これが不覚にも、というのも変だが、試しに聞いてみたら一発で引き込まれ、ついにはCDを手に入れてなんども聞き返す羽目となったのだった。
カマンチェというのは、床に対して垂直に立て、弓弾きする胡弓タイプの撥弦楽器であり、今回は特に倍音成分の多い豊かな音色が出るように調整された特別な楽器を使っているという。伴奏には、チター系、と言えばいいのだろうか、これも従来のものより弦の数を増やし、低音域を充実させたものが使われている。
この二つの楽器が濃密に絡み合う演奏を聴かせて行くのだが、なにやら深く静かな悲しみの感情の表出に、それこそ同時代的に共感してしまった私なのだった。
二つの楽器の対話メインで構成されている演奏だから、当然、音の隙間の多い演奏となるのだが、その隙間にビロードの手触りの夜が存在している。
二つの楽器とその奏者たちを囲んでシンと静まり返り、どこまでも広がっている濃厚な夜の気配があり、その暗闇を探ろうと伸ばされる、音の触手がある。音は凛としたテンションを保ちつつ、殷々と啜り泣く。アルバムタイトルは、なにかの逆説であろうか。むしろ永遠に埋められるとこのない人間の普遍的な孤独への嘆きが、この盤一杯に敷き詰められているのだから。
全てはオリジナル曲、とはいえペルシャの古典音楽の形式にのっとって書かれたこの音楽が、全く同時代のものとして切実にこちらの胸に響くのは、なんとも不思議な気分。これはこの盤の主人公、カイハン・カルホールの資質によるものなのか、こちらが胸襟を開けば、本来古典音楽もこのように楽しめるものなのか。それはまだ、よくわからずにいる。