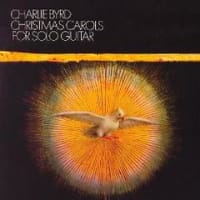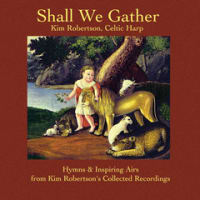”Diwan 2”by Rachid Taha
ラシッド・タハ。フランス在住のアルジェリア人であり、80年代中盤に北アフリカの伝統音楽とパンクを融合したアラブロックバンド「カルト・ド・セジュール」のリーダーとしてフランス在住の移民たちの代弁者的存在となった。
そんな経歴の持ち主なのだが、私はこの「カルト・ド・セジュール」のアルバムに関しては、どのような音だったのかまるで覚えていない。購入した記憶はあるのだから家のどこかにあるはずなのだが。
いつの頃からか、いわゆるワールドミュージックの文脈で語られる音楽のうち、”どこそこの伝統音楽”とパンクの、あるいはヒップホップの、あるいは云々かんぬんの、といった異種混合の素晴らしさを売り物とした作品にまるで心が動かなくなっていた私なのだった。
そのような”無理やり作り上げた歴史的大傑作”よりも、現地の人々が日常生活の中で空気を呼吸するようになにげなく愛しているような普通の音楽に惹かれるようになっていた私なのであって。そんな私はおそらく、カルト・ド・セジュールの”北アフリカの伝統音楽とパンクの融合”具合にもあまり馴染めず、聴くのを途中で放り出した、そんなところだったのではないか。
で、そんな彼の新譜を聴いてみる気紛れを起こしたのは、今回のこの作品は彼がルーツの地である北アフリカの音楽にストレートに挑んだものと聞いたから。それなら”普通の音楽派”の私にも馴染めるのではないかと考えたのである。
流れ出てきた音を、なぜかあのエンリコ・マシアスの”アラブ回帰作”と比べてしまっていた私だった。
あのマシアスのアラブ人なりきりぶりに比べると、タハのそれは、それほどストレートな”帰郷”とはいえないようだ。その独特のだみ声も”ロックのヒーロー”のそれであって北アフリカの体温は伝わらず、むしろ移民としての彼の故郷喪失者ぶりがクローズアップされている感がある。
彼なりの”北アフリカ風の音”を創造してみた音作りからも、ゆったりとくつろげるはずの故郷の土の上で、だが心からは馴染めずに、ここでも移民先のフランスにおける彼の立場と同じような”異邦人”であり続けるしかないタハ自身のとまどいを、どこかに感じられてならないのだ、私は。
余計な事をやって、不用意な姿を晒してしまったのではないかな、とか嫌味なコメントを書きかけたのだが、しかし、そうしてあらわになった彼の、”見せる予定はなかったナイーブな青年ぶり”の不思議な生々しさに、妙な親近感もまた、感じ取ってしまった私なのだった。
ラシッド・タハ。フランス在住のアルジェリア人であり、80年代中盤に北アフリカの伝統音楽とパンクを融合したアラブロックバンド「カルト・ド・セジュール」のリーダーとしてフランス在住の移民たちの代弁者的存在となった。
そんな経歴の持ち主なのだが、私はこの「カルト・ド・セジュール」のアルバムに関しては、どのような音だったのかまるで覚えていない。購入した記憶はあるのだから家のどこかにあるはずなのだが。
いつの頃からか、いわゆるワールドミュージックの文脈で語られる音楽のうち、”どこそこの伝統音楽”とパンクの、あるいはヒップホップの、あるいは云々かんぬんの、といった異種混合の素晴らしさを売り物とした作品にまるで心が動かなくなっていた私なのだった。
そのような”無理やり作り上げた歴史的大傑作”よりも、現地の人々が日常生活の中で空気を呼吸するようになにげなく愛しているような普通の音楽に惹かれるようになっていた私なのであって。そんな私はおそらく、カルト・ド・セジュールの”北アフリカの伝統音楽とパンクの融合”具合にもあまり馴染めず、聴くのを途中で放り出した、そんなところだったのではないか。
で、そんな彼の新譜を聴いてみる気紛れを起こしたのは、今回のこの作品は彼がルーツの地である北アフリカの音楽にストレートに挑んだものと聞いたから。それなら”普通の音楽派”の私にも馴染めるのではないかと考えたのである。
流れ出てきた音を、なぜかあのエンリコ・マシアスの”アラブ回帰作”と比べてしまっていた私だった。
あのマシアスのアラブ人なりきりぶりに比べると、タハのそれは、それほどストレートな”帰郷”とはいえないようだ。その独特のだみ声も”ロックのヒーロー”のそれであって北アフリカの体温は伝わらず、むしろ移民としての彼の故郷喪失者ぶりがクローズアップされている感がある。
彼なりの”北アフリカ風の音”を創造してみた音作りからも、ゆったりとくつろげるはずの故郷の土の上で、だが心からは馴染めずに、ここでも移民先のフランスにおける彼の立場と同じような”異邦人”であり続けるしかないタハ自身のとまどいを、どこかに感じられてならないのだ、私は。
余計な事をやって、不用意な姿を晒してしまったのではないかな、とか嫌味なコメントを書きかけたのだが、しかし、そうしてあらわになった彼の、”見せる予定はなかったナイーブな青年ぶり”の不思議な生々しさに、妙な親近感もまた、感じ取ってしまった私なのだった。