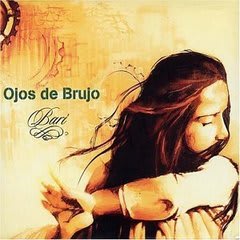” Computerwelt ”by Kraftwerk
車を運転するとき、たとえばパフュームなんかを聴きながらだったりするのだが、まあ、アイドル好きの当方、文句は言いたくないが「これのなにがテクノなのだ」と違和感を感じたりしている。パフュームってのサウンドって、テクノってことになってるわけでしょ?
でもねえ・・・あのサウンドは低音ドスドス重た過ぎるし、音は厚ぼった過ぎるしヘビメタめいた音圧強いギターが終始鳴り渡っていたりするのは、いかがなものか。あれ、ただのシンセを強調したハードロックでしょう。私の感性ではそういうことになる。
それでもカシユカは可愛かったりノッチは良い女だったりアーチャンのオッパイでかかったりするので、しょうがないから聴いちゃったりするんだけどさ。
テクノってのは、もっともっとオモチャみたいな薄っぺらで浅い音が粋なわけでしょう?安っぽいブリキのオモチャの楽しさ。重苦しい芸術なんかとは本来、縁のないものだ。
発祥以来、テクノの持っていた、そんなチープの美学を放逐したのは、言うまでもない、あのYMOの商業的成功だろう。そりゃ誰だってゼニは欲しい。その世界の古兵までもが、あれをやれば売れるのかってんで便乗を図り、そのサウンドを重苦しいYMO風に、実に軽薄な態度で変化させた。
降る雪やテクノも遠くなりにけり。などとつぶやき、このアルバムを取り出してみる。テクノの開祖・クラフトワークの1981年度作品、「コンピューターワ-ルド」のドイツ語盤、「コムプーテル・ヴェルト」である。
まあ、あんまりやる気があるとも思えないいつものボーカル部分がドイツ語で歌われている、という違いしかないが、いや、なんとなく物々しくて面白いじゃないですか。
このアルバム発売時点で、もう彼らはテクノ最前線から置いてけぼりを食ったみたいなイメージで見られていた。いや、それでもいいよ、テクノ最前線の音があれなら喜んで時代遅れになってやろう、と私なんかは確信を持ったものです。それでも、このアルバムにややこしい理屈付けをしたがる人もいて、うんざりさせられたものです。いいじゃないか、テクノなんかオモチャなんだからさ。