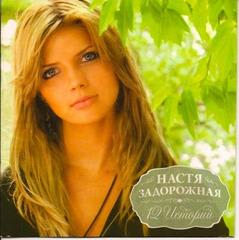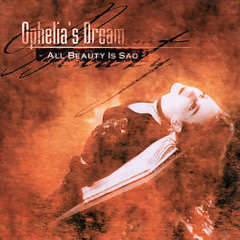”MISTIKOS PROORISMOS”by EFTIHIA MITRITSA
さっき。夜の10時過ぎくらいだったかな、所用あって近所のコンビニに買い物に行ったのだけれど、海岸通りを流れる空気のうちに、ちゃんと初夏の息付きが流れ込んでいるのに驚いたのだった。人の気持ちを妙な胸騒ぎに誘い込む、この空気の不思議な生暖かさ。今夜、初夏が私の町にもやって来た。
ほんの2~3日前には近所の人たちと「この季節にこんなに寒いなんて。自然がどこかおかしくなっているんだよ」なんて話をしたばかりだったのだが。この春から、人々の意識の背中辺りにのしかかって去らぬ重苦しさ。あの”終わりの季節”の囁きにもめげず、春の約束は今年も果たされようとしている。
海岸通りの交差点あたりの灯りは当世風に自粛の風が吹いて薄暗くはあるが、いつの間にか季節の巡りは律義に、このちっぽけな町の通りに今年もやってこようとしているのだった。
20代半ばかと想われるギリシャの女性歌手のデビュー盤である。歌手の名前をどう発音するかなんて、見当つけることさえ諦めた。(このタイトル、”秘密の約束”って意味じゃないかなんて気がするんだが、どうですか?)
瀟洒、という言葉が非常に似合う出来上がりとなっていて、一発で気に入ってしまった。どこか不機嫌な表情をその底に漂わせ、イチゲンの、ヨソモノの食い付きを最初は拒否さえしてみせるかのような偏屈なギリシャ・ポップスにしては珍しく、なんて言い方もどうかと思うが、ともかく非常に素直にポップスとして楽しめた、という話である。
20代の女性にしてはずいぶんと落ち着き払った歌唱だが、まあ、ヨーロッパ、それもギリシャだから。そんな大人ぶった、退廃さえ漂わせる歌声の中からこぼれ落ちる甘酸っぱい青春の日々の感傷。相当周到な計算の元に作り上げられた、そんな構図。アコースティックな、フォークっぽいつくりのサウンドに巧妙にギリシャ伝統のブズーキの響きが紛れ込み、当世西欧風なポップスの流れがいつか、濃密なギリシャ・ポップスへと合流して行く。
悠久のギリシャの歴史の厚ぼったい重圧と 古きヨーロピアン・ポップスの倦怠。張り巡らされたクモの巣のような時の堆積。その狭間を縫って噴出してくる、芽生えたばかりの青草の輝き。この構図もちょっと良い感じだ。