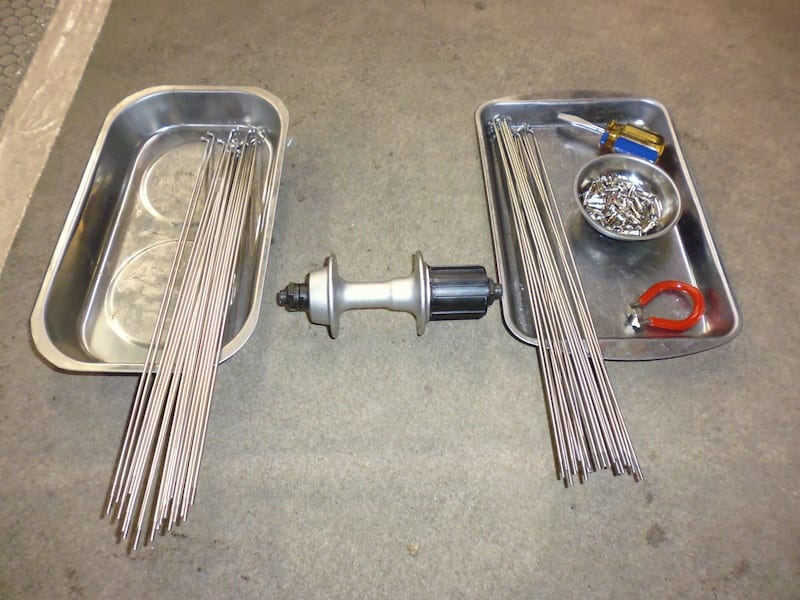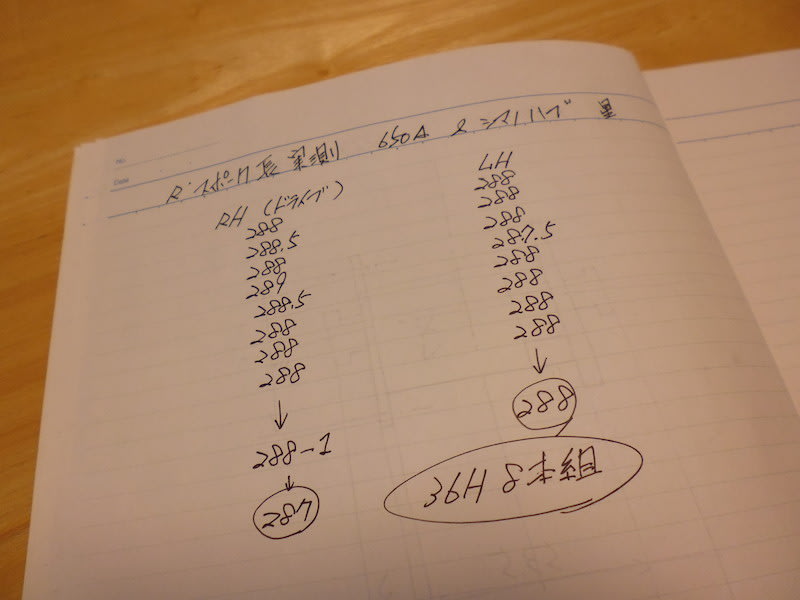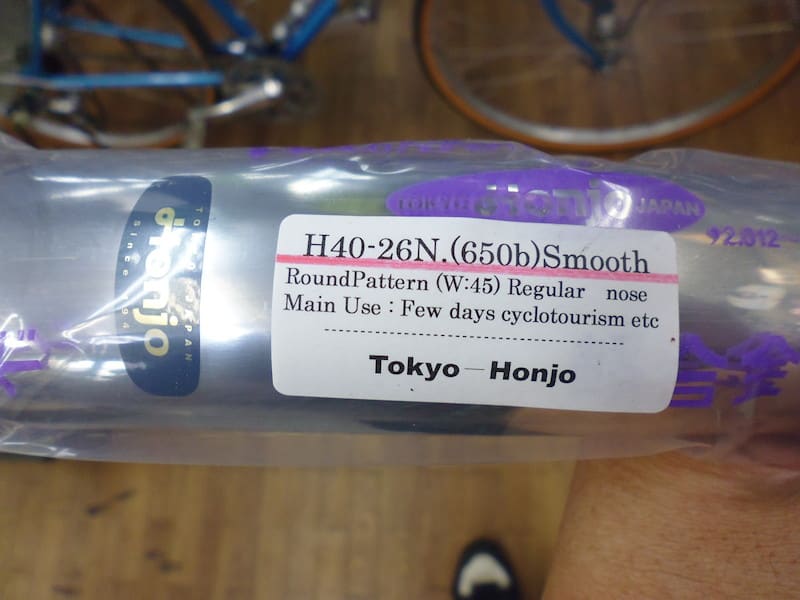フロントに引き続きリアのマッドガードを取り付けます。
その前にボスにネジが通らないので、タップでネジ山を整えます。よく見るとネジ山に塗膜がのっているので、この自転車はマッドガードを取り付けずに使われていたのかもしれません。
面倒なのがチェーンステーとシートステー部分のボス。90度弱回す度にハンドルを付け外ししなければなりません。
まずチェーンステー部の取り付け位置を決めます。
パンチで穴開け。
フレームに直付けだとタイヤとのクリアランスが大きくなってしまうので、適当なカラーを挟んで取り付けます。
フレームに固定しました。
締結部に樹脂やゴムを挟むと緩みの元なのですが、ランドナー本を見ると皆、皮やゴムワッシャーを挟んでいるので、ゴムワッシャーを挟みました。直付けだと振動を拾ってクラックが入っちゃうのかな?
この状態でシートステー部のボスに合わせて穴を開けます。
ボスぴったりの位置に穴が開きました。
と思ったらカラーの厚さ分オフセットするとボスからズレちゃいます。正確にはオフセットではなくチェーンステー部の取り付け点を中心にした円運動ですからね。
仕方ないので、チェーンステー部の取り付け穴をパンチと金ヤスリで長穴に加工しました。斜めっちゃったけど。
無事取り付いたので、ステーの位置を決めます。後ほど判明しますが、この位置、上過ぎです。
テールランプの位置も決めます。ランプの上辺が水平になるように決めましたが、これも上過ぎでした。
穴を開けて取り付け。フロントの経験から1点留めにしました。フロント同様、マッドガードを揉んでタイヤとのクリアランスを一定にします。
フロント同様にステーをカットしアーレンダルマで固定。アーレンダルマをダブルナットの要領でナットで固定したのですが、そのナットとチェーンが干渉してしまいました。
仕方ないのでナットを金ヤスリで薄くします。もう加工次ぐ加工・・・・取り付けに使った既製品のボルトはほぼ全てに加工が必要でした。
一応形にはなりましたが、なんか野暮ったいです。
フロントのステーは下過ぎて鈍重に、リアはステーとテールランプが上過ぎて腰高に見えます。もうちょっと慎重に位置決めすべきでした。
タイヤとマッドガードのクリアランスは、及第点だと思います。