
昨日の朝日新聞の読書欄に、本田さんが、本の紹介をつうじて、「物言わぬ他者」としての動物という興味深い視点を提示していた。自己を知る鏡としての他者。この場合、他者は動物であり、自己は動物である。
以下、全文。
朝日新聞 2010年11月28日号 15面
本田由紀「動物を通して知る人間」
みなさん動物は好きですか?
好きな人は多いでしょう。CMにも待ち受け画面にもカレンダーにも、可愛い動物の赤ちゃんや、珍しくて面白い動物がてんこ盛ですもんね。どうして人間はこんなに動物が気になるんでしょう。もしかしたらそれは、動物が人間にとって「物言わぬ他者」だからじゃないかと思います。動物には動物の言葉があるのかもしれませんが、とりあえず人間には理解不能ですから、「物言わぬ」ことにほぼ等しい。だからこそ、人間と動物の間には、特に言葉によって邪魔されない直接的な共感が生まれる瞬間もあります。
幸田文さんの『幸田文 どうぶつ帖』(平凡社)には、飼われている動物と人間の感情的な交流や、動物園にいる動物への鋭い観察がちりばめられていて、人間と動物との良い関係についてのお手本になります。
でも、動物が「物言わぬ」ことに乗じて、人間は自らのエゴによって彼らを踏みにじることもあります。気まぐれで飼い始める、世話をしきれなくなったり飽きたりして捨てる、捨てられた動物が生き延びようとしてその土地の生態系を壊してゆく、あるいは捕えられてシステマティックに「殺処分」される、といった現象をぐいぐい記述しているのが、小林照幸『ボクたちに殺されるいのち』(河出書房新社)です。
動物は人間にとって「他者」ですから、きれいごとの陰で、優位に立ちやすい人間によって冷酷な行為がなされることもある。それを直視した上で、人間と動物との真摯な共存をどのように図ってゆけるかを、小林さんは問いかけています。
また人間は「他者」であるはずの動物に対して、自分自身の醜い姿を投影することもあります。オーウェルの名著『動物農場』(岩波文庫など)で、人間を追い出して農場を占拠した動物の間に何が起こったか。豚たちが詭弁を弄して「下層動物」を支配し、その労働の産物を独り占めして敵であったはずの人間とも手を結び始める。すごくブラックで面白い寓話ですが、そんな役割を豚に与えてしまっていることは、豚に対して失礼な話でもあります。動物には種を保存する本能はあっても、このような邪悪さはないでしょう。
人間が「物言わぬ他者」たる動物を、どう扱いどう描くかということに、人間という種や、その中の個々人の本性が映し出されているのだと思います。私たちは、「他者」ーそれは動物に限りませんーを通して、自分自身を知るのです。
(数日前にわたしが書いたブログの内容に少し似ている)
http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/5665022680cab0290333eaf9136cefae
この記事を読んで、改めて、動物は、人間にとっての他者だという単純な事実に気づく。この点に照らして、神話や寓話のなかで語られる「物言う他者」たる動物をどのように考えればいいのか。他者であることは変わらないが、わたしたちと同様に話し、考え、行動する存在としての動物について、今少し考えてみたい。










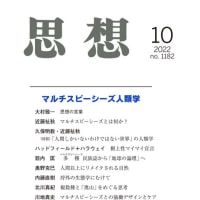

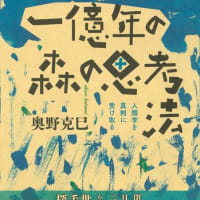
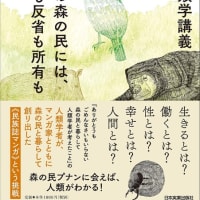



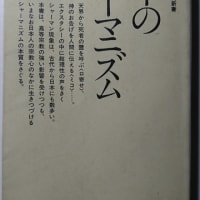


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます