
愉楽に満ちた、じつに実り多き会だった。
http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/959facca1d6f87a27f45634131ca95e8
参加者は、ほぼ定員(40名)だったと聞いている。ドキュメンタリー『ヤノマミ』の上映に続いて、国分拓さんと池田光穂さんの対談が行われ、その後、参加者はヤノマミのシャボノ(屋敷)様に椅子を並べ、座談式で質疑を行った(写真)。
わたしは、ゲストの国分さんのトークに、自分自身と同じ型の感性を見た。
以下は、講演会そのもののまとめではなく、わたしのフィルターをとおした雑感のようなもの。
・国分さんのトークには、ガルシア・マルケスの話が何度か出てきた。お好きなようだ。【わたしもである】
・マジックリアリズムの出来事について。現代日本の空間では嘘のような事柄が、ベネズエラやブラジルでは本当であるように感じられたという。そこに行って何かをやりたいと思われた。海ではなく奥地へ、そうして、ヤノマミにたどり着かれたのだ。
・そうした感性のベースには、生きづらい現代社会の価値観への不満があるという。【これもわたしと同じだ】
・本当の人間の姿が、どこかに行けば見られるのではないかという思いを秘めて、ヤノマミに接近されたのである。【わたしも、本当の人間に会いたい、人間の本来の姿に会いたいという思いを抱いてきた】
・彼らの狩りについてゆくための体力トレーニングの話があった。【わたしも、授業を終えてトレーニングをしていた!】
・150日間のヤノマミとの同居のなかで、何か起こったのは30日、あとの120日は何も起こらない平凡な日常だったという。事件をドキュメンタリーの主題にするが、本当は、何もない事態のほうが彼らの暮らしの本質なのではとおっしゃる。しかし、そうした日常の何もない現実をドキュメントするのは本当に難しいという。【わたしの悩みと同じだ。報告書のために何か非本質的なことを書いて、時間とエネルギーを浪費する。本質的な事柄は、なかなか書くことができない】
・池田さんは、対談のなかで、人類学は、現地言語を習得し、言語による接近をつうじて、他者表象を言語革命によって乗り切ろうとしたが、ポストモダン期に、言語を他者表象の唯一の手段とするような仕方が批判されたし、その延長線上に、『ヤノマミ』のドキュメンタリー作家と文化人類学の学生たちが語り合うこの機会は、<民族誌>を考えるための感動的な場ではないだろうかと述べられた。【なるほどと思った。映像人類学は、民族誌のたんなるオルタナティブだという位置づけはまちがっている】
・空腹に苛まれているときに、肉を与えられて口に入れて食べたさい、それが身体のなかで動いたように感じたという、原初的な(生き物としての)経験。さらには、森のなかでは、耳から入ってくる音の感覚が際立っているという話。【それらは、わたしのプナンの経験と似ている。いや未開文化経験主義の感性なのかもしれない】
・ヤノマミというのは人間という意味であるが、国分さんは、多くの人びとはこのドキュメンタリーを見て、彼らも人間だという印象をもつのかもしれないが、ご自身は、おれもヤノマミであると思ったという。【彼らのなかにわたしを見つけるのではなく、わたしのなかに彼らを見るということ。ヤノマミ経験をつうじた見方の逆転。他者の正しき捉え方だ。この脱・エゴ(エスノ)セントリズムは、人と動物の関係にスライドさせることもできるように思う。動物が人間のようだというのではなく、人間こそが動物なのだという、脱・アントロポセントリズムに】。
ドキュメンタリー『ヤノマミ』は、森を「主語」に製作されたのだという。そうだったのか。国分さんの話をうかがっていて、現実とそのドキュメンタリー化の間における逡巡の大切さを感じた。人類学者にとっては、現実と民族誌の間の逡巡ということになる。一参加者として、深い示唆に富んだ、質の高い、後々まで記憶に残るような講演会だったと思う。国分さん、池田さんには、この場で、謝意を述べさせていただきたい。専攻の学生たちは、人数が少なかったが、現実の厳しさに直面しながら、連日、夜遅くまで打ち合わせを行い、意義のある講演会を成功させた。横目で見ていたが、たいしたもんだと思う。今期の活動としては、冊子編集が残っている。期待したい。










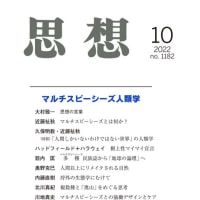

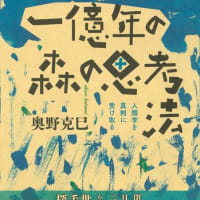
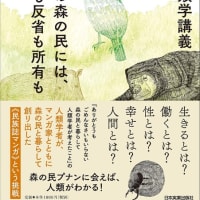



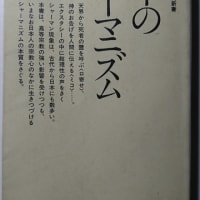


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます