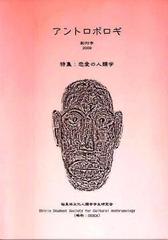4月に入って大学の授業が始まり、わたしの読書量は格段に落ちた。”しかたないだろそれがおまえの仕事なんだから。本を読み耽るためにはもう眠らないと心に決めることだ”、とでもルイ・フェルディナン・セリーヌであればいうにちがいないと思う。
ルイ・フェルディナン・セリーヌの『夜の果てへの旅』(生田耕作訳、新潮文庫)の上巻を読んだ。パリのカフェから第一次大戦の志願兵となり、軍隊での死と隣り合わせの日々を経て狂乱し、アフリカに旅立ったフェルディナンは、極悪の労働条件のもと商事会社の社員となり店を放火し、今度はアメリカで人間精神をすり減らすフォードの工場で働くようになるという件までが、上巻のあらすじである。
主人公フェルディナン(=セリーヌ)は、戦争の悲惨さ、植民地の搾取、資本主義の人間疎外を経験し、そのような「夜の果てへの旅」を経て、世界はつねに不条理を抱えており、悪意に満ち満ちていると感じていて、社会体制から、さらには、ねんごろになった女からも、いつもいつも、すべてのものから逃げることばかり考えている。共振共感できない世界に対して、フェルディナンは呪いと罵りの言葉を吐きつづける。そのような姿に、わたしは打ち負かされてしまった。ほとんどわたしそのものを奪われてしまった。とにかくこんなすごい小説があったもんだと思う。言葉と文章のひとつひとつに、魂の底から叫んでいるような激烈さがあるのだ。
『夜の果てへの旅』のなかの印象深い文章を、このある種トンデモない作品を読んだことを記念して、以下に断片的に書き留めておきたい。
情欲に童貞があるように《恐怖》にも童貞があるもんだ。
大砲もこの連中にとってはただの物音にすぎなかったのだ。これだから戦争みたいなもんが長続きできるのだ。・・・ほとんどの人間はいまわの際にならなければ死なないのだ。残りの人間だけが二十年も前から、時にはもっと前から死に始め、そのことにだけかかりきりだ。この世の不幸な連中。
ここでは、なるほど、僕らは怒鳴られたりすることはなかった、それどころか優しげな言葉づかいで話しかけられ、死が話題にのぼることはめったになかった。けれども死の宣告は、僕らが署名を求められる書類の一つ一つの片すみに、僕らに払われる配慮の一つ一つにも、あらゆる勧告の中にも・・・(中略)・・・看護婦たち、この売女どもは、僕たちと運命を分かち合ってなぞいなかった。彼女たちは、反対に、長生きすることしか考えていなかった。もっともっと長生きし、恋をし(こいつは顔にかいてあった)、散歩し、そして千遍も万遍も男に抱かれることしか。この天使たちは、懲役囚みたいに、股間に潜めた、未来のためのちっちゃな計画に執着していたのだ、つまりこっちが泥んこの中でとんでもない死にざまを遂げたあとの情事の計画に。
このアフリカの地獄の黄昏ときてはすさまじかった。逃れるすべはなかった。毎度、巨大な太陽の殺害とも見まがう悲壮な場景。大仕掛けなトリック。もっとも、観客が一人では張り合いのない話だ。一時間にわたって、空は狂おしい鮮血を全身に浴び、大見得をきる、やがて、木立ちのあいだから緑色が湧き上がり、最初の星々を目ざして、地上からゆらめきながら立ち上がる。そのあと、灰色が地平線をすっかり奪い返し、それからもう一度、赤色の番だ、がこんどは赤色もくたびれはて、長持ちしない。それが末路だ。百回興行のあとの安ぴかの衣装のように森の上で擦りきれくたびれ、色彩は一つ残らずぼろ切れになってくずれ落ちる。毎日きっかり六時ごろこいつが生じるのだ。
想像してもみたまえ。そいつは、彼らの街は、立っていたのだ。完全にまっすぐに。ニューヨーク、これは突っ立った街だ。むろん、僕たちはすでに、いくつもの街を見てきていた。しかも美しい街を、港を、それも有名な港を。だが、ヨーロッパでは、そうだろう、そいつは、街は寝そべっている、海辺に、あるいは海岸に、それは風景に沿って身を横たえ、旅人を待っている。
おまけに年齢というやつが、あの裏切り者が踊り出し、最悪のもので僕らを脅かしかねない。要するに、自分のうちに生命を踊らせる音楽が鳴りやんでしまったのだ。冷酷な真相につつまれたこの世の果てへ、青春は跡形もなく消え去ってしまったのだ。ところで、自分のうちに十分な熱狂がなくなれば、いったい、外へ飛び出したところで、どこへ行くあてがあるのか。現実は、要するに、断末魔の連続だ。この世の現実は、死だ。どっちかに決めねばならない。命を絶つか、ごまかすか。僕には自殺する力はなかった。
市街電車がハドソン河沿いに都心に向かって走っていた。車輪全体と臆病そうな車体でかたがた震える古ぼけた電車。終点まで行き着くのにたっぷり一時間はかかった。乗客は電車の入口にすえられた自動コーヒー挽きみたいな機械による複雑な支払いの儀式に、いらだちもせず服従するのだった。連合軍の一員のようななりをした《バルカン戦争捕虜》みたいな制服の車掌が、お客の支払いぶりを眺めているだけだ。
若いうちは、どれほどすげない仕打ちにも、どれほど意地悪な身勝手にも、愛情の気まぐれとか、世間なぬロマンチシズムの現われとかいった言いわけを見つけ出すものだ。ところが、さらに年をとり、単に人並みの生活を続けるためにも、奸知と、冷酷と、敵意がいかに必要であるかを、人生から十分見せつけられたとき、僕たちははじめて気がつき、迷妄から醒め、過去の忌まわしい事柄を一つ残らず理解できる立場におかれるのだ。自分自身を、つまり、自分がどれほど穢らわしいものになってしまったかを、念入りに観察するだけで十分だ。もはや神秘も、お人好し根性も残されていない、今まで生きてきたからには、手持ちの詩情などすっかり食いつくしてしまっているのだ。人生なんて、いんげん豆とかわりない。
僕をひきとめるために彼女が心をくだくのを見て、僕はすまないような気もするのだった。彼女を愛し散ることには、まちがいなかった。だが、それ以上に僕は自分の悪癖を、あの到るところから逃げ出したい欲望を愛していたのだ。
★★★★★★
相模原や多摩にはたくさんの縄文期の遺物が出土し、それらが、行政当局の努力によって整備されていることを知ったのは、比較的最近になってからである。自分の足元の場所に、1万年前の先史の時代に、ヒトが暮らしていたことを想像することは、じつにワクワクする経験である。昨年度から、3年のゼミで、考古学的な観点から、と言っても遺跡を掘るというような本格的なことには遠く及ばないが、大学の周辺地で、そうした点を視野に入れながら、半日フィールドトリップを行っている。さらに、この地域、とりわけ横浜線周辺の事情を調べているうちに、横浜線が開通する以前の時代に、養蚕業が盛んに行われて、かつて絹の道と呼ばれていた、JR相模線沿いの道路が栄えていたという事実が分かってきた。上溝(かみみぞ)の町は、このあたりを車で走っていると、突如として現れる感があるが、そこは、明治から大正期にかけての経済の中心であった。わたしは、考古学的な興味関心に加えて、上溝のあたりで、人びとの暮らしにあてて、民俗学的なフィールドトリップを行うことをふと思いついた。田名向原に行く<考古学班>と上溝周辺で調べものをする<民俗学班>に分かれて、5月半ばに、半日かけて歩き回って(その後は懇親会になだれ込む)、調査レポートを作成しようという試みである。それが、近隣での人類学の調査実習を組み込んだゼミの、4月から5月にかけての活動の概要である。まずは手始めに、このあたりがどういった地域であるのかを調べて、自分が、考古学か民俗学か、どちらの方向で調べてゆくのかを決める手がかりを得るために、今日のゼミでは、あいにくの雨であったが、相模原市立博物館で展示物を見学し、研究調査室で文献研究を行った(写真)。
腰に挿した山刀でシャーマンは悪霊を叩き切って床にバッタリと倒れる。病気を患った者の家族はあらかじめ用意してあった織布をシャーマンにそおっと掛けて(写真:カリスのシャーマンによる儀礼)、サイチョウの羽で7回叩いて、シャーマンを覚醒させる。シャーマンは、その後、叩き切った悪霊の正体について語り始める・・・
それは、カリスのシャーマニズムにおいて、シャーマンによる悪霊の殺害と観客が見ている現実が交錯する瞬間である。わたしはこれまで、ただ独りシャーマン的な存在だけが、世界のこちら側とあちら側その両方の世界を経験していると思っていた。しかし、そういった理解は正しくないのではないか。そうではないのだ。人びとの間で、悪霊や祖霊たちが跋扈する世界のあちら側と現実に暮らしを営んでいる世界のこちら側は、きちっと切り分けられていないのではないだろうか。それらは相互に重なり合う。こちら側でもあり、あちら側でもある場所に、わたしたちは暮らしている。そのような認識こそが、全体として、シャーマニズムを支えてきた。
人が死んだときなど、現実空間にひんぱんに入り込んでくるスピリチュアルな存在がいる。逆に、夢見によって、生者たちは、スピリチュアルな世界に入ってゆく。スピリチュアルとは、この場合、精神的(内面的)かつ霊的であるような領域のことである。あの世や霊の住む世界などあるわけがないと言って抑圧することによって、わたしたちの世界秩序は、合理的・科学的なものとして立ち現れる。いやむしろ、合理主義・科学主義によって、世界を秩序づけることによって、世界のこちら側だけで完結しようとしてきたし、その反対にあちら側を胡散臭いものとして遠ざけてきたのではあるまいか。
そうした見方をあらかじめ植えつけられてきたわたしたちにとって、じつは、現実と非現実、世界のこちら側とあちら側とが曖昧なかたちで交わり、そのことがヒトの脳のなかに構造化されていることを「再」発見するまでには、長い時間がかかる。
自然環境保護思想の高まりの果てに、生物多様性をビジネスチャンスと捉え、日々、"エコ"であることをいいことのようにお題目として唱えるような滑稽の時代に、そもそもの根源にある<自然>に関して、それに向き合う<人間>を含めて、圧倒的に外部的かつ根源的な、憂いに対する批判の先に建設的な見通しのある研究の方向性は、人類学において、どのようにしたら可能かという問い。わたしたちの研究(「自然と社会の民族誌」)の根元のところにあるのは、そういった問題意識である。昨日、研究会というよりも、研究談話会というような内容の会をもった(写真は、東大キャンパス)。以下、その概要の個人的な覚書である。
今日の現実世界にヘゲモニックに浸透する、<自然>に関する共通した、あるいは共有される傾向にある<自然>観がある。人類は、荒ぶる獣たち、緑の魔境だったはずの密林などに果敢に闘いを挑み、それらを制圧し、さらには、手軽な加工対象に変えてきた。<自然>は、人間によって、大禍を伴う畏怖対象から死せるマテーリアへ、能産的なものから所産的なものへと変工されてきた。わたしたちは、まずもって、ヨーロッパとして一くくりにされる地球上の一地域の人たちによって培われてきた、そうした知性の発展の水脈にあたらねばならないだろう。それは、やがて、ヘーゲルによって精度を高められて、それ以降の人類が参照する、もっとも頼りになる思考を形づくるようになったからである。世界中で日の目を見た、科学主義や客観主義につながる、そうしたギリシャ神話のアポロン神的な思考に対して、ヨーロッパのなかでも、より人間の情念に根ざした陶酔的・熱狂的だという意味で、ディオニソス神的な思考の系譜もまた存在する(ニーチェ以降の哲学)。
もし、人類学が、人間の感情や芸術に接近することに重心を置くと言う意味で、このディオニソス的な系譜に連なるのだとすれば、人類学もまた、ヨーロッパのアポロン的な思考だけが唯一無二のものではないことを人類の思考形態の多様性のうちに示してきたことになる。そうした作業の体系化が、デスコーラやヴィヴェイロス・デ・カストロというアングロサクソンではない民族誌家によって、南米アマゾニアの先住民のフィールドワークから生み出されてきている。彼らは、非西洋の人たちの<自然>をめぐる態度や思想を掘り起こし、非西洋のもののほうが、西洋形而上学に基づく理法よりも優れている、あるいは、ましであるというような、価値判断に基づくモデルを提起しようとする意図を持ち合わせているのではない。デスコーラによる存在論のモデルの提示は、人類社会の行く末に反省を促すより意義深いものである。
http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/3de5d7671fd49016a1f34209629148ea
「フィリップ・デスコラは自己が環境や他者などの様々な非自己を経験するのに社会が用意する説明やその組織化を、四つのタイポロジーによって考察しようとしている・・(中略)・・この理念モデルは、もともと彼が調査した南米のアチュール族の『人間と動物』観(ト-テミズム)を再考するために考察されたものだが、近代科学的世界観を現実理解の総括的・最終的枠組みとして特別視する考え方に反省を促すものになりえている」(出口顕、三尾稔編『人類学比較再考』pp.6-7, 2010, 国立民族学博物館)。
プナンの狩猟キャンプの朝は早い。夜明け前にハンターたちは目を覚ます。彼らのなかに低血圧で起きられないというような人は見たことがない。してみると、低血圧でなかなか起きられないというのは、文化的な問題である可能性がある。彼らは、朝一番に放屁ショーとわたしが名づけている演芸会のようなもので盛り上がり、そのうちに男たちは立ち上がり、自分の荷物をコンパクトにまとめ、狩猟の身支度を整えて、無言のまま、ジャングルのなかに狩猟に出かける。食料がない場合には、口に物を入れることができないのは当然としても、食べ物がある場合にも、同様に物を口にせずに狩りに出かける。彼らは、食べ物・飲み物を準備するのを怠っているのであろうか。狩りに出かける一刻を争って、食べたり飲んだりする暇を惜しんでいるのであろうか。いずれも正しくないように思える。場合によっては、夜明け前から日暮れまで、12時間にもわたって、ハンティング・トリップが続くことが往々にしてあるからである。その間、彼らは、果実の水分とタバコなどの嗜好品を除いて、一切のものを口にしない。プナンのハンターたちに、なぜハンティングに行く前に、食べ物・飲み物を摂取しないのかと尋ねると、それが、ふつうのことだ(malai)、それが、われわれプナンのやり方だ(keja uleu penan)という返答が戻ってくる。彼らはそうは言わないが、わたしは、プナンが、何も食べないでハンティングに出かけるということの底には、狩猟民プナンのハンティングに対する並々ならぬ決心のようなものが潜んでいるのではないかと思っている。自分たちが殺して食べる食料となってくれる動物に対峙するために、空腹(melau)によって自らを苦しめ、痛めつけることによって、つまり、空腹を自らに追経験させることによって、人間による動物の殺戮によってしか行われることがない狩猟のもつ意味を、ハンティングの実践のなかで確認しようとしているかのようにわたしには思える。いやどちらかというと、ハンティングでジャングルを歩き回っている時の空腹感が、動物に対する剥き出しの残虐性によってしか獲得することができない食資源としての肉の有り難さを、彼らに反復的に想起させるのではないだろうか。むろん意識下のレベルにおいてであるが。食べて生き永らえることにまつわる狩猟民のしきたりの意味は、同様に、食べて生き永らえることを、生産者から流通業者から消費者へという流れのなかで、別のかたちで行っているわたしたちのやり方の意味を考えるときに、鋭く突き刺さってくる。問題は、たんにそれだけではないが。わたしの生業としての大学での授業の一年が今日から始まる。火曜日は1,2,5限に授業が入っている。食べて生きるということからいえば、教えたり研究したりして生き永らえるということは、真っ直ぐではない。プナンを経て、その屈折度について考えることには、人類史のなかでは大きな価値があると思う。
BL小説の主人公の恋の相手の名前がわたしと同姓同名だと教えてもらって、昨日青葉台のブックファーストに行ったら売っていたので、買って読んでみたが、読むのにたいしてたいして時間はかからなかった。火崎勇の『椿の下で』(ムービック社、ルナノベルズ、900円)という本で、2010年3月30日発行としてある。つい最近出た本ではないか。「失礼ですが、こちら奥野克巳様のお住まいでは・・・?」という件では、驚いて返事しそうになって、なんとなくくすぐったいが、そんなことはとりあえず置くとして、ストーリー。
晩熟の青島光美(♂)は、2年歳上の克巳(♂)に対して恋愛感情を抱いており、克巳が相続したラブホテルで働くようになった光美は、克巳と近づきになり、どうしようもないモヤモヤとした気持ちを抱き続けるが、とうとうその思いをセクシャルに遂げる。その後、光美は、克巳には探し続けている女性がいることを知って複雑な気持ちを抱く。突然、ある女性が克巳を尋ねてきて、恋人関係にあるとしか思えないような話の内容に、光美は嫉妬心を燃え上がらせ、克巳を忘れるために、行きずりの男に身を任せようとする。そのときになって、その女性は、克巳のお婆さんの不倫相手の孫で、お婆さんと不倫男性、つまりその女性の祖父との恋路の話などをしていたことが分かる。そうした一種の謎解きがあり、ふたたび光美と克巳が結ばれるという内容の話である。
雑感として。光美が女であれば、凡庸な恋愛小説以下の小説である。ということは、男の男に対する恋愛感情の切なさとセックスシーンを描くという異色の内容に、この本の妙味がある。だとすれば、光美のオスとしての心と身体が、どのように克巳に魅かれるのかという点の微細な描写がなされてしかるべきではないだろうか。それは、まったくのないものねだりだろうか。BL小説とは、それ自体で確立されたジャンルであり、そうした門外漢からの批判はあたらないのだろうか?BL小説初体験の身としては、皆目分からない。全体としては、あまりに綺麗に話がまとまりすぎていると感じた。同じ系統であるとまったく意識されていないのかもしれないが、ゲイ小説・三島の『禁色』に比べると、心理・感情描写がずいぶん弱い気がする。
http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/8bdbad1d9224183c8f6093bad1185a57
ホームページを見ると、この作者のなんたる生産性の高さ。昨年一本しか論文を書いてないわたしとしては、すごいと思ってしまう。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Shikibu/2246/index2.html
気になるのは、ティーンズ文庫のコーナーにあったのだが、BL小説というのは、どちらかというと女性向けなのだろうか?ショタコンって言葉があるが、それは少年愛とは微妙にちがうし、BLともちがうのか?こういった性的嗜好のバリエーションが、若い世代においてかなり進んでいるということなのだろうか?大学で、性の人類学という授業をやっているけれど、このあたりについてはまったく知らない。迂闊だったと思う。とはいうものの、今後、BL小説に今後はまることはないと思うけれど。もうひとつ、タイトルの「椿の下」ってどういうことなのか?解を与えてくれるような記述は話のなかには見あたらない。
内田百間(うちだひゃっけん、間の日は月が正しい)の『冥途・旅順入城式』(岩波文庫)のうち、前半の『冥途』の部分を読んだ。18の短編から構成されている。それぞれ、どこにでもあるような、ありきたりの風景から出発して、主人公とともに不安を煽り立てられ、事の成り行きに翻弄され、夢幻の世界に引き込まれていく。そうした感覚に表現を与えてみたいと思い立って、<わたしたちのなかにある他者や外的存在に対する根源的な不安のようなものが、かたちになって現われる、夢を見ているときに見ているような文学である>と仮につぶやいてみたが、そういう言い方で、事の本質を押さえているかどうかは微妙である。
「波止場」は、湯治場で懇意になった男が、妻が蒸気船に乗るときに手を取って船に入り、妻とともに窓からかわるがわる外を覗いてお出でお出でをしているのが目に入るが、足がすくんだままで、蒸気船に乗りそびれてしまった夫の話。夫は蒸気船を追いかけるために車を走らせる。「車は長い土手を走っている。風のように速い。両側に高い草の生えた間を走りぬけていると、草の中から子供が一人ひょろひょろと出て来て、私の車の下に這入った。私が吃驚して、振り返って見ようとしたら、車屋が、『振り向いて見ちゃ困りますよ』と非常に恐ろしい声をして云ったので、私はどきりとした。矢っ張り死んだのだなと思う」。車は、蒸気船から降りた客が乗り換える駅に着く。妻はすでに男といっしょに汽車に乗り込んでいた。切符を買わずに乗ると駅員に突き飛ばされて、汽車は出てしまい、次の汽車で追いかけることになる。そうした道行きにおいて、彼はときどき妻のことを忘れてしまうのだけれども、着いた駅ではふたたび妻のことを探し始める。「早く早く妻の傍へ行き度いと思う心と裏合わせに、もうどうでもいい様な気がし出した。そう思ってぼんやり見ていると、例の男が私の顔を見て、今までに見せたこともないような美しい顔をした。私は己に帰って、はっとした。そうしてあれが平生ひとごとのように聞いていた間男というものだったかと気がついた」。
本のタイトルにもなっている「冥途」では、一膳飯屋でめしを食べているときに、4,5人の客がやって来て、なにやら話しているのが聞こえてきたという件から始まる。そのうちの一人の年寄りの様子は、見えていながら、どうもはっきりしない。蜂が飛んできた。昔蜂をつかまえてビードロの筒に閉じ込めたという話が聞こえてきたのだが、その話を聞いて、主人公は、自分の記憶に思いあたり、その年寄りが、自分の死んだ父であると思い込む。「『お父様』と私は泣きながら呼んだ。けれども私の声は向こうへ通じなかったらしい。みんなが静かに立ち上がって、外へ出て行った。『そうだ、矢っ張りそうだ』と思って、私はその後を追おうとした。けれどもその一連れは、もうそのあたりには居なかった」。その一膳飯屋は、現世と冥途の境界だったのである。解説のなかで、種村季弘は、この物語を受けて書いている。「生と死はそっくり瓜二つであり、いまにも触れ合い同化しそうでいて、平行線のように交わることなくすれ違い続ける。最終的には、いつかはこの世は滅び、自分はあの世に行くだろう。百間にとっては、それまでの遅延として営まれるのがこの世なのである」。★★★★
薄曇のなか今日の桜の美しい林の近辺の桜は少し散りかけている。ところで、わたしが1年間の海外サバティカルから帰国すると桜美林大学に文化人類学専攻なるものができていた。出発前はそういった専攻の名前は案さえ挙っていなかった。文化人類学を専攻する学生が30名(1100人中)というのは多いのか少ないのか、全体としては、いまのところ、33専攻のうち人数的には、半分くらいの位置である。はじめての専門課程の学生(3年生)を出す予定の2009年度の年初めに、専攻の学生を集めて、桜美林大学学生文化人類学研究会(Obirin Student Society for Anthropology:通称OSSCA)を組織し、学生主体で協力し合って活動を開始し、講演会や活動報告のための冊子を作成した。その成果、『アントロポロギ』(創刊号2009:写真)の特集は、「恋愛の人類学」である。本田透さんと池田光穂さんをお招きして、2009年12月16日に開催した、講演会「恋愛の人類学~二次元恋愛は現代の恋愛への宣戦布告か?~」の講演会記録と学生によるエッセイが主要記事である。二次元恋愛はオタク文化によって生み出された近年の現象では必ずしもないという論点との関わりで、個人的に、後になって思い出したのは、落語の『幾代餅』という演題である。搗米屋の奉公人・清蔵は、絵草紙を見て吉原の花魁・幾代太夫に恋煩いをする。その落ち込みを見かねた親方は、1年間みっちり働けば、その金でその花魁を買いに連れて行ってやると清蔵をなだめる。清蔵は、1年後、病気治しよりも女郎買いのほうが巧い医者に連れられて、野田の醤油問屋の若旦那とのふれこみで、幾代太夫に会い、思いを果たす。花魁に「今度いつ来てくんなます」と問われた清蔵は、自分は搗米屋の奉公人にすぎないし、1年間金をためてやっとあなたに会いに来れたのであって、もう来れないと正直に言うと、その言葉に打たれた幾代太夫は、来年3月に年季奉公が明けたら訪ねて行くので、女房にしてくれと応えた。舞い上がってしまった清蔵は奉公先で仕事が手につかない様子で、来年の3月のことばかり考えていて、3月と呼ばれても返事をする始末。3月になると、幾代太夫は約束通り搗米屋を訪ねて来て、清蔵と夫婦になる。その後、二人で幾代餅という餅屋を開いて、それがその両国名物の餅の由来だという話(古今亭志ん生)。二次元空間に描かれた存在に感情移入する、恋愛感情を抱くというのは、たしかに人類社会に広がりをもった現象なのかもしれない。清蔵の場合には、二次元を介して、その先にいる三次元の存在にこそ思いを抱いたのであるが。冊子『アントロポロギ』創刊号は、160部ほど印刷して、主に、学生向けに配付する。学生の手作りの感じが、逆に、なかなか新鮮でいいかも。この件についての問い合わせは、次のメールアドレスまで。ossca_obirin@yahoo.co.jp 学生研究会の本年度の活動はすでにスタートしていると聞いている。なんでもテーマは「この世とあの世」(「世界のこちら側とあちら側」)だと聞いている。学内で興味ある学生はぜひ参加してほしい。
志ん生の「幾代餅」はアップされてないので、かわりに「風呂敷」の名演
http://www.youtube.com/watch?v=GsS4B-G04I8&feature=related
OSSCAブログ(更新なし?あちら側と交信中?)
http://ossaobirin.blog11.fc2.com/
中野麻衣子+深田淳太郎共編
『人=間(じんかん)の人類学:内的な関心の発展と誤読』はる書房発売
2010年3月31日、定価2000円+税、
ISBN978-4-89994113-5
民族誌の実践とは、場の偶有の共有から始まるプロセスであり、同時に経験の具体性を拠り所とする営みであるに違いない。飲酒と死、死霊と生者、歴史語り、ポトラッチと情報、自己と心、動物と禁忌、消費競争、貝殻貨幣、遊牧民と市場、半男半女の仲人・・・・・多様な民族誌の現場から、人と人、人ともの、ものとものの「あいだ」を描き出す(表紙の帯より)。
第1部 死
第1章 酒に憑かれた男たち
第2章 死霊と共に生きる人々
第2部 民族
第3章 インドネシア・ブトン島ワブラ社会の歴史語りの民族誌
第4章 ポトラッチの行方
第3部 関係
第5章 自己と情緒
第6章 ボルネオ島プナンの「雷複合」の民族誌
第4部 もの
第7章 バリにおける消費競争とモノの階梯世界
第8章 トーライ社会における貨幣の数え方と支払い方
第5部 接合
第9章 取引費用の引き下げ方
第10章 Pan kung ma--the Matchmaker of Tebidu
共編者および執筆者のみなさま、企画から出版に至るまで、たいへんお世話になりました。いろいなことがありましたが、この本づくりは、けっこう楽しかったです。ありがとうございました。わたしたちの先生の導きに特大の感謝を込めて。各論考にコメントを寄せていただいたIさんにも、感謝します。利益なしで、当初の企画段階よりも立派なものに仕上げるよう努めてくださった編集担当者のSさんにも、この場を借りて、謝意を述べさせていただきます。
昨日久しぶりに会った人たちにわたしが罹った感染症のことについて話しているさいに、ある人が「そのことを聞いてびっくりしましたよ、しばらく会わないほうがいい、近づかないほうがいいと思いましたよ」と言ったので、わたしは軽いめまいを覚えた。おそらくその方は、14世紀にヨーロッパで大流行したペストやインカ・アステカ文明を滅ぼした天然痘、日本でも時々流行して人びとを苦しめた麻疹、最近では、飛行機に乗ったワイドスプレッダーによって世界各地に運ばれたSARSなどのイメージの延長線上に、レプトスピラ症というなんだか聞いたこともないような流行り病のことを考えたのかもしれない。SARSがハクビシンという獣から人に感染し、さらには人から人へと広がったという事実、あるいは、豚インフルエンザが豚から人へ、さらには人から人へと染ったという事実認識に照らせば、レプトスピラは人から人へは染らないと言われているが、その方の恐れは得心できなくもないと、わたしは後に考えたのである。
この点に関して思い出すことがある。
中高と同じだったAくんのことである。Aくんは、中学のときに腸チフスに罹って隔離入院し、その後しばらくして学校に復帰した。そのときのことを、彼の病後に中学の先生から話を聞かされた。Aくんは生死の境をさまよったとか、他の人に染らないように保健所の人が彼の家を消毒に来たとか、汚れた水が感染源だからみなさんも飲みものには十分注意しなさいとか、Aくんが勉強の遅れを取り戻すために先生たちも家に行って勉強を教えたというような話だったと思う。その後、わたしは、Aくんとは同じ高校に入学して、3年間同じクラスだった。別の中学から来た同級生Bくんが、どこかから、Aくんの腸チフスの話を聞きつけて、Aくんのいないところで、彼は腸チフスに罹ったことがあり、家と家族が消毒されたこともあるということをどうやら触れ回っているようだった。あるとき、Bくんが、Aくんがいないときにその話題を出したときに、Aくんとわたしの共通の友人であるCくんが、、「B、そんなこというたらあかん、友達やんけ」というようなこと言った。そのとき、わたしには、Cくんが神々しく思えた、Cくんはなんて立派な奴だと思った。Bくんは、その後、そのことを触れ回ることをしなくなったように思う。
それから、高校を卒業して数年後に、電車のなかで偶然Aくんに会ったとき、彼のかつての病気のことやこのエピソードのことがふと頭をよぎった。それは、封印された恐ろしい出来事なのだとも思った。そのことをAくんにはいっさい言わなかったが。今、改めて、高校時代の出来事を思い返してみるならば、Aくんの家の衛生状態などを問題視して、悪意をもって発せられたBくんの言葉を制するように思えたCくんの勇気ある発言は、Bくんの立ち回りを前提として、じつは、Aくんが罹った流行り病を、話題に出してはいけないほどの恐るべき現象へと引き上げたのではなかったのかと思える。結果的に、その流行り病に蓋をすることで、はからずも、逆に、闇の奥に、その病気の恐ろしさを浮かび上がらせることになったのではないだろうか。わたしがAくんにしばらくぶりに会ってすぐさま、隔離され、消毒される恐るべき法定伝染病に侵されたかつてのAくんのことを思い出したように。
こうした問題に、医療人類学はあるヒントを与えてくれるかもしれない。スーザン・ソンタグは、「結核」「ガン」「エイズ」などの病気を例に、それぞれがおかれる文化的な位置づけや社会的なイメージを分析している。結核はかつては才能のある人がかかる美しい病気とされ、ガンは自己を抑える人がかかりやすい病気とされ、エイズは性経験豊富な人の病気とされる。わたしたちは、病気そのものを経験するのでなく、病気の文化・社会的な側面を経験している(池田・奥野『医療人類学のレッスン』45-46頁)。病気は、多分に、そのイメージを伴って、われわれの経験世界に流通する。流行り病が、それと聞いただけで、恐ろしい、近寄らないほうがいいというイメージを連想させるのは、その意味では、何も驚くべきことではないのだ。
さきごろ行われた人類学者たちの集いで、そうした場ではよくあるように、現地で罹った流行り病が話題となった。自分は三日熱マラリアをやったし、彼女はデング熱をやった。アフリカ研究者の誰某は熱帯熱マラリアで危なかった。ファンシダールやクロロキンはもはや効かなくて、メフロキンでもドキシサイクリンでもなく、中国のヨモギからつくった抗マラリア薬が効く。国内でもときどきマラリア様の症状がぶり返す。それを聞いていた北方民族を調査対象にしている人物は、自分は寒いところで、そんな流行病がなくてよかったと言っていた。そうした話は、人類学者どうしの情報交換であるとともに、人類学者としての一種の自負(現地で流行り病に罹ってないなんて、まだ一人前のフィールドワーカーではない!)の語りでもある。その延長線上に、わたしは、わたしが罹った流行り病を、授業ネタなどとしても使えるなと無邪気に考えていたのだが、事態はもう少し複雑であり、慎重に考えたほうがいいかもしれない。流行り病の記号論は、話の聞き手に、それを解釈する手がかりとなるあるイメージを伴って、受け取られる。
(夜中に酔っ払って狩猟の支度をして写真に写るフィールドの人びと)
最近、チャイコフスキーの『白鳥の湖』ばかりを聞いている。オフィスではアンドレ・プレヴィン版、家ではシャルル・デュトワ版、移動中はストコフスキー版をぶっとおしでかけている。1877年の初演のときに酷評されて、チャイコフスキーはその後10年間バレエ音楽は書かなかったという。ロッドバルトに白鳥に変えられ、夜にだけ人間に戻るオデット姫、彼女に恋をしたジークフリート王子と悪魔との戦いの物語。わたしにはバレエのことは皆目分からないが(一回しか見たことがない)、曲の完成度が、全体をつうじて高いと思う。しかし、なぜ聴き惚れているのかというと、おそらくは、この曲を聴いているときの、うっとりとするような至福感のようなものだと思う(悪魔の登場時をのぞく)。いまのところ5日間聴き続けてぜんぜん飽きが来ていない。わたしのお気に入りは、<第2幕 第13曲:白鳥たちの踊り コーダ>の気分がウキウキするような曲から、第3幕にかけての流れである。
http://www.youtube.com/watch?v=T_5WCZ-XvG4
一つには、ルーマニア出身の偉大な宗教学者ミルチャ・エリアーデがどのような小説を書くのか、二つには、その延長線上に、宗教学者兼作家が、この世とあの世をめぐってどのような仕掛けをしているのかを探りたいというのが、ミルチャ・エリアーデの『ムントゥリャサ通りで』(原著1967年、直野敦訳、法政大学出版局、1997年)を読もうと思ったさいの下心にあった。200頁に満たない小説で短時間で読めるが、語られる人物がじつに入り組んでおり、伏線が多く、謎が謎のまま残されているという点で、けっして読みやすい本ではなかった。だいたいの話の筋はこうだ。ムントゥリャサ小学校の元校長ファルマ老人が、教え子であるボルザ少佐を訪ねるところから話は始まる。そんな小学校に通っていた覚えはないという少佐。そのときのファルマ老人の話のなかに、ロシア亡命中に飛行機事故で命を落とした人物の名が出てきたことから、ファルマは警察に監禁されて、取調べを受けることになる。当局の調べに応じるファルマの話は、あっちに行ったりこっちに行ったりして、いっこうに要領を得ない。ファルマの話を読みながら、わたしは、こういう話の噛み合わない人物が、かつては何人かいたようなことを、薄ぼんやりと思い出していた。遠い幼少期の経験に似ている。共有している現実がちがうという事態。子どもだったから、現実そのものが理解できなったということであるのかもしれない。ファルマの話を聞いていると、そういう感覚になる。ま、そういったことは、いまでもあるにはちがいないが。わたしは、いまの教育のあり方の方向を考え出している人が、ファルマ的であるとふと思ったりした。こういう話の腰を折るように見えることも、またファルマ的なのであるが、いずれにせよ、そのファルマの語りのなかに、友達どおしで、ムントリャサ通りの地下室の水中に潜って遊んでいるときに、忽然と姿を消したヨジの話が出てくる。ヨジは、あの世へと旅立ったのである。調べてみたが遺体は見つからなかった。当局の官憲が何人か出てきて、その事件の周りにいた人物のうち、亡命したダルヴァリのことを尋ねたり、さらには、2メートル40センチも身長のあるギリシャ彫刻のような女・オアナのことを尋ねたりして、それに応じて、ファルマ老は話をするのだが、時間を遡ったり、まったく関係のないところから話し出したりして、話はいちじるしく錯綜していく。ファルマの語りのなかには、現実とも非現実とも判定できないがゆえに、興味をそそられる話も出てくる。子どもたちが天空に矢を放っても落ちて来なかったり、ドクトルというマジシャンが人びとを箱のなかに閉じ込めたり、オアラが山のなかで暮らして結婚相手の出現を待つ間牧夫の精を吸い取ってしまうまで盛んに夜な夜な性の交わりを行ったりする話などである。しかし、そうした一貫性のない話へと寄り道をするファルマに、思い出す限りのことを紙に書かせ、話を聞くことによって、いったい、当局は、何のためにこういったことを調べているのだろうか。その点については、官憲によって一切明かされないし、さらには、小説のなかでも明らかにされることはない。このことによってフラストレーションが起こる。それは、ルーマニアの社会的現実に対して向けられた批判だったと捉えることができるのかもしれない。忽然といなくなったヨジをめぐる謎については、小説の終わりのほうで、オアラの結婚式で、オアラが夢のなかで訪れた水底の深い洞窟に神隠しのしるしを見つけて興奮するリクサンドルの話につながっているが、その話によって、すっきりとヨジの消息の謎が解けたわけではない。謎はむしろ深まるばかりである。すべてにわたってこういう調子で、ファルマの前にボルザが現われ、ファルマが身に覚えがないという身ぶりをして、そのボルザがじつはリクサンドルであるということをほのめかすところで、宙ぶらりんのまま話は終わっている。★★★★
親愛なるSさま、
新学期がスタートし、ご多忙のことと存じます。早速ですが、わたしなりに昨日の研究会を以下に手短にまとめます。
まずは、H先生からのコメントを手がかりとして、存在論に関して議論しました。それは、観念論とどう違うのか、さらには、デスコーラのいう存在論とは何かという点に焦点をあてました。ハロウェルが1960年の論文で言っているオジブワの存在論は、アニミズムなどが言語表現されているという事態を指し、われわれがふつういうところの観念論であったのに対して、デスコーラのいう存在論は、実践を踏まえて立ち現れるような人びとの観念世界のことです。
I want to make clear that these four modes of identeification are not mutually exclusive. Each human community may activate any of them according to circumstances, but one of them is always dominant at specific time and place in that it gives to persons who acqired skills and knowledge within a same community of practice the main framework through which they perceive and interpret reality. It is this framework that I call an ontology.(Descola, Philippe "Beyond Nature and Culture. p.8.)
(邦訳)これらの4つのアイデンティフィケーションの4つの様式がお互いに排除的であるというのではないという点を明らかにしよう。人間が集まると、それぞれの状況に応じて、それらの様式のうちの幾つかを動かすようになるが、そのうちの一つが、同じようなふるまいをするような人たちの集まりのなかで、技術と知識を獲得した人たちに与えられるという点で、ある特定の時間と場所において、つねに支配的なものとなる。そして、その主要な枠組みをつうじて、人びとはリアリティーを感知しかつ解釈するのである。この枠組みのことをわたしは存在論と呼ぶのだ。
4つのアイデンティフィケーションの様式とは、①トーテミズム、②アニミズム、③自然主義、④類比主義のことである。大雑把に説明すれば、①トーテミズムは、ある動物との一体感を感じるというようなモードで、身体性+内面性+であると表されます。②アニミズムは、霊現象のように精神性だけを共有しているようなモードで、身体性-内面性+。③自然主義とは、マテーリア(物質)であると捉える一方で、精神性を認めないようモードで、身体性+内面性-。最後に、④類比主義とは、干支でそれぞれがつながっているようなモードのことで、身体性-内面性-となります。こうした4つのアイデンティフィケーションの様式が、お互いに排除的ではなく、つまり、相互に浸透しあうようなかたちで存在しており、同じようなふるまいをする人たちの間で共有されるような、ある支配的な様式が現れてくる。そうしたときの枠組みのことを、デスコーラは存在論と呼んだようなのです。
人間と動物の関係にあてはめるならば、神話世界は、人間と動物が溶け合って一体化している点でトーテミズム的であり、ペットを飼うことは、人間とペットは精神的につながっているのでアニミズム的、動物園で動物を飼育し、市民に公開することは、人間と動物の精神的なつながりがそれほど明瞭ではないという点で自然主義的、さらには、加工して販売された食肉は、原型をとどめないかたちで解体され、人間と動物の間の物質性・内面性ともども粉々に破壊されているという意味で類比主義的だと思われます。しかし、そうしたモードのありようは、必ずしも普遍的なものではありません。動物園の動物と人間の関係は、リンリン・ランランという人気のあるパンダのような動物の場合には、人間と動物のつながりは、俄かに精神性を帯びる場合があります。そうすると、その様態は、トーテミズム的なものに傾くことになります。要は、時と場合によって、その図式は変わりうるのです。デスコーラのいう存在論とは、そうした実践との関わりにおいて移り変わる可能性を含むような枠組みのことなのです。
わたしの理解はまだまだ不十分かもしれませんが、この存在論を軸にして、人間と動物の関係、人間(文化)と自然をめぐる問題について、考えてゆくことは知的にスリリングであるような気がします。
ところで、個々のメンバーの論考についてですが、Kさんは、動物と人間の関係をめぐる生態学的アプローチと象徴論的アプローチおよびその統合アプローチに対して、それらは西洋中心主義であると退けた上で、間側から見る人間をどのように探求すべきかという問題を取り上げています。存在論というキータームによりながら、こうした問題の全容を見取り図にして示そうとする意欲的な内容です。Iさんは、神経生理学教室の自然観を文化領域との関わりから捉えた上で、4つのアイデンティフィケーションのモードを用いて、自然と文化の境界というのは、状況に応じて変容するものであり、その意味で、根拠がないというようなことを示そうとしています。Tさんは、魚にも人間性があるというスリリングな民族誌事例に焦点をあてて、魚への人間性の拡張という捉え方がどのようにして研究者の間に登場したのか、さらには、そうした捉え方が、どのように現地の人たちの魚観(自然観)と同じであり、異なるのかという点の検討を踏まえた上で、自然と社会をめぐる問題を検討しようとしています。わたしはといえば、理論立てを強調することによって分析過多となり、感情や感覚という人びとの実践の重要な部分がすっぽりと抜け落ちてしまう事態を反省して、自然と人間をめぐる民族誌記述の可能性に対して、人類学をふたたび開いてゆくために、エピソードを中心として民族誌を読み上げました。ちょっといきなり感があるので、説明が必要かもしれません。
拙いまとめで申し分けありません。
ひどい文章に疲れ果てたら、アルゲリッチの気力のあふれるピアノ演奏でも聴いてみてください。
http://www.youtube.com/watch?v=JaYx6XfhKZE
(Martha Argerich, Tchaikovsky Piano Concerto No 1 III.Allegro con fuoco)
そのうちに意見交換しましょう。
たんなるエスノグラファーより
(ジャックフルーツがたくさん実っていて甘くておいしいので腹いっぱい食べた。寄生虫はどこにいるか分からない)
バルガス=リョサの『楽園への道』が入った、池澤夏樹個人編集の世界文学全集に入っていたラテン・アメリカ文学だったので、期待して読んでみたが、う~ん、わたしとしては、★三つでしょうね。
わたしの1982年のメキシコへの旅のイメージは、小田実の『何でもみてやろう』のなかのアメリカ・サンディエゴからメキシコのティファナへの国境越えの記述によって形成されていた。小田の旅からおそらく30年近くを経て、わたしもまた、米墨国境において、極めつけの格差を経験することになった。エアコンの効いたグレイハウンドバスの快適な王様のシートは、国境を越えた途端、窓を開けっぱなしてカセットテープのボリュームを最大化して流すオンボロバスの、スプリングが切れて飛び跳ねると天井に頭を打ちつける椅子にへと変わり、物乞いや新聞売りなどがごった返すメキシコへと来たのだなと感じた。
カルロス・フェンテスの『老いぼれグリンゴGringo Viejo』(原著1985、安藤哲行訳、2009年、河出書房新社)は、そうした雑然たる熱気が支配するメキシコの探究であり、さらには、裏返しのアメリカ批判の書でもある。1913年、アメリカの作家・アンブローズ・ビアスは、忽然とその姿を消した。フェンテスは、彼の消息を、この作品のなかでフィクションとして引き受けている。次々と息子と娘、妻を亡くした71歳の老いぼれグリンゴ(アメリカ人)は、見てくれのいい死体になりたいという願望を抱いて、自著2冊、『ドン・キホーテ』などを鞄のなかに詰め込んで、馬で、死ぬためにメキシコに不法に越境してくる。
老いぼれグリンゴのメキシコ滞在を彩るのは、グリンガ(アメリカ人女性)で、父のキューバでの愛人との暮らしを、父の死として隠蔽しながらアメリカで暮らし、恋人を捨ててメキシコにやって来た、31歳のハリエット・ウィンズロー嬢と、農民から革命軍の将軍となり、ハリエットと情交を結ぶようになるアローヨ将軍である。年老いたグリンゴ、若いが精神に不幸を背負うグリンガ、メキシコのマチスモ(男性至上主義)の男の三人が軸となって物語は展開する。物語の後半で、グリンガ・ハリエット嬢は、同時にその二人の男を失う。生き残ったハリエットを軸として見れば、孤独と苦悩のアメリカと、人と人が交わって、英雄主義をまつりあげるメキシコの対比が見えてくる。フェンテスのそのような構図の提示は巧いと思うが、小説としては、全体をとおして、心にダイレクトに届くようなものがいま一つなのである。