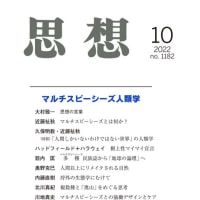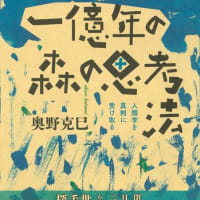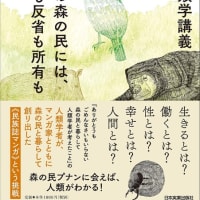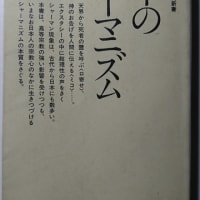本年度の殺生科研の第3回研究会
・10月26日=「来たるべき人類学構想会議・第4回の集い」
・10月27日=桜美林大学・明々館

1.「北方樹林の倫理学者:内陸アラスカにおける動物を殺す/生かすこと」
近藤祉秋(アラスカ大学フェアバンクス校人類学科博士課程)
5カ月弱のフィールドワークに基づいて、アメリカ合衆国アラスカ州の北方アサバスカン文化における「動物を殺す/生かすこと」に関わる調査研究の途中経過が口頭で報告され、質疑などを含めて、活発な議論が行われた。野生の鳥に餌が与えられ、動物を殺すのとは反対に、動物を生かそうとする行為が行われるなど、民族誌データが非常に興味深く、今後の調査の進展が大いに期待される。
2.Rane Willerslev "Not Animal, Not Not-Animal: Hunting, Imitation,and Empathetic Kowledge among the Siberian Yukagirs" Journal of Royal Anthropological Institute(N.S.) 10: 629-652 の仮翻訳に基づく読解
これは、Viveiros de Castro の「観点主義」のベースとなった論文"Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism"を下敷きとしながら、シベリアのユカギールの狩猟における人と動物の関係を解釈した論文である。ウィラースレフは、この論文のなかで、ユカギール人は、動物のように振る舞うが、それは不完全なものであって、決して、完全に動物そのものになってしまうのではないという、「動物ではない、動物でないのでもない」情況を描きだしている。しかしながら、参加者間の議論では、そうした論点を支えるような民族誌データが、全体的に、乏しいという意見が出された。
3.谷泰著『牧夫の誕生』の読書会
これは、西アジアにおける羊・山羊の家畜化の開始とその後の牧畜の展開を、考古学資料や民族誌資料に基づいて、丁寧に跡づけた、牧畜研究書である。あくまでもロジカルに、論証を積み上げてゆく著者のスタイルは明快であり、農耕・狩猟段階から牧畜が開始されたプロセスを辿ることができる一方で、繰り返しが多く、より薄い本にもなり得たのではなかったかという意見が出された。雄誘導羊の去勢と人の去勢を比較するパートは、はたして必要だったのかどうかという疑問の声もあった。我々の主題である「動物殺し」に関しては、「殺して集める」弓矢猟から「集めてから殺す」追い込み猟へ、その後の母子生かしおきを介して、逃げない獲物(=家畜)の発生や、その延長線上で、西アジアの牧夫は、人民統治における西洋の生の管理という牧畜的思考の源泉であった点など、興味深い指摘がたくさんあった。
4.今後の調査や研究の進め方の打ち合わせ
各メンバーの調査研究の進捗の報告の後、今後の科研研究の進め方、なかでも、次回の第4回の研究集会について、さらには、来年度の文化人類学会研究大会の分科会発表などに関して、議論と打ち合わせが行われた。
本年度の過去の研究会については:
殺生科研2013-2
殺生科研2013-1