
わたしたちは、人間らしい生き方とはいったい何か、人間であることの意味とは何かを、毎日、自分自身に問いかけながら生きている。学校教育で、わたしたちは、そうした態度を徹底的に植えつけられるからである。そのため、わたしたちは、人間は動物である、という単純な事実を、日ごろ、忘れてしまっている。
現代日本社会に暮らすわたしたちにとって、動物とは、いったい何か。動物園に行けば、動物たちに出会うことができる。動物園にいるライオンやゾウ、キリンなどが、わたしたちの動物イメージの典型の一つである。あるいは、テディ・ベアやミッキーマウスなどの玩具やキャラクター商品が、わたしたちにとっての「どうぶつ」なのかもしれない。牛肉、豚肉、鶏肉、魚肉は、ほとんどのわたしたちにとっては、おかずの材料としての食料品であって、それらが、動物を解体した結果であるとは、なかなかイメージされないだろう。ペットは、飼われているときは、つうじょう、家族として、人間の一部である。日本全国で、年間30万頭以上のイヌ・ネコが、不用動物として殺処分されているなど思いもよらない。
現代日本人の実感としては、人間として生きる努力をしている反面、自らが動物であることをうっかりと忘れてしまっており、生身の動物から遠くへだたった場所で暮らしているということなのかもしれない。逆に言えば、わたしたち現代人の日常には、生身の動物ではなく、加工され、薄められ、操作されて別のものになったイメージとしての動物が、深く溶け込んでいるということができるのかもしれない。
その一方で、これもまた実感をなかなか伴わないことが多いのだけれども、20世紀の終わりごろに、欧米から動物の権利をめぐるアニマルライツの思想が、日本社会に輸入されてきた。その流れに沿って、畜産工場の屠畜作業が公開された。最近の出来事としては、口蹄疫の感染により、大量の牛豚が殺処分されたニュースが流され、生物多様性条約で、絶滅が危惧される動物の保護が話題にのぼるようになった。そうした動物をめぐる諸問題が、わたしたちの日常の暮らしのなかに、遠くのほうからなだれ込んできた感がある。わたしたちは、そうした、ややぼんやりとした、動物襲来とでもいうべき時代を生きているのではないか。
(とれたてのイノシシを触るプナンの子ども)










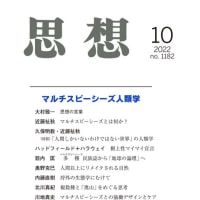

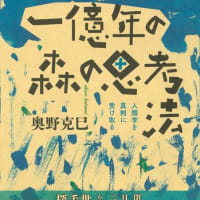
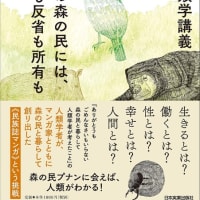



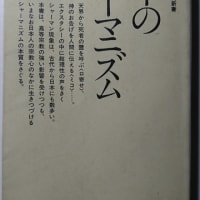


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます