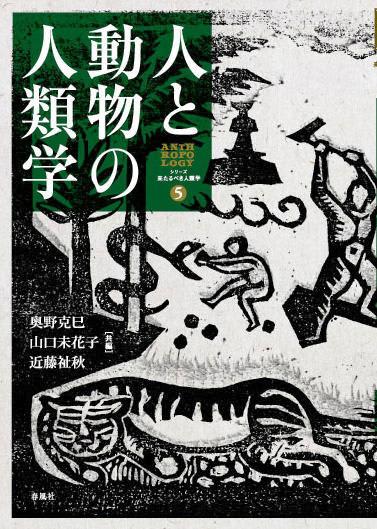夜行バスの移動を含めて延べ6日間の日程で、学生たちと、仙台から三陸海岸を経て、北は田老町、内陸は遠野、盛岡まで足を延ばした。
明治二十九年、昭和八年の三陸沖地震の津波などの後に、<海嘯記念碑>や<津波碑>が建てられている。それらは、津波災害の記録と、その後世への伝承を目的としたものではあったが、それらの碑の建立の起源の部分には、津波の災害で亡くなった人たちを弔う気持ちがあったのではないか。石碑は、墓碑でもあったのだ。そうした仮説は、現在、残すか残さないかで揺れている数々の<震災遺構>に、被災して逝った人たちへの弔いのための祭壇が設けられていて、それらが慰霊の場となっていることが多いことに一致符合する。
鉄骨を用いて建てられたがゆえにつぶれてしまうのではなく、倒れて残骸化する建造物の遺構化は、その意味で、災害の歴史にとって、きわめて新しい現象であるような気がする。かつては、残らなかったがゆえに、その場所で死んだ人たちを弔い、災害の記憶を継承するためには、新たにいしぶみを築くほかなかったのではないだろうか。
被災地震災遺構フィールドワーク報告
遠野では、柳田國男の『遠野物語』を片手に、千葉家の曲り家、続き石、カッパ淵、デンデラ野、ダンノハナ、卯子酉様、山崎金勢様、五百羅漢、程洞金勢様などをめぐった(写真は、デンデラ野の近くの、美しすぎる田園風景)。道のいたるところにみられる石碑。早池峰大神、金毘羅大権現、山神などの碑。程洞神社の金勢様を見に行ったときには、その森に、神々が棲むような気がした。異界は、つねに、そうした場所をつうじて、私たちに開かれている。遠野には、『遠野物語』のせいか、いたるところに、異界への入り口があるように感じられる。人びとは、つねに、外部の霊力に接続してきた。