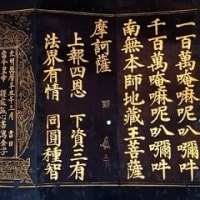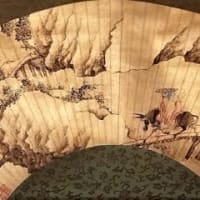〇鶴見良行『バナナと日本人:フィリピン農園と食卓のあいだ』(岩波新書) 岩波書店 1982.8
 大衆食品として日本人に親しまれているバナナ。しかしその背後には、多国籍企業の暗躍、農園労働者の貧苦、さらに明治以来の日本と東南アジアの歪んだ関係が隠れていることを紹介する。1979-80年、国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)が実施したバナナ経済の研究調査に基づく報告である。岩波新書の名著の1冊で、いつか読もうと気に掛けながら読んでいなかった。たまたま旅先で読む本が切れて立ち寄った書店で本書が目についたので、読んでみることにした。
大衆食品として日本人に親しまれているバナナ。しかしその背後には、多国籍企業の暗躍、農園労働者の貧苦、さらに明治以来の日本と東南アジアの歪んだ関係が隠れていることを紹介する。1979-80年、国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)が実施したバナナ経済の研究調査に基づく報告である。岩波新書の名著の1冊で、いつか読もうと気に掛けながら読んでいなかった。たまたま旅先で読む本が切れて立ち寄った書店で本書が目についたので、読んでみることにした。
日本のバナナ輸入先は、台湾→エクアドル→フィリピンと変遷してきた。フィリピンでは、ミンダナオ島においてアメリカ資本の多国籍企業が日本市場を念頭に置いてキャペンディッシュ種のバナナを生産している。
戦前、ミンダナオのダバオには日本人が進出し、麻農園を開いた(麻は軍艦のロープのほか、和紙や真田紐の原料に使われた)。土地の所有をめぐって伝統的な諸種族との間に軋轢が起こり、日本人の増加する1910年代末からは邦人殺害事件が頻発した。一方、日本人労働者の勤勉さはよく知られていた。フィリピン人の麻農園の生産性が低かったことは、日本人の勤勉とフィリピン人の怠惰という紋切り型の文化観で説明されがちだが、そもそも雇用の形態が異なり、当時のフィリピン人労働者はいくら努力しても独立の希望がなかったことを著者は丁寧に指摘する。
太平洋戦争中、フィリピンは日本軍に占領される。日本は、ここを敵国アメリカから奪い取ることが重要だっただけで、特に必要な土地ではなかった。砂糖やタバコ、麻など日本に不要な農産物の畑は、ゲリラの活動を抑える目的もあって、数千ヘクタールも焼き払われた。こうして農民の生活手段を奪われたことが、戦後のフィリピンの出発にどれだけ打撃になったか、あらためて愕然とした。
1958年、フィリピン政府は日本市場の自由化に備えて輸出バナナの生産を決定する。そうかー。20世紀の農業は、風土に適した農産物が徐々に販路を広げていくなどという牧歌的なものではなくて、海の向こうに新たな巨大市場が発見されると、誰もつくったことも食べたこともない農作物の生産がいきなり立ち上がるのだ。ミンダナオのバナナ農園は「日本人の食欲を満たすための農園だった」というのが怖い。でも、現在もこうした第一次産業が、世界の各地で生まれているのだろう。
日本の市場に向かうミンダナオのバナナの出口を預かるのは4つの外国企業(チキータ、デルモンテ、ドールの3つのアメリカ企業と住友商事)。外国企業は地場農園、契約農家、労働者を序列化して巧妙に支配している。最底辺の労働者は経済的に囲い込まれており、彼らの世界には市場原理が働かない。出荷物は、生産性向上に努めれば努めるほど安い価格で買い上げられ、農園の親方が経営するサリサリ・ストア(雑貨店)にツケを溜めながら日々の暮らしを細々とつないでいく。こういう雇用者と被雇用者の非対称な関係は昔話ではなく、21世紀の現在でも、社会の各所にあると思う。
バナナが日本の消費者に向けて出ていく一方、フィリピンのどの村にも、外国製品であるコーラとインスタント・コーヒーとビールのサン・ミゲルが入り込んでいる。著者はこの状態を「買う自由、買わされることの残酷さ」と表現している。他国の自由だけが村に押し寄せてくる。他国の自由が彼らを不幸にし、彼らの不自由が私たちの自由を可能にしている。戦後、植民地というものがなくなった国際世界でも、「持てる国」と「持たざる国」の支配・被支配関係が連綿と続いていることは忘れないようにしたい。
最後に日本に到着したバナナが、むろ屋さんによって黄色く熟成されてから小売り業者に渡っていたことも初めて知った(※参考:2016年の記事/株式会社まつの)。本書のもとになった調査からすでに40年が経過し、バナナの生産状況も日本の輸入状況もずいぶん変わっているのではないかと思う(改善されていることを望む)。私は、あまり好んでバナナを食べないが、バナナに限らず、自分の食べているものが、どこでどのように作られているのか、ときどき関心を持つようにしたい。