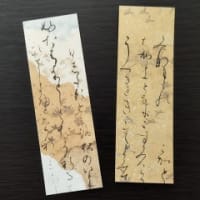○奈良国立博物館 特別展『第64回 正倉院展』(2012年10月27日~11月12日)
今年はやめておこうかなあ…と思いながら、やっぱり行きたくなって、週末スケジュールを調整して、飛び出していく。今回は開催初日に観覧。昨年と同じで、朝8時半頃に行って、テラスの行列の三折目に並んだ。これ以上早く並んでも、あっと言う間に会場内がいっぱいになってしまうので、同じことだと思う。今年の見ものは琵琶とか瑠璃の坏とか、あまり小さいものではないので、人だかりの後ろからでも大丈夫だろう、とも予測。
第1室。最初のブロック(南側)は大混雑なので、突き当たり(東端)の琵琶あたりから行こうかな、と思って、ぎょっとした。テレビカメラが入っていたのだ。初日の朝って、マスコミ取材が入るのか。そこは避けて、折り返しの後半ブロック(北側)から見始める。初めに『木画紫檀双六局(もくがしたんのすごろくきょく)』。見覚えがあると思ったが、双六盤にしては罫線がないなあ、と初めて気づく。別の展示ケースには、『黄瑠璃双六子(きるりのすごろくし)』をはじめ、緑、朝緑、藍など色ガラス製の双六の駒。各色15枚ずつ伝わっているが、藍色は1枚しか伝わらないそうだ。今年の大河ドラマ『平清盛』を思い出してしまうが、劇中の双六の駒よりずっと小さい。シャツのボタン、あるいは肝油ドロップくらい(←今でもあるのかしら)。
さらには『双六筒(すごろくのつつ)』『双六頭(すごろくとう=サイコロ)』も、ぬかりなく取り合わせてあって、感激した。双六筒には、よく見るとタンポポのような草花が金銀で描かれていたが、華美ではなくて、よく使いこまれた感じがした。聖武天皇も双六に興じられたのだろうか(後白河法皇みたいに)。
図録の解説を読んだら、大中小計6個のサイコロの1つ(小)は、表裏の目の組み合わせが7になっていないという。え!裏面に鏡が用意されていたのだから、ちゃんと確認しておけばよかった。
ここで混雑の中、前半ブロックに立ち戻る。今回は楽器が中心で、『甘竹簫(かんちくのしょう)』『鉄方響(てつのほうきょう)』は、実際に演奏してみたときの録音が会場に流れている。『螺鈿紫檀琵琶(らでんしたんのびわ)』は、パネルの拡大写真を見たら、螺鈿で表わされた迦陵頻伽が驚くほど可愛い(図録にも掲載)。『紅牙撥鏤撥(こうげばちるのばち)』は、華麗な細工もだが、その薄さに驚く。
第2室の展示物は『瑠璃坏(るりのつき)』だけで、最前列で見たい人は列に並ぶ方式。ポスターで見るより濃い印象の藍色である。そして銀製の台脚・受座の細工が素晴らしい。西アジアの産であることは間違いないだろうけれど、よくまあこの極東の地まで伝わり、今日まで損なわれずにきたものだ。今回は、関連してガラス製品の展示が多かったが、『雑色瑠璃(ざっしょくのるり=さまざまなガラス玉)』も面白かった。
あと『密陀彩絵箱(みつださいえのはこ)』が面白かった。躍動感あふれる文様をよく見ると、口を大きく開けたユーモラスな怪鳥・怪魚が描かれている。正倉院文物の装飾って、キレイ・カワイイだけじゃないんだな、と思った。
いま、奈良博のサイトで「出陳品一覧」(PDFファイル)を参照しながら記事を書いていて気づいたが、ネット上の「出陳品一覧」には「前回出陳年」が載っていて、とても参考になる。しかし、会場内で配られていた印刷版の「出陳目録」だと、このデータがない(初出陳に○だけ)。どうしてだろう?
『螺鈿紫檀琵琶』は、前回出陳が2000年とあって、思わず自分のブログを検索したら、2010年の『螺鈿紫檀五絃琵琶』とも、2009年の『紫檀木画槽琵琶』とも別物なんだな、ということが分かった。正倉院には、五絃琵琶1点と四絃琵琶は5点が伝わるらしい。「出陳品一覧」リストを見ると、2000年以降に1回でも出陳されているものは稀だということが分かる。やっぱり20年くらい通い続けないと、宝物の全貌は見えてこないんだな…。
今年はやめておこうかなあ…と思いながら、やっぱり行きたくなって、週末スケジュールを調整して、飛び出していく。今回は開催初日に観覧。昨年と同じで、朝8時半頃に行って、テラスの行列の三折目に並んだ。これ以上早く並んでも、あっと言う間に会場内がいっぱいになってしまうので、同じことだと思う。今年の見ものは琵琶とか瑠璃の坏とか、あまり小さいものではないので、人だかりの後ろからでも大丈夫だろう、とも予測。
第1室。最初のブロック(南側)は大混雑なので、突き当たり(東端)の琵琶あたりから行こうかな、と思って、ぎょっとした。テレビカメラが入っていたのだ。初日の朝って、マスコミ取材が入るのか。そこは避けて、折り返しの後半ブロック(北側)から見始める。初めに『木画紫檀双六局(もくがしたんのすごろくきょく)』。見覚えがあると思ったが、双六盤にしては罫線がないなあ、と初めて気づく。別の展示ケースには、『黄瑠璃双六子(きるりのすごろくし)』をはじめ、緑、朝緑、藍など色ガラス製の双六の駒。各色15枚ずつ伝わっているが、藍色は1枚しか伝わらないそうだ。今年の大河ドラマ『平清盛』を思い出してしまうが、劇中の双六の駒よりずっと小さい。シャツのボタン、あるいは肝油ドロップくらい(←今でもあるのかしら)。
さらには『双六筒(すごろくのつつ)』『双六頭(すごろくとう=サイコロ)』も、ぬかりなく取り合わせてあって、感激した。双六筒には、よく見るとタンポポのような草花が金銀で描かれていたが、華美ではなくて、よく使いこまれた感じがした。聖武天皇も双六に興じられたのだろうか(後白河法皇みたいに)。
図録の解説を読んだら、大中小計6個のサイコロの1つ(小)は、表裏の目の組み合わせが7になっていないという。え!裏面に鏡が用意されていたのだから、ちゃんと確認しておけばよかった。
ここで混雑の中、前半ブロックに立ち戻る。今回は楽器が中心で、『甘竹簫(かんちくのしょう)』『鉄方響(てつのほうきょう)』は、実際に演奏してみたときの録音が会場に流れている。『螺鈿紫檀琵琶(らでんしたんのびわ)』は、パネルの拡大写真を見たら、螺鈿で表わされた迦陵頻伽が驚くほど可愛い(図録にも掲載)。『紅牙撥鏤撥(こうげばちるのばち)』は、華麗な細工もだが、その薄さに驚く。
第2室の展示物は『瑠璃坏(るりのつき)』だけで、最前列で見たい人は列に並ぶ方式。ポスターで見るより濃い印象の藍色である。そして銀製の台脚・受座の細工が素晴らしい。西アジアの産であることは間違いないだろうけれど、よくまあこの極東の地まで伝わり、今日まで損なわれずにきたものだ。今回は、関連してガラス製品の展示が多かったが、『雑色瑠璃(ざっしょくのるり=さまざまなガラス玉)』も面白かった。
あと『密陀彩絵箱(みつださいえのはこ)』が面白かった。躍動感あふれる文様をよく見ると、口を大きく開けたユーモラスな怪鳥・怪魚が描かれている。正倉院文物の装飾って、キレイ・カワイイだけじゃないんだな、と思った。
いま、奈良博のサイトで「出陳品一覧」(PDFファイル)を参照しながら記事を書いていて気づいたが、ネット上の「出陳品一覧」には「前回出陳年」が載っていて、とても参考になる。しかし、会場内で配られていた印刷版の「出陳目録」だと、このデータがない(初出陳に○だけ)。どうしてだろう?
『螺鈿紫檀琵琶』は、前回出陳が2000年とあって、思わず自分のブログを検索したら、2010年の『螺鈿紫檀五絃琵琶』とも、2009年の『紫檀木画槽琵琶』とも別物なんだな、ということが分かった。正倉院には、五絃琵琶1点と四絃琵琶は5点が伝わるらしい。「出陳品一覧」リストを見ると、2000年以降に1回でも出陳されているものは稀だということが分かる。やっぱり20年くらい通い続けないと、宝物の全貌は見えてこないんだな…。