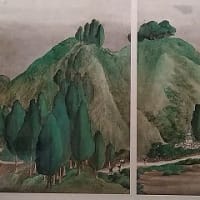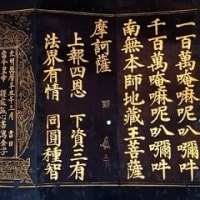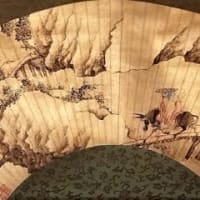〇永青文庫 早春展『細川家と中国陶磁-名品でたどる中国のやきもの-』(2018年2月10日~4月11日)
興味のある展覧会だったので、始まって早々に見に行った。同館の設立者である細川護立は、大正末年のヨーロッパ旅行中から中国の古美術品を本格的に蒐集し始めた。また細川家は、三斎(忠興)以来、茶の湯に親しみ、「唐物」と呼ばれた中国の陶磁器を含む、優れた茶道具の数々を伝えている。その結果、永青文庫は、古く漢代から清代まで100点を超える中国陶磁を所蔵しているが、本格的な中国陶磁展を開催するのは、実に17年ぶりとのこと。私にとっては、たぶん初めての体験だと思う。
会場は4階から。まず最も古い漢代の灰陶が2点。2番目が、SNSで写真を見てびっくりした『灰陶三人将棋盤』という珍品である。三方向から駒を進めることができるよう、将棋盤はY字型をしている。中心部には三角形の「海」があり、三方には「山」、その背後に「城」があり、「城」の背後に駒の並べ方が文字で示されている。いちばんよく見えた列は「車馬相士將士相馬車」だったと思う。あとの二方向は、少し文字が違っているように思えた。これ、とても面白かったので、図録代わりの雑誌「永青文庫」に何か解説が載っているだろうと期待したのに、写真すら載っていなかったのにはガッカリ。まだ分からないことが多くて何も書けないのかなあ。ほんとに漢代(前2-3世紀)の品なのかも疑っておこう。
なお、ネットで「三人将棋」を検索すると、昭和初期に日本人が発明した「国際三人将棋」というのがヒットすることは初めて知った。囲碁に比べると、将棋の歴史は分からないことが多いようだ。
灰陶加彩馬(北朝時代、6世紀)はシンプルで堂々とした造形。続いて、時代は唐代に飛び、三彩の名品が並ぶ。現代の工場でお土産用に量産されている唐三彩と違って、色味は決して多くないのに、品があって大胆で美しい。盤面全体を覆う小さな白い斑点が華やかな『三彩宝相華文三足盤』が一押し。緑釉が目立つ『三彩花文盤』も好き。唐三彩は、1904年に始まる卞洛鉄道工事等によって掘り起こされた唐代の墳墓から、初めて見つかったものだ。細川護立が唐三彩を褒めると「墓から出たものを飾るのはなんだか変ですよ」と言われたそうだが、「どこから出ようといいものはいい」という姿勢を貫いたという。三彩馬も三彩獅子も三彩女子も、護立の選択眼は確かにいい。
次に宋代のやきもの。磁州窯もやはり20世紀の初めから注目を集めるようになった。『白釉黒花牡丹文瓶』は優美で風格のある名品だが、磁州窯としては少し整いすぎな感じがする。私は『白釉鉄絵瓢形水柱』が面白くて気に入った。縦縞柄の磁州窯はいくつか見たことがあるが、これは瓢箪形に横縞柄という珍しいものだった。定窯の『白磁長頸瓶』は故宮伝世品とのこと。硬質の白い肌に、展示ケースの白とオレンジの小さな照明が点々と反射して、仏菩薩の瓔珞のように見えた。あと、4階展示室の入口には、白い大理石の石仏(唐代)が常時置かれているのだが、今季の展示内容とマッチしていて、仏様も少し嬉しそうだった。
3階展示室は明清のやきもの。五彩、青花、青磁など。悪趣味すれすれで面白かったのは『金琺瑯蓋付馬上杯』。『白磁明笛』は実用品だそうで、武侠ドラマに出てきそうだと思った。
2階は茶道具としての中国陶磁。『油滴天目』(金代)は口径が大きくて、小どんぶりくらいあるのではないかと思った。ただし裾がきゅっと縮まっているので、量はそんなに入らなそうである。『黒釉油滴斑壺』の美しさには見とれた。黒釉の上にうっすらと載る銀色の油滴。この渋さ!! 『黄天目』と『黄天目(珠光天目)』という2つの茶碗もよかった。「黄」というほど明るい色合いではなく、黒釉が錆を吹いたような風情。黒楽茶碗を思わせて、大変よかった。
興味のある展覧会だったので、始まって早々に見に行った。同館の設立者である細川護立は、大正末年のヨーロッパ旅行中から中国の古美術品を本格的に蒐集し始めた。また細川家は、三斎(忠興)以来、茶の湯に親しみ、「唐物」と呼ばれた中国の陶磁器を含む、優れた茶道具の数々を伝えている。その結果、永青文庫は、古く漢代から清代まで100点を超える中国陶磁を所蔵しているが、本格的な中国陶磁展を開催するのは、実に17年ぶりとのこと。私にとっては、たぶん初めての体験だと思う。
会場は4階から。まず最も古い漢代の灰陶が2点。2番目が、SNSで写真を見てびっくりした『灰陶三人将棋盤』という珍品である。三方向から駒を進めることができるよう、将棋盤はY字型をしている。中心部には三角形の「海」があり、三方には「山」、その背後に「城」があり、「城」の背後に駒の並べ方が文字で示されている。いちばんよく見えた列は「車馬相士將士相馬車」だったと思う。あとの二方向は、少し文字が違っているように思えた。これ、とても面白かったので、図録代わりの雑誌「永青文庫」に何か解説が載っているだろうと期待したのに、写真すら載っていなかったのにはガッカリ。まだ分からないことが多くて何も書けないのかなあ。ほんとに漢代(前2-3世紀)の品なのかも疑っておこう。
なお、ネットで「三人将棋」を検索すると、昭和初期に日本人が発明した「国際三人将棋」というのがヒットすることは初めて知った。囲碁に比べると、将棋の歴史は分からないことが多いようだ。
灰陶加彩馬(北朝時代、6世紀)はシンプルで堂々とした造形。続いて、時代は唐代に飛び、三彩の名品が並ぶ。現代の工場でお土産用に量産されている唐三彩と違って、色味は決して多くないのに、品があって大胆で美しい。盤面全体を覆う小さな白い斑点が華やかな『三彩宝相華文三足盤』が一押し。緑釉が目立つ『三彩花文盤』も好き。唐三彩は、1904年に始まる卞洛鉄道工事等によって掘り起こされた唐代の墳墓から、初めて見つかったものだ。細川護立が唐三彩を褒めると「墓から出たものを飾るのはなんだか変ですよ」と言われたそうだが、「どこから出ようといいものはいい」という姿勢を貫いたという。三彩馬も三彩獅子も三彩女子も、護立の選択眼は確かにいい。
次に宋代のやきもの。磁州窯もやはり20世紀の初めから注目を集めるようになった。『白釉黒花牡丹文瓶』は優美で風格のある名品だが、磁州窯としては少し整いすぎな感じがする。私は『白釉鉄絵瓢形水柱』が面白くて気に入った。縦縞柄の磁州窯はいくつか見たことがあるが、これは瓢箪形に横縞柄という珍しいものだった。定窯の『白磁長頸瓶』は故宮伝世品とのこと。硬質の白い肌に、展示ケースの白とオレンジの小さな照明が点々と反射して、仏菩薩の瓔珞のように見えた。あと、4階展示室の入口には、白い大理石の石仏(唐代)が常時置かれているのだが、今季の展示内容とマッチしていて、仏様も少し嬉しそうだった。
3階展示室は明清のやきもの。五彩、青花、青磁など。悪趣味すれすれで面白かったのは『金琺瑯蓋付馬上杯』。『白磁明笛』は実用品だそうで、武侠ドラマに出てきそうだと思った。
2階は茶道具としての中国陶磁。『油滴天目』(金代)は口径が大きくて、小どんぶりくらいあるのではないかと思った。ただし裾がきゅっと縮まっているので、量はそんなに入らなそうである。『黒釉油滴斑壺』の美しさには見とれた。黒釉の上にうっすらと載る銀色の油滴。この渋さ!! 『黄天目』と『黄天目(珠光天目)』という2つの茶碗もよかった。「黄」というほど明るい色合いではなく、黒釉が錆を吹いたような風情。黒楽茶碗を思わせて、大変よかった。