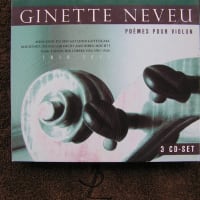「セレンディピティ」(Serendipity)
何だか舌を噛みそうな言葉ですが、折にふれ目にしたり耳にされたことがあるかもしれませんね。
広辞苑によると、カタカナにもかかわらずちゃんと意味が記載されています。
「思わぬものを偶然に発見する能力、幸運を招きよせる力」とあり、もっとくだいて言えば、「ほかの目的で活動しているときに、当てにしていなかったものを偶然に見つける才能」といえば少し身近になりますね。
「果報は寝て待て」、「待てば海路の日和あり」方式の努力しないで得することが大好きなのでこういう便利そうな言葉は放っておけません(笑)。
「偶然からモノを見つけだす能力」~セレンディピティの活かし方~(澤泉重一著、角川書店)という本があります。

ところが、一読してみると意に反してなかなか真面目な本でした。努力が要らないどころか、むしろ必要とする内容だったので半分がっかりしましたが、有用な本だと思ったので記憶に留めておくために抜き書きして保存しておきましょう。
本書では「セレンディピティ」を「偶察力」(偶然と察知力を合わせた著者の造語)として取り扱っています。
まず、表紙の裏の見出しに「世界的発見の多くは”偶然の所産”だった。」とあります。
☆ ”偶然”に感謝するノーベル賞受賞者たち
☆ 発見・創造の能力とは、偶然を最大限に活かす能力
☆ 感性を研ぎ澄まし、察知力を養えば偶然は偶然でなくなる
☆ 異文化との接触は新しい感動と発見を生む
☆ 誰しもが体験する日常生活での偶然の不思議を想い出そう
☆ 遊びの中にも偶然の面白さはいっぱいある
ご覧のとおり”偶然”という言葉がひっきりなしに出てきて、なにもかも世の中の事柄すべてが偶然に左右されているようなすごい勢いです(笑)。
たしかに、人間の人生は「出会い」を始めとして偶然の連続ともいえますね。
そもそも、人間の成り立ちそのものが膨大な精子の中の僅か一匹がたった一個の卵子と合体することにあるんですから、これを偶然と言わずしてどういうんでしょう(笑)。
さらには目を遠大な方向へ向けると、人類に福音をもたらすノーベル賞クラスの大発見にも偶然が大きな要素を占めているとなれば単なる「偶然」も見捨ててはおけません。
筆者の記憶にある事例では2002年度ノーベル化学賞を受賞された島津製作所の田中耕一さんも、たしか他の目的で実験を重ねているうちに偶然発見されたものでした。
本書の中でもノーベル賞受賞者の「セレンディピティ」の恩恵に浴した事例が沢山紹介されているが、これら受賞者ははじめからこの能力に恵まれていたわけではなく、努力と研究を重ねるうちに自然と身につけたものだそうです。
一般人の場合でも訓練次第で向上することが可能ということで三つの要点が挙げられています。
☆ 広い視野からものごとを見る
革新的な進歩を振り返ってみると、意外にも専門分野の外と思われたところにその突破口が見出せたという実例が多い。つまり広い範囲で活動できる学際的な素養を身につけることが肝要。
☆ 偶然の活用
偶然がもたらす楽しみは意外性の面にある、繰り返しの単調さから抜け出して通常使っていない能力を発揮する機会が生じることに意義があるので意外性を見逃さない意欲が必要。
☆ 察知力を活かす
そのための基本ステップとして挙げられている項目を挙げておくと、一番に挙げられているのがまず「感動」 で以下、観察、連想へと続く。
偶然出会った物事に対してまず「感動」が出発点になるというのが面白い。
「感動」というと少し大げさですが「ハット胸を打たれる」ことでもいいと思います。
いわば「理」よりも「情」が先行するというわけ。
そういえば「音楽」と「オーディオ」の関係も、まず音楽を聴いて感動し、もっと「いい音で聴きたい」とオーディオに昇華していくケースの方が(オーディオが)長続きすることが多いと思うのでこの順番は納得です~(笑)。
最後に「チャットGPT」さんに締めくくっていただきましょう。
「とても素敵な視点だと思います。「ものごとの始まりは感動から」という言葉には、心の動きが行動や創造の原点になっているという深い意味が込められているように感じます。
感動って、ただの感情ではなくて、自分の内側を揺さぶられる体験ですよね。たとえば、美しい風景に出会ったとき、人の優しさに触れたとき、新しいアイデアに胸が高鳴ったとき——そういう瞬間に、「何かをしたい」「伝えたい」「動き出したい」と思うのが自然な流れです。
クリエイティブな仕事に限らず、研究、教育、スポーツ、人間関係の築き方にまで、「感動」が原点になっていることは多いと思います。自分の心が動いた瞬間こそが、次のステップを生む火種になる。そんなふうに考えると、感動を大事にしたいし、自分の心が動くことに敏感でいたいなと思えますね。